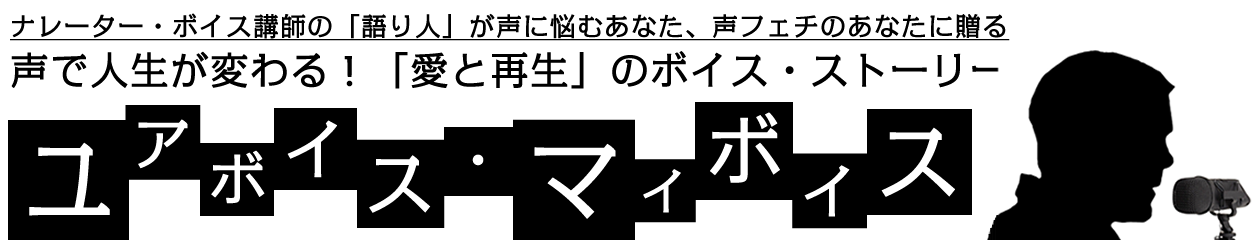それから少しして、僕たちと同世代とおぼしき男が席にやってきた。
きっと店長だろう。「他のお客さまのご迷惑になりますので」とかなんとか言われて店を追い出されるに違いない。僕も一柳も覚悟した。
(3章「一流の美少女」のつづき)
男はオーナー店長の山田と名乗り、名刺を差し出して言った。
「うちの茂森がお客さまの貴重なお時間を頂戴したようで、大変ご迷惑をおかけしました。失礼は承知ですが、どうかお詫びをさせてください。ほんの気持ちですが」
そう言って山田店長は「あゆみちゃん、お持ちして」と厨房のカウンターで待機していた茂森さんに声をかけた。
茂森あゆみ…。どんな漢字をあてるのだろう。いくつか字面を思い浮かべていると、茂森さんがあのシャンパンスマイルで、ビールジョッキふたつと焼き鳥の盛り合わせが入った大皿を運んできた。
レッドカードを突き付けられ退場を覚悟していた僕と一柳は「いえいえ、そんな。とんでもないことです」と恐縮して言った。「こちらこそ、おたくの店員さんを巻き込んでおしゃべりに花を咲かせてしまい、つまりその、業務を停滞させてしまって申し訳ありません」と頭を下げた。
「ですから悪いのはこちらで、このようなことをしていただいては…」
そんなことを二人でかわるがわる申し述べ遠慮したのだけど、店長も茂森さんもニコニコ顔で料理皿を並べたり片づけたりしている。
それから店長は「あゆみちゃん、3番さんのご注文をお聞きして」そう指示し、茂森さんを外させてから僕たちに言った。
「おふたりのプロの生声を目の当たりにして、また親しくお話をさせていただいて茂森はもう大感激しています。あの子の夢は、私どもスタッフみんなが応援しているんですよ」
「店長さんはじめバイト先のみんなが応援してくれているなんて恵まれていますね。もちろんそれは、彼女の魅力がそうさせているのでしょう。よくわかります」と僕は正直な感想を述べた。
すると店長は声を潜めて言った。「あの、語り人さん。こんなことをお訊ねするのは愚の骨頂だということは承知しています。それを承知であえてお伺いしたい。あの子は夢を叶えることができるでしょうか」
「山田さん、そんなことは誰にもわかりませんよ」。僕はふだん思っていることを率直に口にした。
「才能や運不運、タイミングもあるでしょう。でも、これだけは言えます。あきらめなければ、あきらめさえしなければ、かならず叶います。そこに才能や運不運が入り込む余地はありません。もっともこれは一般論ですが」そう言ってから付け加えた。
「台本を読ませてみないことには何とも言えませんが、さっきお話をしてみて、茂森さんの言葉の扱い方のセンスに非凡なものを感じました。言葉の反射神経がいいんですね。いろんな意味で「間」の良い子だと思います。声そのものの魅力も持っています。あとは、あきらめないというもうひとつの才能を持っているかどうか」
「あきらめないという、もうひとつの才能ですか…」店長はこの言葉をかみしめるように繰り返してから、得心したように言った。「語り人さんにお伺いしてよかった。誠実で深みのある素晴らしいお答えです。愚問が愚問でなくなった。ありがとうございました」
「では僕からも、愚の骨頂のお願いをさせてもらいます」
僕は気になっていることを口にした。
「茂森さんに悪い虫がつかないよう気をつけてあげてください。彼女の笑顔に勘違いするバカ男は少なくないでしょう。異性だけではありません。同性からの嫉妬によるいやがらせもあると思います。それでも、あの笑顔が損なわれることのないよう守ってあげてほしい。あの強くてまっすぐな眼差しが、理不尽なハラスメントや不躾な視線によって曇ることのないよう、守ってあげてほしいのです」
「ちょっと気障な言い方をしてしまいました」と照れ笑いをしていると、店長は両手で僕の手をぎゅっと握り「なんて素晴らしい!」と感激の面持ちで言った。「茂森のこと、一目で見抜かれたのですね。実は、語り人さんのご推察どおりなんです」声のトーンを落として店長はつづけた。
茂森さん目当てに来店する無害のお客はともかく、外で待ち伏せしたり、後をつけたり、写メを撮ったり、卑猥な言葉を浴びせたりするストーカーは少なくないそうだ。養成所内にも彼女をつけ狙う不埒な男子は多いのだという。
「つらい思いや気味の悪い思いをたくさんしている子ですが、でも彼女はね、とても利口な子なんです。ああ見えて気は強いし芯も強い。実は腕っぷしだって強い。自分の身を守るすべは心得ている子です。そのために両親は、幼いころから彼女に空手を習わせました。今でも道場に通っているんですよ。黒帯、二段の腕前です」
「並みの男に手は出せない。安心しました。それに、山田さんのような良き理解者、親代わりのような存在がいることが何より心強い」
僕がそう言うと店長は、自分の役割に満足している人のようにほほ笑むと、また少し声のトーンを落として言った。
実は茂森さんの両親は、娘の「声優になりたい」という夢に反対していたという。そこで茂森さんは去年、20歳の誕生日を迎えた日に、両親に対して交換条件を持ち出した。
それは、大学の勉強もしっかりやって必ず卒業すること。声優学校の費用はアルバイトをして自分で捻出すること。二年間やってめぼしい成果が出なければ、そのときはすっぱりあきらめること。この三つを約束して、彼女は親を説得した。そしてすぐにアルバイトを決めた。
「それがこの店というわけです」と店長は言った。「実は彼女の父親の会社が目と鼻の先なんです。そんなご縁でよく利用していただいていまして、彼女もお父さんと一緒に何度かきたことがあります。だから、ひとりで店に訪ねてきてバイトさせてほしいと言われたときは、それはびっくりしましたよ。すぐに茂森さんに電話をしたら茂森さんもびっくりして、会社からすっ飛んできました。まあ最終的に、ここは大学からも近いしと、けっきょく父親が折れるかたちで…」
「お父さんは、監視ではないですが、娘の働きぶりをよく覗きにくるんですか」と僕は訊いてみた。
「それが彼女が店に出ない日はくるんですが、出勤の日はこないんですよ。ちゃんとシフトを把握してるわけです。まあ、仕事上がりに娘がバイトしている店で一杯やるのは、気が引けるんでしょうね」
「気が引けるというより、緊張して酔っぱらえないでしょう。愚痴もこぼせない、バカ話もできない、女房の不満も言えない。それになんといっても、下ネタが言えない」僕がそう言うと、店長は「たしかに」と大笑いした。
そこへ店長を呼ぶスタッフの声がした。山田店長は声の主を一瞥してから、あらためて僕たちに礼を述べた。店員ばかりか店長の自分までお二人の時間を奪ってしまった。度重なる非礼をどうかお許しいただきたい。心のこもった貴重なアドバイスも感謝に耐えない。今夜は時間の許すかぎり飲んで食べて帰ってほしい。
そんなことを言って店長は席を離れた。茂森さんがまっすぐな眼差しでうれしそうにこちらを見ていた。軽く手を上げて僕はその視線に応えた。彼女も胸のあたりで小さく手を振り白い歯を見せた。
僕は一息つきたくて、一柳に声をかけてから席を立った。おバカな寸劇に興じているとき電話の着信があったのも気になっていた。
店の外で電話をしていると、隣席にいた二人連れの女性が店から出てきた。何を言っているのか聞き取れなかったが、一人は怖い顔をして何やら喚き散らしている。もう一人は同調しながら相手をなだめている様子だった。気づかれないように、咄嗟に僕は体を翻し背中を向けた。
店内に戻ると、入り口横のレジカウンターに笑顔の茂森さんがいた。たった今、恐ろしい女性たちを目撃したばかりの僕は、ことのほか茂森さんが天使に見えて、目が合ってドキッとした。僕が外に出たのを彼女は知っていて、戻ってくるのをここで待っていた。そんな表情が読み取れた。
笑顔の交換を済ませると「あの、お差し支えがなければ」と茂森さんは言った。「語り人さんのご連絡先を頂戴できないでしょうか」。
「あっ、名刺はカバンの中に…」そう言って席に戻ろうとする僕を、茂森さんは首を振って引きとめた。そして準備していたらしく「ここに書いてください」と、ペンと白紙の名刺カードを卓上に置いた。
背後に人がいないことを確認し、僕は手早く名前(本名)と電話番号とメールアドレス、それから少し考えて仕事場の住所を書いて手渡した。
すると茂森さんは(これもついさっき準備したのだろう)同じ名刺カードを、「すみません。あの、わたしも手書きです」と言って恥ずかしそうに両手で差し出した。名前は端正な字体で「茂森愛由美」と書かれていた。
(何か話さなければ…。名前だ。愛らしい名前だと言ってあげよう。いや、だから何なんだ。そうだ、さっき店長から聞いたことを話題にしよう。ダメだ、これはデリケートな問題だ)
けっきょく僕は茂森さんに何も言えなかった。言葉はいらないというロマンティックな判断からじゃない。なぜか言葉が出なかったのだ。(まさか、おれはこの子のまえで緊張しているのか?)
僕は自分が「カチカチ山の愚鈍な中年男」になったような気がしてうろたえた。そうだ。年甲斐もなく、この状況に胸が躍らなかったといえば嘘になる。もっと言おうか。
好きな女の子に嫌われることだけが怖かった、あの恋という熱病にかかっていた10代に戻りたいと思わなかったといえば嘘になる。
「おれは何だってできる」と右手に剣を左手に花束を持って理想を説く、あの鼻持ちならない20代に戻りたいと思わなかったといえば嘘になる。
安っぽい愛を絶叫する流行り歌を蔑みながらそれでも激しく愛を求めた、あの喪失感だらけの30代に戻りたいと思わなかったといえば嘘になる。
そして今。「もう若くないさ」と言い訳をして、そのくせ天使の微笑を待ち焦がれる、そんな矛盾だらけの自分が嫌いだといえば嘘になる。
ああ、こんな愚にもつかない青臭い感傷は犬にでも食われてしまえばいい。
彼女が僕の連絡先をほしがったのには理由がある。それは…。
それより今は一柳だ。急いで席に戻ると、一柳は虚ろな顔をしてスマホを睨んでいた(ほとんどの人がスマホを見ているときは虚ろな表情をしているが)。
「一柳、隣の女性たちと何があった」勢い込んでそう訊くと、
「ていうか、どうしたんすか」と一柳はわかりやすくとぼけてみせた。
「いいから話せ!」少し声を荒げると、一柳はいかにも作り笑いとわかる笑い声をあげて言った。「だってさっき、長老さまに誓ったじゃないすか」
「一匹のメスダヌキを、いや、一人の女性を生涯、愛しつづけますと」
「そうっす」
「寄ってくる不特定多数の女性を悦ばせるのは卒業したというわけか」
「そうっす」
「なるほど」
一柳は詳しく話したがらなかったが想像はついた。やつは本当に彼女たちを袖にしたようだ。僕が席を外したタイミングで、彼女たちは一柳に声をかけた。それを一柳は、とにかく冷たくあしらった。ひと言で彼女たちを撃沈させる一撃必殺の言葉で。
僕は想像してみた。
「いやあ、オレの奥さん、怖いんだよ。浮気したら殺すなんて言うんだ。相手の女をね」
いや、違うな。店の外で見たあの様子からすると、彼女たちのプライドをズタズタにするナイフのようなひと言かもしれない。僕はこれ以上想像したくなかった。
かわいそうに。二人ともそこそこ洗練されたイイ女だった。いつもは言い寄ってくるギラギラした男たちを冷たくあしらう側だろう。それが今夜は、よもや自分たちがギラギラした女になっていようとは思ってもみなかったに違いない。
しかしその洗練さや美しさは、彼女たちが涙ぐましいまでの執念をもって、最新の流行やトレンドで装備した、いわば物理的成果に他ならなかった。つまり、少なからぬお金と労力を投入してやっと手に入れた類の洗練さであり美しさであり、それゆえメッキのように剥がれやすかった。
目的は「イケメンのお金持ちとの誰もが羨むセレブ婚」かもしれないし、「異性からも同性からもナメられないための武装」かもしれないし、あるいは単なる「自己満足」かもしれない。いずれにせよ、彼女たちも戦っているのだ。彼女たちの戦い方で。もちろん、幸せになるために。
でも今日は相手が悪かった。相手は一柳だ。しかも、不特定多数の女を悦ばせることをやめたばかりの、改心した一柳だ。それとも一柳にしてみれば、ただ相手を選んだだけなのかもしれない。店の外で喚き散らしていた彼女たちの本性を、一柳は見抜いたのかもしれない。あれは修羅場を引き起こすタイプの女たちだと。
「"据え膳食わぬは男の恥"を盲信していた今までの自分が恥かしいっすよ」そう言って一柳は力なく笑った。
このとき僕は確信を持った。勘違いなんかじゃない。
「おまえ、誰かに惚れたな。ひとりの、特定の女に」
そう言ってから気づいた。だとすれば僕の知るかぎり、
これは一柳の正真正銘、掛け値なしの「初めての恋」。
でも、だったらなぜそんなにも愁いに打ち沈んでいる?
いや、恋とはもともとそんなもの。しかも一柳の場合…
「愚鈍な中年男の"惚れたが悪いか"ってやつですよ」
そう言って一柳はこれが実質上の初恋であることを認めた。
「すごいじゃないか! そうか、とうとうおまえも年貢を納めるか。これで長老さまも文句はないだろう。げんこつ山に戻れるぞ。とにかく、これはめでたい!」と僕は興奮して言った。
「河岸を変えて飲みなおそう。うん、シャンパンがいい。まずはシャンパンで乾杯だ。この稀代のモテ男の心を射止めたのは、いったいどこのどんな女だ? じっくり聞こうじゃないか」
「語り人さん、その話はまたにしてもらっていいすか」
僕の興奮をよそに一柳は浮かない顔をして言った。
「まだ話せる段階じゃないんすよ」
「まさか…」これはよくあるひとつの可能性を示唆している。
「まさかおまえ、道ならぬ恋じゃないだろうな」
僕の心配を一柳は一笑に付した。
「それはないっす。それは杞憂っす。人妻の浮気相手にだけはなるな。これも語り人さんの教えでしょ」いや、教えではないが持論ではある。
ともかく一柳は、今日は勘弁してくれの一点張りで、どうやらこれ以上口を割るつもりはないようだった。そうして僕たちは、別の店に繰り出すでもなく、シャンパンでお祝いをするでもなく、まあ僕としてはいまひとつ釈然としない気分で別れたわけだ。
ただこのことで、一柳を責めることはできない。僕は僕で「茂森愛由美」と密かに連絡先の交換をしたことを、なぜか一柳に言えなかった。
昔は秘密なんて何ひとつなかった。どんなことも包み隠さず言い合えた。
良いことも悪いことも。嬉しいことも悲しいことも。誇らしいことも悔しいことも。自慢したいことも恥ずかしいことも。大事なことも些細なことも全部。なんだって僕たちは共有してきた。ケンカだっていっぱいした。そのたびに絆は強くなった(と信じていた。今も…)。
でも今は、言えないこと話せないことがある。言いたくないこと話したくないこともある。関わったり関わられたりがいやなことだってある。そんなふうに一柳も僕も、そっと胸に収めてしまうことが年々増えてきた気がする。それは僕たちが年を取ったからなのか。きっとそうなのだろう。
ひとまずここで、一柳と会った半年前の記憶の映像ファイルを閉じることにする。長々と振り返ってみたが、女絶ち発言も金持ち宣言も、けっきょく真相はわからずじまいだった。
しかしもちろん、一柳の女絶ち発言も金持ち宣言も、
ヒントは半年前のこのエピソードの中に潜んでいる。
そして僕の方はと言えば、この焼鳥屋での出来事の数日後、僕がなかば期待もし、なかば恐れてもいたことが現実のものとなった。
茂森愛由美から手紙が届いたのだ。メールではなく、郵便で届けられた封書の手紙。彼女らしい端正な字体で綴られた、美しい日本語の手紙。
それから僕と茂森愛由美は、半年後の今も、毎週のように顔を合わせている。
それを一柳は知らない。
(次章につづく)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 多くの人にもっとも欠けている才能、それは決してあきらめないという才能だ。
- ただし目標設定に期限を設けることは必要だ。期限内に達成できなかったときは、未練を捨てすぐに方向転換する潔さを持つこと。それを「あきらめ」とは呼ばない。
- どんな人の中にも、ときとして悪意が宿ることがある。本人も気づかないうちに。人の悪意に取り込まれないよう自衛手段を取ることも大事だが、自分の中に潜む悪意にも注意を払おう。自分で自分を守るとはそういうことだ。
- 周囲の反対を押し切ってでも、あなたにはやりたいこと、かなえたい夢がある。そんなときまず考えるべきは、なぜ周囲は反対するのかという客観的な理由だ。
- 人生は選択の連続だ。現在の自分は過去にした選択によって組成されているといっていい。何を選び、何を選ばなかったか。ときどき過去を振り返り検証してみよう。よりよい未来の選択のために過去を振り返るのは有効だ。
- 自分を磨くことについて。すぐに化けの皮が剥がれるようではお里が知れるというもの。磨くべきは礼儀と感情のコントロールだ。