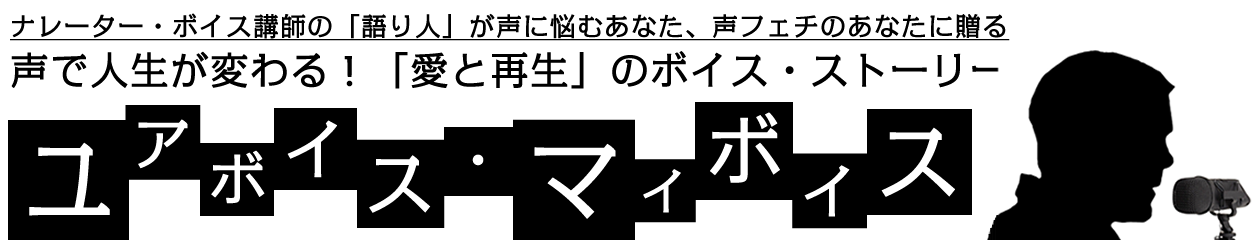「そんなに悲しいのは、本気で愛したからでしょ?」
「それ、どういう意味? 僕に言ってるの?」
「ほかに誰がいる。だいたい、きみが僕を呼んだんだよ」
「なに? 呼んだ覚えはないけど」
「じゃあ、きみが僕を求めた、と言い換えようか」
そう言うと男は、その無邪気な笑顔に真っ白な歯を添えた。
それがジョージとの最初の出会いだった。
(1章「米兵ジョージ」のつづき)
最初に言ったように、僕のウォーキングコースはこの公園だけじゃない。ここに来るのは週2~3回。曜日も時間もばらばら。ジョージが門衛につくローテーションも知らない。でもなぜかいつもジョージの姿はそこにあった。
彼の名前を知ったのは2回目に会ったときだった。
「日本人みたいだろう」と言って白い歯を見せた。
「ジョージ・ワシントン」と僕は言ってみた。
「ああ、尊敬している。親父がね」
「君は違うの?」
「わからない。時代が違うしね」
ジョージの表情が一瞬、曇った。
「ところで、聞かせてくれるかな」
最初に彼が放った言葉の真意を知りたかった。
そんなに悲しいのは、本気で愛したからでしょ?
彼が看破したとおり、そのときの僕は生涯守り抜くはずだった人との別れを経験したばかりで、我と我が身を責め苛んでいた。
「きみにニコラス・ケイジの言葉を贈るよ。『僕は本気で愛して失恋したい。欲しいのはその経験だ』」そういうとジョージはにっこり笑った。
「それは役者の言葉だろう」僕は少し投げやりな口調で言った。
「きみは違うの?」ジョージは首を傾げた。
「……」
「役者だけじゃない。表現者の宿命だ。魂は経験によってのみ磨かれるんだ。好むと好まざるとにかかわらずね。きみはいつだってあまり賢明とはいえない、あまり効率的とはいえない経験を好んで求めた。違う?」
ちがうちがう、そうじゃない。
ちがうちがう、…ちがわない。
たしかに僕にはその傾向が強くある。
「僕が君を求めたって、どういうこと?」
「そのうちわかるよ。ところで、まだ名前を聞いてなかったと思うけど」
「失礼」と言って、僕はファーストネームを名乗った。
「わお、グレイト! 君は日本一の人なのか!」
「名前だけだ。だから語り人と呼んでくれ」と僕は言った。
それから僕たちは、自分の名前にまつわる悲喜こもごもの歴史、簡単にいうと名前で得したこと・損したことなどを面白おかしく披露し合った。
ジョージの英語は西海岸で話される標準的な米語で、正確で訛りもない。とはいえ相当な早口で、脳が言葉の意味を咀嚼するのに少なからず時間を要した。まともに英語を話さなくなってから四半世紀になる。だから噛んで含めるように話してくれと頼んだ。
「君の英語は若々しくて美しいよ。東海岸だね。学園都市。そう、ボストンの香りがする」とジョージはゆっくり刻むように言った。「でも君は、アメリカには行ったことがない、だろう?」
たしかに僕はアメリカに行ったことがない。これまで幾度となく渡米の機会は巡ってきたが、なぜかいつもすんでのところで邪魔が入り計画は頓挫した。
でも、なぜわかる?
「でも、ボストンから来た女の子と付き合ったことがある、違う?」
もうわかったよ。そうだ。大学生のとき僕の通う大学に、ボストンの大学から交換留学生としてやってきた女の子がいた。彼女のお世話係を任されたのが事の始まりだった。
僕たちはたちまち惹かれ合った。
彼女の屈託のない笑顔と、その笑顔を裏切る愁いを帯びたベルベットボイスに、僕は一発でやられてしまった。利発というより聡明で、活発というより思慮深い彼女に夢中になった。
ポップなリズムでまくしたてる鼻にかかったべちゃっとした米語ではなく、どちらかといえばBBC英語に近いがそれでいてスノッブさを感じさせない、クラシカルで気品のある英語を話す彼女に恋をした。
そして彼女は、僕の黒い瞳と黒い髪が好きだと、ギターを弾くその指と、優しくて深い声、本を読んでいるときの横顔が好きだと言った。
そのくせいつも「本と私、どっちが好きなの!」と駄々をこねては僕の手から本をひったくり、そうして僕が教えた日本語「書を捨てよ、町へ出よう」をしつこく何度も復唱し、いやがる僕を外へ引っ張り出した。
僕たちは文字どおり恋に落ちた。魂の物理法則に従って。
一年という留学期間は、恋という熱病に侵された二人にはあまりに短すぎた。僕たちは、どちらかがどちらかの国に住むという選択肢を真剣に話し合った。日本かアメリカか…。離れたくない思いは一緒だったはずだ。
「やっぱりあなたが交換留学生としてボストンにきて! そうすれば少なくともあと一年は一緒にいられるわ」
少なくともあと一年?
彼女は”long time”でも”forever”でもなく”at least one more year ” と言った。彼女のこの言葉に、19歳の僕は勝手に傷ついたことを覚えている。
結果的に僕は交換留学生の資格を得ることは出来なかったし、彼女も期間を超えて日本に留まることは許されなかった。アメリカは、僕にとってこんなにも近いのに、こんなにも遠かった。
「うん、そのときも辛い別れだったよね。僕たちは選べないんだよ。恋の始まりも、終わりもね」と、ジョージはまるで「両手の指は10本だよね」みたいな、それが当然であるような言い方をした。
「しかたないさ。二人はまだティーンエイジャーだったし、おとなが決めたことに従うしかなかったんだから」
もう三十年も前のことなのに、僕の中の忘れていた感情が、舌が酸味の刺激を敏感に捉えるように甦ってきた。 それを追い払おうと、僕は激しく頭を振った。
それにしても、この黒人にしては華奢な体型のハンサムな男は、いったい何者なのだ。僕の過去や現在が視えるとでもいうのか。「たしかに視えている」としかいいようのない事態に、僕はひどくうろたえた。
(3章につづく)