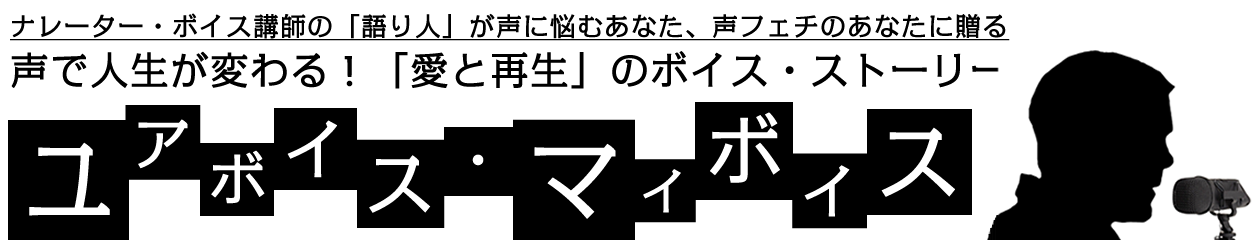自分の仕事ができること以上に大事なことなんてこの世にありはしない。
だから、返事は決まっている。「もちろん、やります」。
そう応えて僕は、孤独なナレーションブースに潜り込んだ。
深い海底にたった一人で潜る潜水夫みたいに。
(2章「身体の中心で愛を叫ぶ」のつづき)
オーディオブック『脳内沖縄紀行』後編は、世界遺産としての沖縄のグスク(首里城を代表とする城跡)から、琉球王国の歴史をひもとく語りで幕を開けた。
「ここは重厚にね。だけど重苦しいのはダメよ。淡々と流して。でも言うまでもないけど、立てるところは立ててよ」
ヘッドホンからシーサーさんのガラガラ声が飛び込んでくる。
「立てますとも! それが男っしょ!」
いつもの流れでそう返そうとしたが、今日はそれどころじゃない。しかも、シーサーさんはいざ収録が始まると人が変わることを、集中力のギアが数段上がることを、僕は知っている。ふだんは全開の下ネタもジョークも、このときばかりは通じないのだ。オネエ言葉だけは変わらないのだけれど。
「そう、いいわよ。その調子。次は琉球王国を支配したふたりの男の物語。説明するわよ、よく聞いて。ふたりは奄美との交易の主導権をめぐって争ったライバル同士なの。(中略)…わかったわね。男の美学をしっかり表現するのよ。セリフはふたりのキャラを際立たせる声を使い分けてちょうだい」
シーサーさんの演出を挟みながら、僕は無我夢中で読み進めていく。
彼の指示は的確だった。 いや、指示というより啓示だ。その声は天の啓示のごとく、表現の深い海の底にいる僕を覚醒させコントロールした。
「さあ次は、沖縄の食と酒の歴史よ。権力欲・征服欲のあとは食欲を満たしてあげましょ。ガラリと変わるわよ。ちょっとやってみて。そう、いいわね!」
「はい、そして沖縄といえば”ソーキそば”。擬音もちょうだい。おいしそうに啜ってみて。そう、そしてセリフよ」
「アンタも食べるといいサー」
「いいわ。完璧なアクセントよ」
「そして琉球泡盛、30年ものの古酒(クースー)、呑みたいわね!
飲む前のワクワク感、飲んだ後の幸福感をきちっと押さえてね」
言われたとおり、僕は酒好きのおじさんになりきった。
「ノッテきたわね、語り人ちゃん。ほんとうに酔っぱらってるみたいだわ」
そうだ、僕はノッテきた。「やべー、キモチいい!」という陶酔状態。と同時に意識は明晰で心は落ち着いている。「冷静と情熱のあいだ」というより、両者がなんの矛盾もなく共存している状態。
収録が始まって3時間。だいたいいつもこのくらいの時間。待ちに待った瞬間を迎える。ランナーズハイだ。ご存知のかたも多いと思うが、ここで少し説明しておこう。
ランナーズハイ(runner’s high)とは、長時間のランニングなどのさいに経験される陶酔状態のこと。走っている最中に苦しさがいつしか高揚感に変わり「空を飛んでいる」ような快楽現象が起こる。
その正体は脳内麻薬といわれるβエンドルフィンの存在だ。この快感物質、βエンドルフィンには麻酔作用があって、覚醒効果や鎮痛効果があると報告さられている。
マラソンなどで身体が苦痛やストレスを感じると、脳は自らβエンドルフィンを作り出し、苦痛やストレスを和らげようとする。それが快楽現象を生んでいるというのだ。この現象を僕は、自分に当てはめてナレーターズハイと呼んでいる。
通常オーディオブックは一冊の書籍を丸ごと音声化する。たとえば三百ページの本なら、だいたい7時間ほどの音声データになる。収録時間でいうと(読み手によって差異はあるが)その2倍から3倍の時間を要する。これを2~3日で収録するのだから、どれほどの長丁場かわかるだろう。
15秒のテレビCMはもちろん、1時間ものの番組でも経験することのできないランナーズハイ(ナレーターズハイ)を、このオーディオブックで体感することができるのだ。声の長距離アスリート。僕は自分をそう呼んではばからない。
「聞いてるの? 語り人ちゃん」おっと、シーサーさんが呼んでいる。
「さあ次よ。景色を変えてちょうだい。頭の中で映像を切り替えるのよ。はい、ナレーションから、スタート!」
(ここはコザの街、アメリカの田舎町といった風情だ。そこかしこで英語が飛び交っている。とあるレコードショップ。ウインドウから見える古いジャズの名盤に誘われて、貧しいミュージシャン風の若い男が入ってきた)。
映像を思い浮かべながら、というより現場を俯瞰している目になって、僕は読み進めていった。
「店番はでっぷり太った黒人女性よ。いい? イメージして。若者が盗みを働きはしないかと睨みをきかせているわ。はい、黒人女性のセリフ!」
(Do you have any ID cards?)
「すごいわ、語り人ちゃん。本物みたい!」
「さあ、いよいよエンディングよ。…あら、どうしたの? 声に張りがなくなってきたわよ! それに、滑舌も少しあまくなってるわ」
シーサーさんの耳はだませない。もちろん、自分がいちばんわかっている。
海に潜っておよそ6時間が経過していた。僕の息は、僕の声は、いや息でも声でもない、お腹だ。僕のお腹は限界を超えていた。
声と呼吸を支えるお腹が、疲労と空腹で機能不全に陥っている。そのため腹式が利かなくなり、必要以上に声帯に負荷をかけていた。声の張りつやがなくなってきたのはそれが原因だろう。
さらに、集中力を使いすぎたことによる脳の酸素不足が滑舌をあまくしていた。βエンドルフィンはすでに使い果たしている。いま一度再生するためには食事と休憩が必要だ。
気が遠くなってきた。頭が真っ白だ。景色が描けない…。
そこへシーサーさんの金切り声が飛び込んできた。
「だめ! まだよ、語り人ちゃん。まだイッちゃだめ! 男なら、我慢するの! いっしょにイクのよ!」
シーサーさんは、萎えかけている僕をふたたび奮い立たせようと、収録中は絶対口にしないはずの下ネタを解禁して叫んだ。
(ああ、シーサーさん! 僕のために、ごめんなさい。そしてありがとう)
僕は目を閉じ、脳にひとつの映像を呼び起こした。
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん
そこはサーカス小屋。
天井から吊るされた空中ブランコが
大きく揺れている。
ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん
中原中也の詩「サーカス」に出てくる、これはブランコの擬音だ。
この音を繰り返し唱えると心が静謐になり、空を飛んでいるような高揚感が全身を包む。本来、一定の条件下で無意識に分泌されるβエンドルフィンを意識的に、あるいは作為的に作り出そうという、これはある意味で危険な荒療治だった。
次に意識を丹田(第3のチャクラ)から心臓(第4のチャクラ)、そして喉(第5のチャクラ)、さらに眉間(第6のチャクラ)へと巡回させた。これは生命エネルギーを全身に隈なく満たすための、僕が限界を超えなければならないときに自分に施す応急蘇生法だ。
まあ、どちらも「それって、おまじないみたいなものだよね」と言われればそれまでなんだけど。なんでもいい。どうか、僕に最後の力を!
そのとき、傷だらけで息も絶え絶えの孫悟空が両手を天にかざし、みんなから少しずつ分けてもらったパワーで、でっかい元気玉を作るシーンが浮かんだ。
「少しでいい。おらに力を分けてくれ!」と悟空は言った。
スーパーサイヤ人の孫悟空でさえ、自分の力だけではどうしようもないときがあることを知っていた。
「はーい、オールOKよ!」シーサーさんの声が終幕を告げた。
どうやってエンディングを迎えたのか、よく覚えていない。
こうしてすべての収録を終えた。
海底から地上に戻り、僕は大きく息を吐いた。
(次回「最終章」につづく)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 声優は腹で戦う。だから「腹が減っては戦(いくさ)はできない」。
- 複数のキャラを演じるときは無理に声を変えよう、あるいは作ろうとしてはいけない。対象となる人格を瞬時にイメージし、それを丸ごとわが身に引き受ける。「乗り移っちゃう感覚」といえばいいだろうか。
- ランナーズハイ、長い「ひとり語り」はこれがあるから快感だ。
- ランナーズハイは身体に相当の負担がかかることを忘れてはいけない。フィジカル・メンタル両面の強化が不可欠だ。
- ダジャレと下ネタは脳の活性剤だ。
- 限界を感じたとき、それでもそこを超えなければならないとき、蘇生するためのおまじないを持っているといい。僕は本文で紹介した中原中也の詩「サーカス」に登場するブランコの擬音(ゆあーん ゆよーん ゆあゆよん)を繰り返し唱えることにしている。おまじないを侮ってはいけない。それにしても中也の擬音のセンスは秀逸だ。
- 『ドラゴンボール』が名作であるゆえん。それは、死んだ人を生き返らせることができるドラゴンボールによってではない。人間を含めた生きとし生けるものの「地球への愛」が集結した元気玉によってである。