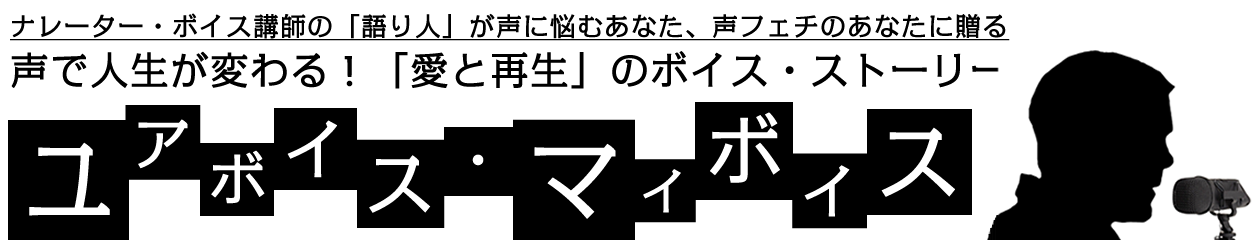20年ぶりに再会するその人は、間違いなく45歳になっているはずだった。なのに、僕は幻覚を見ているのか。その容姿も体型も、髪形も服装も、眩いばかりの精神の溌剌さも、もう何から何まで、僕の記憶に鮮明に焼き付いている、20年前の彼女そのままなのだ。
「語り人さん!」昔のままの澄んだ声で彼女は僕を呼んだ。
タイムスリップした人のように僕はうろたえた。
(過去からの贈り物(中)のつづき)
と、ここまで書いて僕は筆を止める。
まずい。このまま書き進めていけば、またしても長大な物語になる。
そもそも本稿はエッセイだったはず。しかし、エピソードの端緒を僕はすでに書いてしまった。ディテール描写はなるべく控えるので、どうかこのままお付き合い願いたい。
というわけで、いきなり出てきた謎の女性「奈都子」とは何者なのか。その話をするにはここでもう一人、このエピソードに欠かせない重要人物に登場してもらわねばならない。
僕と同期入社で同い年のその男は、最年少で役員に就任し、今や次期社長と目される大物だ。名前を岡本としておく。岡本とはおよそ10年ぶり、いや酒を酌み交わすのは25年ぶりだった。
僕たちは昔よく一緒に飲んだ銀座のバー「ルパン」にいた。
アルセーヌ・ルパンの名前に由来したこの店は、昭和三年から続く老舗の文壇バーで、川端康成、永井荷風、泉鏡花、菊池寛など錚々たる作家たちの溜まり場だった。太宰治や坂口安吾も常連だったことで知られている。
場所柄もあってか、当時から新聞社の人間や、丸の内の三菱系の会社員も多く出入りしていた。
ビアジョッキ2杯を空けて、それから岡本は山崎12年のオンザロック、僕はドライマティーニでふたたび乾杯した。それが合図だったみたいに岡本は急にあらたまった態度で言った
「語り人、あのときはすまなかった。おまえの味方をしてやれなかった。おまえはいつだっておれをかばってくれたのに」
彼がいつの何の話をしているのかすぐにわかったが「いったい何の話だ?」と僕はとぼけてみせた。岡本はそのときの出来事を苦渋の表情でぽつぽつ語り、最後にもう一度、僕に謝罪した。しかし岡本は全部を話していない。核心的な部分を巧妙にぼかしていた。
「昔のことだ。おれが覚えてるのは、おまえは人気者で、おれは嫌われ者だったということだけだ。人気者には人気者の仕事があり、嫌われ者には嫌われ者の仕事がある。おれたちは結構、いいコンビだったよな」
僕がそう言って笑うと、岡本は目を潤ませて何度も頷いたあと、ふっと表情を緩めて言った。「変わってないな、語り人は。そんなおまえに、おれはずっと嫉妬していたんだ」
「嫉妬だって? 冗談じゃない!」僕は呆れたように返した。岡本は同期で一番の出世頭で、若手の花形社員だった。同期の男子社員みんなが多かれ少なかれ彼に嫉妬していたのだ。
「おまえは嫉妬なんかしないだろ?」
僕の目を覗き込むようにして岡本は言った。
「いかにも。それが嫌われ者の流儀でござる」
僕がおどけてそう言うと、岡本はからだを揺すって大声で笑った。
途中から僕は気づいていたが、彼もまた過去の後悔を引きずっていた。そして禊(みそぎ)のために、今の自分を書き直すために僕に会いに来たのだ。ならば、僕も腹をくくろう。今こそ岡本と僕がそれぞれに隠し持ってきたパンドラの箱を開けるべきときだった。
「おれにもある。おまえに謝らなければならないことが」
声のトーンを変えて僕が言うと、岡本は「きたか」という顔をした。そのくせ表情とは裏腹な言葉を口にした。「そんなもん、おまえにはないだろう」
「飯倉奈都子。覚えてるか?」
「忘れるはずがない。おれたちのアイドルだった」
僕の問いかけに岡本は即答した。
その当時、僕たちの部署に編集アシスタントの女子大生がいた。今でいうインターンシップ生だ。大学三年生の彼女は、卒業後この会社への就職を志望していた。
「いい子だったよな。美人で頭が良くて、そのうえ素直で気立てが良くて。ミステリアスな雰囲気も魅力だった。おまえの意見は?」
岡本は飯倉奈都子の熱烈な讃美者だった。
「声がきれいで、話すときと食べるときの口元もきれいだった」
僕が答えると、岡本は大きく頷いて言った。「パーフェクトな女だった」
岡本だけじゃない。若手男子社員のほぼ全員が、彼女の気を引こうとやっきになっていた。
そんなあるとき、岡本のかけ声のもと「飯倉奈都子の純潔を守る会」という、なんとも馬鹿げた会が発足した。
いわく、飯倉奈都子に個人的感情を抱いてはならない。いわく、飯倉奈都子を個人的に食事および飲みに誘ってはならない。他にも10項目くらいあったと思うが、結びの言葉はこうだった。飯倉奈都子に手を出すやつはこの岡本が許さない。
「あの子は内定を控えたうちのアイドルだ。我が社にきれいなかたちで入社できるよう、みんなで大切に守って応援してあげようじゃないか!」
岡本がなぜ急にこんなことを言い出したのか、僕は知っている。岡本はひた隠しにしていたが、真っ先に飯倉奈都子に個人的感情を告白したのは他ならぬ彼だった。その事実を僕は飯倉奈都子本人から聞いていた。
彼女は岡本からの交際の申し出を、遺恨が残らないよう上手に断った。卒業してこの会社に入社するまでは誰とも恋愛するつもりはない。だからお願いだ。そのときまで静かに見守っていてほしいと。
自信家の岡本は、これを拒絶とは取らなかった。むしろ控えめな肯定と捉え、ますます熱を上げた。飯倉奈都子にふさわしい男は自分しかいない。だからそのときまでは誰にも、断じて、指一本触れさせない。あの子をものにするのは自分なのだ。
「飯倉奈都子がどうした?」岡本はロックグラスを揺らしながら眉間に皺を寄せて険しい顏をした。このとき僕は確信した。この男は知っている。やはり岡本は、飯倉奈都子と僕の関係を知っていたのだ。
「その後おまえが海外に赴任してまもなく、彼女は突然うちを辞めた。せっかく手にした内定も返上した。それは…」ここで岡本は言葉を止めた。絶妙な「間」だと感心している自分が可笑しかった。
「それは、おれのせいだと思っていた。はじめはな。いや、やっぱりおれのせいだろう」ひねりを入れた巧妙な言い方に、僕はまたしても感心してしまった。しかし感心ばかりしている場合じゃない。岡本は僕に自白させようとしている。だからここへ呼び出したのだ。
「そうだよ。おれは抜け駆けをした」僕はすんなり自白した。
「それはおれの抜け駆けの前かあとか、つまり、おれが飯倉奈都子の純潔を守る会をつくった前かあとか、どっちだ?」岡本も自分が抜け駆けしていたことを自白した。
「あとだ」と僕は正直に答えた。
「そうか、あとか…」岡本は拍子抜けしたような顔をした。
「だからおれは裁かれて島流しの刑に処された」ひと息で僕は言った。
「どっちにしろおれはフラれて、おまえは受け入れられた。彼女は…」岡本はまた間を取った。
「嫌われ者の支持者だった」と僕は引き取った。
「彼女に何をしたんだ?」と岡本は訊いた。
「彼女が好きだと言ったチェーホフの話で盛り上がった。『かもめ』のトリゴーリンの台詞をおれが口ずさむと、彼女はニーナの台詞で返してきた。それがきっかけだ」
「どんな台詞だ? いや、待て。やらんでいい。もうわかった。とにかくおまえは自分の得意分野に持ち込んで、得意技を使って彼女を口説き落とした」
「おれが持ち込んだわけじゃない。口説き落としてもいない」
「自然に惹かれ合ったと言いたいのか。おれと違って」岡本は鼻で笑った。
「おれが邪魔だったみたいだな」僕はそう言ってみた。
「そのときは嫉妬に狂ってた。だから…」岡本はまた間を取ろうとする。
「だからおれが海外に飛ばされるよう画策した」間を取らせないよう僕が引き取った。
「知ってたのか? 最初から」岡本は悲壮な表情を見せた。
「いや、いま知った」僕は嘘をついた。「こう見えておれは鈍感なんだ」
「飯倉奈都子を取られたくなかった。おまえにだけは」岡本は絞り出すように言った。
「取ったとか取られたとか嫉妬に狂ったとか、反吐が出るほど陳腐な台詞だな。とにかく、おれが日本を離れてるあいだ、おまえは奈都子を…」
「……」岡本も黙った。間を取ったわけではないようだった。
「同じ質問をする。彼女に何をした?」僕は少し凄んで言った。
「そうだよ。おれは陳腐な卑怯者だ!」追い込まれた人がそうするように岡本は開き直った。
「そんな言葉じゃ足りないな」
「ああ、おれは友情を踏みにじった下劣な男だ」
「安い友情を語るな。おまえが踏みにじったのは飯倉奈都子の青春だ」
「結果、おれは永遠に彼女を失った」
「相変わらず自分のことばかりだな、おまえは。まあ、出世は勝ち取ったじゃないか。社長就任を目前にして、今さら青春の過ちを懺悔ってか? 虫のいい話だな」
「語り人、おれは何をすればいい? 教えてくれ」
「自分で考えろ。今やおまえは大企業の頂点に立つ男だろ」
「おまえが帰国後、会社を辞めたのはおれのせいだ。飯倉奈都子と別れる原因をつくったのも、きっとおれだろう。その後いろいろあったことは聞いて知ってる。おまえらしく生きてるようだが、おれに出来ることがあったら言ってくれ」
「そうか。じゃあ頼みがある」思い切って僕は言ってみた。
「おまえはうちのOBだ。グループ会社の重役のポストくらいならすぐ空けられるぞ。社長がいいならちょっと調整が必要だが、まあ何とかなる」
「バカか、おまえは。おれは今のナレーター稼業を愛してるんだ」
「たいして稼げないだろう。年収はいくらだ?」
「余計なお世話だ。生活に困らない程度に仕事はある」
「もっと欲を出せ、語り人。じゃあ今後は声案件でサポートさせてもらう。で、頼みって何だ?」
さあここからだ。身体の重心を丹田に落として僕は言った。
「おれを大阪に行かせてくれ」
「大阪? ああ、おまえのエッセイは読んだ。それが頼みごとか? わかった。大阪の仕事をつくればいいんだな? すぐに大阪本社に連絡を取って何かみつくろわせよう」
さすが岡本だ。話が早い。えっ、エッセイを読んだ?
(ボイスエッセイ「大阪へゆきたし」参照)
「大阪本社はまずいんじゃないか。東京本社とは昔から良好な関係とはいえないだろう」心配して僕は言った。
「だいじょうぶだ。同期の森田が、いま大阪の広告局長をやってる」
「えっ、あの森田が? なんで大阪へ行かされたんだ。しかも広告だって?」
「それはまた詳しく説明する。森田はおまえに懐いてたからな。喜ぶぞ!」
「岡本、おまえも一緒に来い」
「おれも大阪にか? なんでだ」
「おれたちの青春を書き直すんだ」
「大阪で青春を書き直す? どういう意味だ」
「この流れだ。少しは想像してみろ」
「まさか、飯倉奈都子が大阪にいるって話か?」
「ああ、あのときのままの飯倉奈都子がな」
(「過去からの贈り物(完)」につづく)