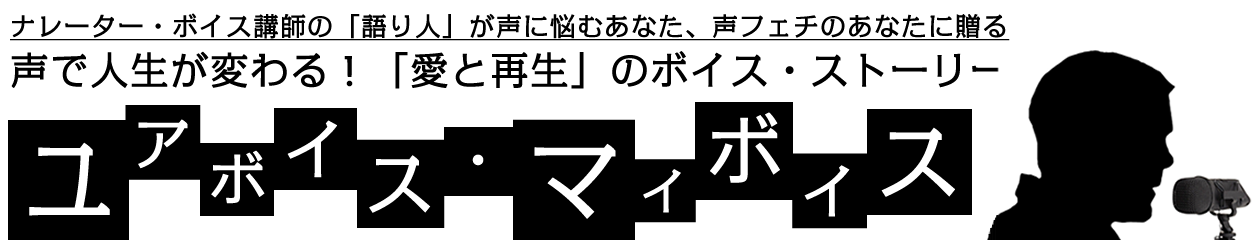根岸森林公園──
ここでは観光ガイドしての僕の出番はない。ただひたすら歩くのみ。
しかし、ここにも語るべき物語はある。今回はここで起きた不思議な話をしよう。もっとはっきり言えば、これは語り人に起こった奇跡の物語だ。
(序章「ヨコハマウォーク」のつづき)
ここ根岸森林公園は敷地内に米軍の基地がある。
ジョギングコースに入るとき、基地のゲート前を通過する。ゲートには迷彩服姿の米兵が交代で門番を務めている。長年この門前を通っているので、ほとんどの米兵が顔見知りだ。
そのなかに、ジョージという名の新入りの男がいた。カリフォルニア州サンディエゴからきたハンサムな黒人。
彼にはおそろしい能力がある。おそろしいといって悪ければ「驚嘆すべき」と言い換えてもいい。
ジョージと初めて会ったのは去年の初秋だった。ときおり夏が未練がましく舞い戻ってきたりする季節で、僕は帽子を目深に被り、いつものようにゲート前を通り過ぎようとしていた。
「かっこいいキャップだね。とてもよく似合ってる」
聞きなれない声だと思って一瞥すると、はたして新入りの米兵だった。
繰り返すが、僕のウォーキングスピードは速い。どのくらい速いかというと、競歩の選手にはむろん敵わないにしても、たとえばダイエットのために決死の形相で走っているポッチャリ女性を軽くスルーしてしまう、つまりそのくらいの速さ。
とにかく僕が言いたいのは、ここにきているのはジョギングやウォーキングが目的じゃないってこと。健康やダイエットのために歩いているわけじゃないんだ。
だから、ジョギングスーツやランニングパンツなんか着用しないよ。だって、いかにもって感じでカッコわるいじゃないか。
なんていうか、集中するために歩いてる。孤独と向き合うために歩いてる。考えるために歩いてる。考えないために歩いてる。うまく言えないけど、そんな感じ。
だから新人門番の呼びかけにも立ち止まることなく「サンキュー、きみの帽子もなかなかだよ」と言って通り過ぎた。
3キロのコースを例のスピードで一周して再びゲート前にくると、その男がいた。ずっと待ち構えていたように僕のことを見ている。いやな予感。
彼とおしゃべりをする気もなかったのでキャップをさらに目深に被り、そのまま通り過ぎようとした。男の響きのあるバリトンが僕を捉えた。
「そんなに悲しいのは、本気で愛したからでしょ?」
思わず足を止めて男を見た。とても無邪気な笑顔。その表情から悪意は読み取れない。真意を確かめたくて訊いてみた。
「それ、どういう意味? 僕に言ってるの?」
「ほかに誰がいる。だいたい、きみが僕を呼んだんだよ」
「なに? 呼んだ覚えはないけど」
「じゃあ、きみが僕を求めた、と言い換えようか」
そう言うと男は、その無邪気な笑顔に真っ白な歯を添えた。
それがジョージとの最初の出会いだった。
(2章へつづく)