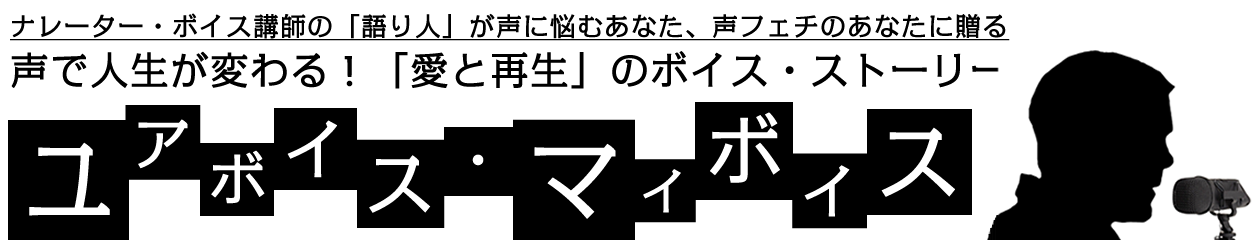「でも語り人さんは、役者のオレに惚れたんすよね」
「おまえ、誤解を招くようなことを…」僕は玲子さんの顔色を窺った。
「やっぱりあなたたち、そういう関係だったのね!」玲子さんの目が吊り上がった。
「オレね、語り人さんにナンパされたんだよ。男にナンパされたのは初めてだった」
(最終章「一流の証明(前編)」のつづき)
「あなたたちはいったいどこで出会ったの? 大学は違うはずよね」玲子さんは疑り深い目をして訊いてきた。
「喫茶店だよ。池袋にある珈琲専門店。オレ、そこでバイトしてたんだ。大学三年のとき。語り人さんは四年で、すでに就職先の内定を取っていた。大企業のね」
そう言って一柳は、茂森愛由美をちらりと見た。
一柳は当時、大学に通うかたわら池袋にある演劇学校の夜間部で、演技の勉強をしていた。そうそうたる大物俳優やミュージカルスターを数多く輩出している名門だ。
僕は大学の四年間、その演劇学校と目と鼻の先の安アパートに住んでいて、そこで催される役者の卵たちの舞台公演を欠かさず観ていた。
「語り人さんは当時、学校では知らない人がいないくらい有名な人だったんだ。オレたち役者の卵に愛あるダメ出しをする影の演出家としてね」
「えっ、どういうこと? 語り人さんはその演劇学校に関係していたの?」
一柳の話に玲子さんは疑問を投げた。
「いや、そうじゃない。芝居のあとお客さんに記入してもらうアンケートがあるだろ。語り人さんはいつも、演出を含めた舞台全体の感想と、出演者一人ひとりの所見を事細かに書いてくれていたんだ。無記名のお客さんとして」
「良いところ悪いところ、こうすればもっと良くなるとかね。用紙の枠をはみ出してぎっしり書かれている。みんながそれを指針に稽古に励むほど的確にして愛情溢れる言葉が。この人はいったい誰だ? 何者だ?って」
「なんで、その人が語り人さんだってわかったの?」
「その喫茶店でわかったんだよ。オレがコーヒー置いて立ち去ろうとすると、そのテーブルの客が話しかけてきた」
「『舞台"飛龍伝"で全共闘のリーダー桂木順一郎を演じた、一柳成人くんだね。ここでバイトしてるの?』って」
「びっくりしたよ。舞台を観てくれた方ですか?って訊いたら、『観た。いい役者に出会えたと思った。君のことだよ』って言うんだもん。そのときぴんときたんだ」
「もしかして、あのアンケートの方ですか?」
「『アンケート? ああ、書いたよ。いつも勝手に書かせてもらってる。君のことは、ええっと』語り人さんは少し考えてから歌うように朗誦した」
「立ち居振る舞いに品格あり。群舞で見せたダンスは頭抜けている。未来のミュージカルスターの片鱗を見た思い。声は良いが発声と滑舌、ブレスの使い方にやや難あり。声の良さに頼り過ぎか。枯れない声帯を獲得すべし。しかしこの男、なんと魅力的な役者だろう。確かこんな感じだったかな」
「はい。ありがとうございます。いただいた言葉を胆に銘じ精進しています! あのオレ、あと1時間でバイトが終わります。そのあと…」
「『いいよ。どうせここで長居するつもりだったから』そう言って語り人さんは、テーブルに積んである買ったばかりの5~6冊の本に目をやって笑った。痺れるようなカッコいい笑顔だった」
「ちょっと待って。語り人さんにナンパされたって言ってたけど、あなたのほうから誘ってるじゃない」と言って玲子さんは一柳を睨んだ。「まあ、いいわ。それで、そのあとどうなったの?」
「語り人さん行きつけの飲み屋に行った。パリのモンマルトルにありそうなアンダーグラウンドなバーでね、学者や作家、アーティストたちの溜り場みたいな店。ママが不思議な人だったな。不愛想で殆ど喋らないのに、なんか人を惹きつける磁力のようなものを持っていた」
「大学時代は助けてもらったな。出世払いだって、いつもタダ酒を飲ませてくれた。タダ飯もね。あのころはなにしろ金がなくて、いつも腹を空かせてた」と僕は笑って言った。
「一柳を初めて連れて行った日は忘れられないよ。あの不愛想なママが珍しくうれしそうな顔を見せた。おまえがトイレに立ったとき言われたもん。あなた、はじめていい男を連れてきたわねって」
「あはは。語り人さんがトイレに立ったときは、オレに言ってたっすよ。語り人さんは毎回、違う女を連れてくるんだって。そして女の品定めを自分にさせるんだって」
「それは誤解だ」僕は即座に弁明した。
「つきあいに発展しそうな女ができたら、関係を持つ前にかならず店に連れてこい。当時、ママからそうきつく言われてたんだ。一度、事後に連れて行ったときなんかこっぴどく叱られた。それどころか、あの女はやめておけ、語り人くんをダメにするタイプの女だ、とかなんとか言われて別れさせられたもん」
「えっ、オレには言ってくれなかったすよ」一柳は不満そうに言った。
「おまえはあまりにもとっかえひっかえ違う女を連れていくから、こりゃ言っても無駄だと、ママもあきらめたんだろう」
「あの、そのママさんですけど」茂森愛由美が突然、口を挟んだ。「先生が連れて行った女の子で、ママさんのお眼鏡にかなった人はいたんですか?」
「いや、ひとりもいない。やれ性格が悪いの頭が悪いの、育ちが悪いの服のセンスが悪いのって、何かにつけて難癖をつけられた」
「ママさんは、先生のことがお好きだったのではないでしょうか」
「まさか! それはないだろう。親子ほど歳が離れていたはすだよ。叱られてばっかりだったし」
「語り人さんと愛由美ちゃんだって、親子ほどの年の差でしょ。好きという気持ちに年齢差なんか関係ないのよ」玲子さんはいつもひと言多い。
「そうか。そういえば」一柳もまた余計なことを思い出したようだ。
「語り人さんと一緒じゃないときは、いつも訊いてきてたっすよ。語り人くんはどうしてる? 変な女に引っかかってないか。またトラブルに首を突っ込んでないか。ご飯を食べにくるよう伝えろとか。それに…」
そう言って一柳は驚くべき事実を口にした。
「ママは老け顔だったけど、親子ほど年は離れてなかったすよ。オレが21歳のとき35歳だったから、14歳差っすね。だから語り人さんとは13歳差」
「35歳なら今の私と同い年よ。女盛り真っただ中だわ」と玲子さんは語気を強めた。
「そうそう、語り人さん言ってたじゃないすか。おまえと店に行くとママは上機嫌で飲み代も受け取らないけど、女の子を連れていくとなんか不機嫌で、しっかりお勘定を請求されるんだって」
ひとつ思い出すとまたひとつ思い出す。まるで消えていた電球が一個ずつ点灯していくみたいに、一柳は四半世紀前の記憶を連鎖的に蘇らせていった。
「語り人さん、ママの気持ちにまったく気づかなかったんですか?」
玲子さんの責めるような問いかけに「いや、気づくも何も、ママのことは"池袋の母"って呼んでいたくらいだし…」と、しどろもどろになって僕は下を向いた。
「一柳さんも、ただ酒を飲ませてもらっておきながら、自分のことにしか興味がなかったのね」今度は一柳を責めるように玲子さんは言った。一柳も申し訳なさそうに下を向いた。
「本当にあなたたちは、今も昔も鈍感なお子ちゃまね! 当時のあなたたちと同い年の愛由美ちゃんがすぐにわかったのよ」
「あきれたわ。女ごころもわからないで、よくそれで文学だポエムだって、熱く語れたものよね!」
「お説ごもっともです。面目ない…」一柳と僕は、揃って鈍感な頭を垂れた。
大学を卒業して就職して、僕は池袋を離れた。その後、何度か店に行ったが、忙しさにかまけていつの間にか足は遠のいた。数年後に立ち寄ったとき、店はなくなっていた。ママは実家のある長野県に帰ったという話を、のちに当時の常連客に知らされた。
「おれはママに出世払いを済ませてないよ」と僕はつぶやいた。
「まだ出世してないけど、オレもっす」と一柳もつぶやいた。
「一柳、近いうちに長野に行こう」と僕は言った。
「そうっすね。二人でママに会いに行きましょう」一柳が応じた。
「ちょっと待って」と玲子さんが言った。「私も行くわ。お礼をしなきゃ」
「わたしも」と茂森愛由美が言った。「同行してよろしいでしょうか」
「ナイスアイデア!」一柳が叫んだ。「彼女ができたら連れて行く約束でしょ、語り人さん。四人で行きましょう! うん、それはいい!」
「なんで、そうなるんだ。また、ややこしいことになるじゃないか」と僕はつぶやいたが、弱り目に祟り目のこのつぶやきは一柳の大きなはしゃぎ声にかき消された。
「さあ、先を急ぐわよ。珈琲店で出会って、そのママの店でお酒を飲んで、それからどうしたの?」
「閉店まで飲んで、それから近くの語り人さんのアパートに移動して、朝まで語り明かした」
「その2週間後に、一柳は大学近くの国立のアパートから、おれのアパートに引っ越してきた」と僕は付け加えた。
「えっ、同棲を始めたの?」玲子さんが不適切な表現をした。
「まさか、6畳ひと間だよ。ちょうどタイミングよく一部屋空きが出たんだよ」
「すごいわね、なんか電撃結婚みたい。まるであなたたちが恋に落ちたみたいだわ」そう言って玲子さんは絶句した。
「ある意味、そう言っていいと思う。心強いパートナーというか、頼もしい用心棒を得た思いだった。少なくともオレにとってはね」と一柳は真顔で言った。
「大学には遠くなったけど、語り人さんの部屋まで30秒。演劇学校まで2分。ママの店には3分、バイト先にも5分と、オレの必要なものがぜんぶ至近距離に揃う好立地。まあ大学にはあまり行ってなかったし、語り人さんのいる場所がオレの大学だったから」
「とにかく二人が、出会った瞬間に雷に打たれたみたいに強い絆で結ばれたことはわかったわ。でもずっと不思議だったんだけど、なぜ一柳さんは語り人さんに敬語を使うの? だってひとつしか違わないでしょ」
「出合う前から、語り人さんはオレの師匠だった。出会ってからも、そして今も、その思いは変わらない」
「そのおかしな敬語はやめてくれって何度もお願いしたよ。でもこいつは、変なところで律儀というか頑固なんだよ」
僕が苦笑してそう言うと、一柳は持論を展開した。
「言葉使いが同等になると、関係まで同等だと勘違いするものなんすよ。オレと語り人さんは親友以上の関係だけど、決して同等じゃない。何度もオレを救ってくれた恩義ある師匠にため口はあり得ないっしょ」
「それはおれも同じだよ。おまえという友がいなかったら、オレの人生はもっと孤独で、もっと味気ないものだったと思う。おれのほうこそ、おまえにはずいぶん助けられた」
そのとき、嗚咽が漏れる音が聞こえた。見ると茂森愛由美が鼻を真っ赤にしてすすり泣いていた。
「はいはい。あなたたちの甘くほろ苦い青春ストーリーはこのへんにしておくわよ。少し時計の針を先に進めましょう」
玲子さんはディレクターみたいに右手の人差し指をぐるぐる回して指示を出した。
「一柳さんは大学を卒業して劇団に入った。そこから話して。劇団をやめた本当の理由。役者もダンサーもやめて実家に帰った理由よ」
「一柳、おれから話すぞ。いいな?」
「頼んます」一柳は観念して深くうなだれた。
一柳は演劇学校から文句なしの推薦を受け、難関のオーデションも難なく突破し、誰もが知る大手ミュージカル劇団に入団を果たした。
その劇団は他の多くの劇団と違い株式会社の形態をとっていることから、給料が支給される。したがって、入団ではあるが会社に入社したといえる。つまり一柳は、その劇団に就職したのだ。
ほどなくして、研究生としていくつかの舞台で新人離れしたパフォーマンスを見せつけた一柳は、とんとん拍子でミュージカルスターへの階段を駆け上がっていった。
研究生の域を超える輝かしい実績を積み、2年という研究生期間を待たずして、劇団の目玉である本公演の大役をつかんだのだ。
ところが、好事魔多し。(「好事魔多し(こうじまおおし)」とは、良いこと(好事)が続いていると、悪いこと(魔)が起こりやすいこと)
結論から言うと、このタイミングで一柳は女性問題を起こした。
相手は本公演で共演することが内定していた新進の人気女優だった。
役者が共演する相手と男女の関係を持つこと自体は珍しいことではない。しかし、このときばかりは相手が悪かった。状況も悪かった。
その女優が劇団の大物幹部の女であることは半ば公然の秘密で、そのため彼女に手を出そうとする男は、あるいは彼女の誘惑に落ちる男は誰ひとりいなかった。劇団内の男女相関図に疎い一柳はそれを知らなかった。
ではなぜ、その公然の秘密を一柳は知らなかったのか。
これは僕の想像だが、新人ながら一柳が持つミュージカル俳優としての才能とスター性は、同期の俳優どころか先輩俳優に比しても頭ひとつ抜きん出ていた。彼らにしてみれば一柳は脅威であり、できることなら弱みでも握って潰してやりたい存在だった。
これが公然の秘密が一柳の耳に入らなかった理由ではないか。彼らは人気女優が遅かれ早かれ、一柳に目をつけることがわかっていた。大物幹部との関係を知らない無邪気な一柳は、まんまと人気女優の手練手管にかかるだろう。あとは時期を見て、証拠を掴んで大物幹部にチクればいいのだ。
さらに悪いことに、入団してからずっと一柳は、密かに劇団の看板女優から特別な寵愛を受けていた。そして、その看板女優と大物幹部が夫婦同然の間柄であることもまた、公然の秘密だった。
これ以上、説明する必要はないだろう。要するに大物幹部は、自分の女をふたりとも一柳に寝取られたというわけだ。
情けない男になり下がって怒り心頭の大物幹部は、劇団内の公序良俗を乱す危険人物として、一柳に退団処分を言い渡した。
「そこまですることはないだろう」という反対の声も上がったが、彼はその声を全力で封じ込めた。そしてふたりの女優には何のお咎めもなかった。
さらに、大物幹部はそれだけでは気が収まらなかったのか、「もうおまえが入れる劇団はどこにもないと思え。よそにいってもおれが潰す」と脅しをかけ、ミュージカル俳優「一柳成人」を事実上、葬り去った。彼にはそれだけの力があった。
劇団の目玉公演の主役級に抜擢され、夢の舞台まであと一歩のところで文字どおり梯子を外された一柳は、ものの見事に転落した。物理法則に従って。
将来を嘱望されていたとはいえ、23歳の研究生に過ぎない非力な一柳に、いったい何ができただろう。どんな抵抗ができただろう。
よりによって劇団の看板女優、そして人気女優から「ご指名」を受けたのだ。当時の一柳に関係を拒む術などなかったし、拒んだら拒んだで、また別のやっかいな問題を誘発したに違いないのだ。
「これは一柳の名誉のために言っておきたい」と僕は言った。「一柳にはどうすることもできなかった。なにひとつ選択権がなかったということだ」
「すっごい話…。本当にあるのね、そんなドラマみたいな話」
玲子さんは整った顔を歪め、息苦しそうに言った。
「わたし、中学生の頃からそこの劇団の主要な演目は観ていますが、華やかな舞台の裏で、そんなドロドロのといいますか、生身の愛憎劇が繰り広げられていたのですね。それでも舞台の素晴らしさが損なわれることはない…」
茂森愛由美もこわばった表情で言った。
「こう言っては一柳さんのお気の毒なお話に水を差すようですけれど、そんなことも滋養にして生きていくのが俳優の性(さが)なのかって、逆にプロの逞しさといいますか、凄まじさが伝わってきます」
「それで、一柳さんは他の劇団には行かれなかったのですか?」
まずは卒業した演劇学校に行って仁義を切るのが先決だと、僕は一柳に進言した。そのうえで今後の相談をするのが得策だと。言い訳はするな。謙虚に頭を下げろ。そうすれば、またどこか推薦してくれるだろうと。
一柳は、お世話になった校長を訪ねた。ずっと目をかけてくれ、ミュージカル劇団に進むよう後押ししてくれた恩師だ。しかし校長は、一柳の訪問を喜ばなかった。
「わたしに恥をかかせてくれましたね」一柳を見るなり校長は険しい表情で言った。「きみの失態はわが校にとって大変不名誉なスキャンダルです」
「先生! 申し訳ありませんでした。オレは…」
「もう話すことは何もありません。帰りなさい」
一柳は泣いて許しを請うた。そして泣きながら訴えた。
「先生、教えてください! オレはどんな悪いことをしたんでしょうか。役者の道を絶たれるほどの、どんな罪を犯したんでしょうか」
「この期に及んでまだわたしに教えを乞うのですか。きみは本当にたちの悪い子です」と、校長は鉛のように重いため息をついて言った。
「頭がいいくせにバカのふりをする。内面に複雑さを抱えているくせに無邪気さを装う。そして今、わたしに謝罪しながらも、罪を認めていない。本当にたちの悪い子です」
僕は一柳からこのくだりを聞かされたとき、校長の真意がわかったような気がした。校長は一柳を「たちの悪い子」と二度言った。それは逆に言えば、「たちの良い子」がいい役者になどなれるわけがない。
バカのふりをできない人間が、いい役者になれるわけがない。内面に闇を抱えていない人間が、いい役者になれるわけがない。つまり校長は「だからこそ、きみはいい役者なんです」そう言いたかったのではないか。
しかし校長は最後まで、一柳に優しい言葉をかけることはなかった。
「女性問題には気をつけるようにと、あれほど言いましたでしょ。色事は芸の肥やし。外でならいくらでもおやりなさい。しかし劇団内の女優にはくれぐれも注意しなさいと」
「ここは学校だからまだよかった。プロの劇団はそうはいきません。目障りな者はすぐに足元をすくわれます。才能があるかどうかは関係ない。いや、才能があるほど標的は大きくなるでしょう」
「先生、オレはもう、どこの劇団にも入れないんでしょうか」
「きみは実に、やっかいな人を敵に回してしまったよ。実際の話、彼の目の黒いうちはむずかしいでしょう。もっとも彼の目の届かない、無数にある小劇団なら、その限りではありませんがね」
「いっそ、一般企業に就職したらどうです。きみは高学歴なんだから、少しはまともな会社に入れるんじゃないですか。とにかく、これ以上わたしにできることは何もありません。さあ、もう帰りたまえ」
ここまで言われては、これ以上の懇願も抗弁も無意味だった。
一柳は無言で頭を下げ校長室をあとにした。そして、役者としての自分を鍛えてくれた懐かしい学校に別れを告げた。こうして一柳の役者への道は、志半ばにして完全に閉ざされたのだ。
「語り人さんは、これは一柳さんにとって不可抗力の事件だったって擁護しましたけど、一柳さんに落ち度がなかったとは、私にはどうしても思えないのよ」
玲子さんが現実的な問題に引き戻して言った。
「だって、同性の嫉妬を買うなんてこと、一柳さんなら昔からずっとあったことでしょ。なんでそこで、うまく対処できなかったかなあ。それにふたりの女優も、一柳さんを見捨てたわけよね。自分が生き残るために、つまり保身のために、一柳さんを売ったわけよね」
「私はそこがひっかかるの」と玲子さんは続けた。
「お勉強ができてダンスがうまくて、そのうえ超イケメンで声も良くて。そりゃあ同性からの妬みとかやっかみもそうだけど、異性からちやほやされるのだって仕方のないことよ」
「でも頭のいい一柳さんがなぜいとも簡単に、そこでつまずいちゃったのか。天から授かったその能力を生かせなかったのか。私はそこが理解できないの」
「一柳は安心しちゃったんだよ」
玲子さんの疑問を氷解する答えかどうかわからないけど、僕は言った。
「天から授かった能力を遠慮なく発揮できる場所、自分がいるべき場所にやっと辿り着いたって」
「ここでなら特別視されることもない。なぜってここにいるのはみんな、選ばれた特別な人たちなんだから。一柳はそう思った。だから無防備だった。ここに人を陥れる悪意や計略が存在するなんて思いもしなかった」
ここで一息入れると、僕は玲子さんを直視して言った。
「それは玲子さんなら理解できるんじゃないかな。さっき席を外したとき一柳から聞いたよ。ミスキャンパスだったそうだね。芸能事務所からスカウトされた話も」
「そんな大昔の話、やめてください」玲子さんはうんざりした顔で返した。
「おれたちも大昔の話をしている。それこそ愛由美ちゃんが生まれる前の」
「私はミスキャンパスにも芸能界にも興味なんてなかった。ただ祭り上げられただけ。私の意思なんてどこにもなかったのよ。もう思い出したくもないわ」
玲子さんは吐き捨てるように言うと、何かを振り払うように続けた。
「わかったわ。一柳さんは純粋すぎた。警戒心も忘れてひたすら役者道に邁進した。そこは理解する。じゃあ、女性に関してはどうなの? ふたりの女優はなぜ、一柳さんをかばってくれなかったの?」
「私、思うんだけど、本当にいい男って、女を味方につけるんじゃないかな。女のほうが勝手に味方するって意味よ。この男を守ってあげたいとか、成功させてあげたいっていう、いわば母性本能ね。一柳さんはその女優たちを味方につけることができなかった。それは…」
そこで言い淀む玲子さんの代わりに僕は言った。
「一柳が愛さなかったから」
「ええ。でも、それだけかしら」
「ほかにも理由があると?」
「愛さなかったし、愛されなかった。本当には」
玲子さんのこの言葉は、言った本人も含めてみんなを黙らせた。
あなたはたしかに一流の「モテ男」かもしれない。
でも「愛され男」としては二流以下ではないのか。
そう言ったも同じだった。
沈黙の重たい帳が下りた。それを破ったのは一柳だった。
「そのとおりだ!」一柳の悲痛な声が響いた。
「オレはどの女も愛さなかったし、結果として、どの女からも愛されなかった。だからどの女も、オレのために持ち前の母性本能を発揮しようがなかった。玲子さんの言うとおりだ」
「玲子さん」と僕は言った。「あなたなら一柳の孤独がわかるはずだ」
「ごめんなさい。言い過ぎたわ…」玲子さんは素直に認めた。
「じゃあ、ちゃんと言って!」そして玲子さんは勝負に出た。
「そんなあなたが、初めて女を愛した。その女が、私なのね?」
一柳はゆっくりと大きく頷いた。
「何に誓って?」玲子さんは誓いを求めた。
「語り人さんに誓って」と一柳は答えた。
「おい、おれじゃなくて神に誓え」僕がそう言うと、
みんながくすっと笑った。張りつめた緊張の糸が少しだけ緩んだ。
「オレは宗教は信じないすけど、語り人さんのことは信じますから」
「わかった。信じる」玲子さんは即答した。
一柳の発言にめずらしくいちゃもんをつけなかった玲子さんは、大きく深呼吸をすると、覚悟を決めるように言った。
「じゃあ私も言う。こんなこと二度と言わないからよく聞いてね」
「私も初めてなの…こんな感情。だからとても混乱した。なんだか自分が恥ずかしくて、それを認めたくなくて、だからあなたを警戒したし、いやなこともいっぱい言った」
「わかってる。続けて」一柳は優しい声で促した。
「私も、初めて男の人を愛したんだと思う。あなたを」
「玲子さん!」一柳が歓喜の声をあげた。
「素敵です!」茂森愛由美も感動を露わにした。
「玲子さん、すばらしい。よく言ったね!」僕も手放しで喜んだ。
玲子さんが言ったことに触発されて、ある言葉が口をついて出た。
もの憂さと甘さがつきまとって離れないこの見知らぬ感情に、
「愛」という仰々しくも美しい名前をつけるのを、私はためらう。
それは自分にかまけてばかりの、あまりにエゴイスティックな感情で、
私は自分を恥じたくなるのだ。
「それ、なんの引用すか? 聞いたことないなぁ」一柳が首を傾げた。
「フランソワーズ・サガンの『悲しみよこんにちは』の冒頭部分に似ていますが、ちょっと違うような気も…」茂森愛由美も首を傾げた。
「愛由美ちゃん、正解。そう、サガンだ。いま玲子さんが言ったことに驚くほど似ていないか? たねあかしをすると、サガンは愛ではなく悲しみと言っている。タイトルが"悲しみ"だからね。ところが、このふたつの語を置き換えてもなんの違和感もない」
「本当にそうですね。先生、愛と悲しみは近似した感情なのでしょうか」
「ねえ、私が恥を忍んで、勇気を奮い起こして言ったことをネタに文学談義するの、やめてもらえます?」玲子さんが物言いをつけた。
「ごめんごめん。もうちょっと聞いてくれるかな。この『悲しみよこんにちは』は、サガンが18歳で書いた処女作なんだ。彼女は17歳のヒロインの女の子に、悲しみを"見知らぬ感情"と言わせている。つまり初めて経験する感情だと」
「これは、日本語で言うところの"箸が転んでもおかしい"少女からの脱皮を意味しているんだと思う。だから悲しみという名の、あるいは愛という名のエゴイスティックな感情に戸惑う。憂鬱になったり、イライラしたり、自分を恥じたりね」
「語り人さんが何を言いたいかわかりました」一柳が口を尖らせた。
「オレも玲子さんも、この歳になって初めて人を愛するという感情を経験した。それに付随する悲しみという感情も味わった。でもこれってふつう、17歳で経験することだぞ。おまえたちの脱皮はどんだけ遅いんだ」
「あははは」僕は笑って言った。「それでも、遅きに失したわけじゃない。少しばかり遅刻したけど、それは満を持してやってきた。堂々と迎えてあげよう。恥らいながらもね。悲しみよ、こんにちは。愛する人よ、こんにちは」
「そうっす! オレにもきてくれたんっす!」
一柳はそう叫ぶと玲子さんを見て最高の笑顔で言った。
「玲子さん、こんにちは」
「一柳さん、こんにちは」
玲子さんは持ち前のツンデレキャラを発揮して、恥らいがちに返した。そして何か大事なことを思い出したみたいに、慌てて次の言葉をつけ加えた。
「あっ、もちろんこの歳だから、今まで何もなかったとは言わない。そこはいいわね?」
「あたりまえでしょ」と言いながら、一柳は玲子さんの手を取った。
「そりゃあそうよね。いっぱいオイタをしてきたあなたに較べたら、私なんて無傷みたいなものだわ」そう言いながら玲子さんは一柳の手を振り払い、茂森愛由美を見た。
「愛由美ちゃんは初めてなの? 語り人さんへの感情は」
茂森愛由美は恥かしそうにこっくりと頷いてから言った。
「でもおかしいんです。先ほどから考えていたのですけれど、わたしには、憂鬱になったりイライラしたりという副作用がないんです。自分を恥じる気持ちもありません。むしろ尊敬する方をお慕いしている自分が誇らしくさえあります。わたし、どこかおかしいのでしょうか」
「もういいわ」と呆れた顔で玲子さんは言った。「愛由美ちゃんに聞いた私がバカだった。あなたは私と違って、ひねくれていないものね」
「それは相手が語り人さんだからだよ」と一柳がしたり顔で言った。
「愛由美ちゃんの感情は"愛"とは少し違うんじゃないかな。むしろ"敬愛"と呼ぶべきものだとオレは思う」
「でも"敬愛"なら初めて経験する感情ではありません。両親や学校の先生に対して、すでに経験ずみの感情です」茂森愛由美はめずらしくむきになって反論した。
「じゃあ"思慕"はどうかな? 語り人さんに会う前、見知らぬ感情だった?」一柳はしつこく食いついた。
「"思慕"はわたしも考えました。たぶん、初めてだと思います」
「じゃあ、それだ」一柳は病名を特定する医者のように断言した。
「否定はいたしません。たしかにわたしは、先生に対して思慕の情を抱いています。それなら伺いたいです。思慕は愛とは違うのですか? 愛は人を憂鬱な気分にしイライラさせるけど、思慕はそうならないということですか?」
「いや、それは…」一柳は答えられない。
愛由美ちゃん、いい質問だ。加えてすばらしい問題提起だ。と僕は思ったが、やぶ蛇になることを恐れて黙っていた。
「一柳さん、あなたの負けよ」玲子さんが調停をしてくれそうだ。
「何が負けって、ぜんぶ負け。あなたは愛由美ちゃんを子ども扱いしてるみたいだけど、愛由美ちゃんはあなたよりずっとおとな。ちゃんと自分をわかってる」
「あなたはまだわかってない。だいたい40も半ばにして初めて愛を知った情けない男が、偉そうに愛を語るんじゃないわよ。そんなことだから、夢からも女からも見放されるのよ」
玲子さんはすごい。いつもなら僕が言うであろう文句を、僕よりまっすぐな力のある直球でぶつけている。それでいい。こうして二人は、互いの愛を育てていくのだろう。
「ごめんなさい、玲子さん」一柳は萎れたキュウリみたいにヘナヘナになって謝った。そんな一柳に玲子さんは、私じゃなくて愛由美ちゃんに謝りなさいと命令した。
「愛由美ちゃん、ごめんなさい。40男にしてお子ちゃまのオレが、もらったばかりの愛を見せびらかしたくて、つい知ったかぶりをしちゃいました」
一柳がそう言うと、みんなが吹き出した。みんながお腹を抱えて笑った。
茂森愛由美は一柳の言いかたが可笑しくて笑った。玲子さんは一柳の気持ちがうれしくて笑った。そして僕は、一柳と玲子さんの愛の成就をよろこんで笑った。とにかく僕たちは、今日ここへきて初めて心から笑った。
笑いは心に余裕を生む。笑ったおかげでお腹がすいていたことに、僕たちはようやく気づいた。ずっと重たい話が続いたせいで、だれも箸が進まなかったからだ。ご馳走はまだたっぷり残っている。
しばらくは他愛のない話をしながら、僕たちは次から次へと料理を平らげていった。
「ところで、一柳さんと玲子さんの馴れ初めをまだ伺っていませんよね」
お腹が落ち着いたところで、茂森愛由美が興味津々といった様子で口火を切った。
「あっ、一柳がなんで金持ちになるって喚き出したのかも聞いてないぞ」
半年前に持ち上がった、一柳の「金持ち宣言」を僕は思い出した。
「それはね…」一柳が言いかけると、玲子さんが遮った。
「待って。一柳さんが役者の夢破れて実家に帰ってから、10年の歳月を経て再び上京し、ナレーターになった経緯をまだ聞いていないわよ」
やれやれ、今夜はいくら飲んでも酔いそうにない。僕と一柳は、ご馳走に伸ばしかけた手を引っ込め顔を見合わせた。
(次回、最終章「一流の証明」完結編につづく)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 異性の友人が「つきあってる人に会わせろ。見極めてあげるから」なんて言ったら、その異性の友人は、実は友人として以上にあなたのことが好きなんだって、知ってた?
- 女性の35歳は女ざかり真っただ中。はい、今ならよくわかります。
- 「出世払いでいいよ」って言われても忘れちゃうよね。じゃあ出世しなかったらどうなの?って話。出世したかどうかは主観だし。あはは。大事なのは「借りは絶対に返せ」ってこと。
- よく聞く言葉。「男ってホント、鈍感な生きものよねぇ」。じゃあ、敏感な男と付き合ってごらん。マジ、疲れるよ。現代を生き抜く上で必要な能力、それは「鈍感力」だ。
- ビビッとくる電撃的な出会いってあるよね。異性であれ同性であれ、その人はあなたのソウルメイトだよ。ソウルメイトはあなたの人生のカギを握る重要人物です。
- 異性問題で人生を狂わされるなんて、バカだなって思うよね。でも、うまく立ち回れないバカは純粋ってことじゃない? うまく立ち回るお利口ちゃんは不純ってことじゃない? 純粋に惚れて惚れられて、結果、人生が狂わされるなら本望じゃないか。
- 自分で能動的に選んで入った世界。人に言われて受け身的に入った世界。ただなんとなくの流れで入った世界。動機は何だっていいんじゃない? そこで自分の居場所が見つけられれば。だって、自分らしくいられる場所を見つけることが、いちばん大変なんだから!