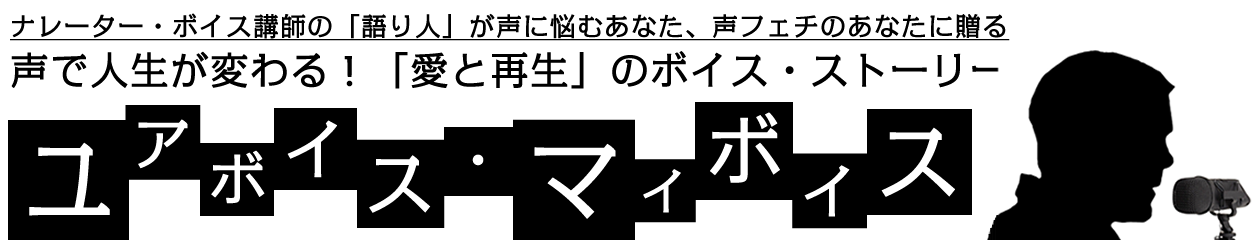宝石を散りばめたような美しさといわれる横浜の夜景が
視界いっぱいに広がった。
言わなければ。今だ。今、言うんだ!
僕は大きく息を吸った。
(7章「一流の女性たち」のつづき)
地下鉄みなとみらい21線で新宿三丁目まで行き、そこから丸ノ内線に乗り継いで四谷三丁目に着いた。駅のアナログ時計の針は19時半を指していた。宴会を始めるには遅すぎず早すぎずの時間だ。
これからが大事な話になる。
茂森愛由美にとって。それから一柳にとって、三条玲子にとって。
もちろん僕にとっても。
半年前はまだ予兆に過ぎなかった四人の縁が動き出し、今その四人がはじまりの場所で一堂に会し、今後の人生が大きく変わるだろう決断を一人ひとりが下すのだ。僕は出会いの不思議を思わずにいられなかった。
店に到着すると、店長はじめスタッフのみんなから熱烈な「お帰りなさいコール」を浴びた。
いやな予感がした。賑やかしいクラッカー音で迎えられ、「祝!声優デビュー!」と書かれた垂れ幕が下がっているのではないか、という予感だ。店内を見回したが特別変わったことはなく、ほっと胸をなでおろした。
すぐに個室に案内され部屋に足を踏み入れると、いやな予感はやっぱり外れていなかったことを思い知った。床の間に大きなくす玉が仕掛けられていたのだ。僕は見なかったことにした。
「いやぁ、こんなご馳走を用意してもらって申し訳ないっす。愛由美ちゃんのお祝いに、オレたちまでご相伴にあずかって」
一柳はくす玉ではなく、テーブルに並んでいる大きな寿司桶やご馳走の数々が真っ先に目に入ったらしく、興奮して言った。
「何をおっしゃる。愛由美ちゃんが今日という日を迎えられたのは、一柳さんのおかげでもあります。その一柳さんの大切な方まで連れてきてくださって、今日はなんてうれしい日でしょう!」
山田店長はそう言って玲子さんに熱烈な握手を求めると、感激の面持ちで続けた。「一柳さんの初恋のお相手がどんな女性か、ずっとその話題で持ち切りでしたからね。もう想像どおりというか想像以上の麗しい方で、感激もひとしおです」
「ちょっと待ってくださいよ!」一柳が気色ばんで言った。「その話題で持ち切りって、どういうことすか? いったいここは、プライバシーってものがないんすか!」
「プライバシーって、よくそんなことが言えたわね」
玲子さんがすかさず切り返した。
「だったらなぜ私が、愛由美ちゃんのことを知ってたの? 店長さんだって、今日はじめてお会いしたとは思えないほどよ。それはなぜ? ぜんぶあなたから聞かされていたからでしょ。あなたにプライバシーをうんぬんする資格はないの」
玲子さんのもっともな突っ込みに一柳はタジタジになって、例のごとく盛大な笑いでごまかしてから「ほら、この切り返し、語り人さんにそっくりでしょ」と僕を見てうれしそうに言った。
今日は店が立て込んでいるらしく、店長は「私はまたあとで少し参加させてもらいますが、みなさん遠慮しないでどんどんやってくださいね」と言って笑いながら出て行った。
「ちょっと一柳さん、今のは聞き捨てならないわね」
玲子さんが突然、目くじらを立てて言った。
「もちろん、語り人さんと突っ込みどころが同じなのは光栄よ。でも、もしかしてあなた、語り人さんと切り返しがそっくりという理由で、私のこと好きになったわけ?」
玲子さんの追撃に一柳は、今度は真面目な表情で答えた。
「それは確かにあるかもしれない。昔からオレを本気で叱ってくれる人は語り人さんだけだったから」
「まあ、それはいいわ。ごまかさないで率直に答えたことは評価してあげる。さっきも言ったように、これから一柳さんと語り人さんふたりの事情聴取に入るけど、その調子で頼むわよ。でもそのまえに」
そう言って玲子さんは、ずっと思いつめた様子の茂森愛由美に目をやった。
「こっちの事情聴取が先かもね」
「語り人さん、愛由美ちゃんに何を言ったんすか?」一柳が真面目な顔で訊いた。
「おまえはもう気づいてるんだろう? 愛由美ちゃんの卒業後のことだ」と僕は答えた。
「卒業したら、ずっとおれのそばにいろって話?」玲子さんは声をオクターブ上げてはしゃいでみせたが「そんな雰囲気じゃないみたいね」と声のトーンを戻して言った。
「事務所をやめろ。声優にはなるな、でしょ?」一柳がぼそっと言った。
「えっ、どういうこと? ちょっと問題を整理させて」玲子さんが眉間に人差し指を当てて言った。
「その会社というか事務所? 事務所側にとって愛由美ちゃんは金の卵なわけよね。アイドル声優として大々的に売り出したい。でも愛由美ちゃんはアイドルじゃなくて、実力のある本格声優として認められたい。そのために今、語り人さんがバックアップしている。私の理解は間違っているかしら?」
「間違ってないよ。でも語り人さんはそもそも最初から、愛由美ちゃんを声優にしたくなかったんだよ」そう言って一柳は僕の目を覗き込んだ。
「で、語り人さん、愛由美ちゃんをどうしたいんすか?」
「お嫁さんにしたい、じゃないのよね」と玲子さんが首を傾げた。
玲子さんの言葉に苦笑して僕は言った。「声優をやめて就職するよう進言した」
「先生」茂森愛由美がはじめて口を開いた。「先生ははじめから、わたしを、声優にするつもりはなかったのですね。それならどうして、レッスンをつけてくださったのですか? 教えてください」
「そうよ!」黙っていられないとばかりに玲子さんが割って入った。「レッスンをつけて、声優の仕事をさせて、そのデビューの日に、こんなデビュー祝いまでして、それで声優をやめろだなんて、そんな話聞いたことがないわ。ちょっと残酷なんじゃないかしら」
玲子さんの意見はもっともだった。
「今日、愛由美ちゃんがどんなにうれしかったか、どんなに幸せだったかわかります? どんなに語り人さんを信頼し寄り添っていたか知ってます? 私は一緒にいて痛いくらい感じたわ。それなのに何? 同じ業界にいて愛由美ちゃんがアイドルになって、その事務所だかに奪い取られるのがいやなの? オタクたちにもみくちゃにされるのが我慢ならないの? それならそれで男らしく、おれのそばにいろって言えばいいじゃない!」
玲子さんの抗議は続いた。
「就職しろですって? 愛由美ちゃんが観覧車で聞きたかったのはそんな言葉じゃなかったはずよ。高いところまで上げておいて、直後に落として放り出して逃げ出そうなんて、無責任にもほどがあるんじゃない? 正直言って私、語り人さんを見損なったわ」
「いいかげんにしないか!」一柳が玲子さんに声を上げた。
「語り人さんの真意も知ろうとしないで、勝手に先走るんじゃない!」
一柳の剣幕に玲子さんは驚いて息をのんだ。彼女はこれまで一度も、一柳に怒鳴られことなどなかっただろう。気づまりな沈黙のあと、一柳が照れ笑いのような表情を浮かべて言った。
「語り人さん、すみません。オレの連れ合いが失礼なことを言って」
「いや、玲子さんの言うとおりだ。無責任と言われても仕方がない」
「そうじゃないっしょ」一柳はふっと笑ってから言った。
「語り人さんの弱点その1、女ごころをわかってそうでぜんぜんわかってないこと。弱点その2、責任感が強すぎて相手をビビらせること。結果、その人の人生を変えてしまう」
一柳は続けて言った。「で、最後は責任をとって自分の人生まで変えちゃう。語り人さんはそんな人だ。オレのときもそうだった」
「まあ、その話はあとにしてと…」一柳は咳払いをして言った。
「アナウンサーですか? 愛由美ちゃんをテレビ局に就職させようって魂胆でしょ、語り人さん」
やっぱり一柳はお見通しだった。僕は肯いてから「愛由美ちゃん、すまない」と言った。茂森愛由美は俯いたまま何度も首を振った。
「でも、最初から考えてたわけじゃない。君の能力と性格を知れば知るほど、君を声優という枠に嵌めることに疑問を感じるようになった。ちょうどそんなとき、アナウンサー役の仕事がきた。これだと思った。それからはアナウンサーの発声とイントネーションを徹底的に叩き込んだ」
「なるほど。語り人さんにとっては好都合でしたね。自然の流れでアナウンサーのトレーニングに切り替えることができたわけっすから」一柳が僕の心情を代弁した。
「質問していいかしら」と玲子さんが言った。「そのまえに、語り人さん、先ほどはすみませんでした。語り人さんの真意を知りもしないで、失礼なことを言いました。申し訳ありませんでした」と神妙な顔をして頭を下げた。
「いえいえ、その率直さで引き続きよろしく」と僕は笑って返した。「それに、玲子さんの言ったことは半分当たってることを白状しますよ。ただそれを、僕の口から言わせないでもらえるとありがたい」
「言わなくてもわかりますよ。ね、愛由美ちゃん」そう言って玲子さんはうれしそうに茂森愛由美の顔を覗き込んだ。茂森愛由美は恥かしそうに俯いた。
「で、語り人先生、質問なんですけど、声優のトレーニングとアナウンサーのトレーニングって、どう違うんですか?」
ついさっき、ドスを聞かせた声で僕を責め立てていた人が、急に新入生のようなかわいらしい質問をしてきたことがなんとも可笑しかった。この人はたしかに一柳に合っているな、と僕は思った。
「基本的には発声・発音などのトレーニング方法は同じだよ。役者でもアナウンサーでも"外郎売"はやるからね」と僕は言った。
「あ、知ってる。"拙者、親方と申すは"ってやつでしょう」
「よく知ってるね、玲子さん」一柳が言うと「これでも高校で演劇部だったのよ。入りたくなかったけど、無理やり誘われてね」と玲子さんは、嫌な思い出でもあるのか顔をしかめて言った。
「言葉を正確に伝える。つまり、日本語の50音を正しい明瞭な音で発声する点では、役者もアナウンサーも同じだよね。じゃあ、両者の決定的な違いは何か。愛由美ちゃん」僕は茂森愛由美に振った。
「はい。役を演技で表現するのが役者で、情報を正確に伝達するのがアナウンサーです。先生に何度も言われました。演技はエクスプレション(表現)でアナウンスはトランスミッション(伝達)だと」
「そうだね。だからトレーニング方法の違いを言えば、声優のトレーニングメニューから"演技"の項目を抜いて、たとえばそこに実況を伝えるための"フリートーク"を入れる」
「また、役者は役になりきるために自分の感情を解放しなければいけないけど、アナウンサーは逆だ。つねに感情を抑制し、あるいは感情を排して事実関係を客観的に伝えなければいけない。だから原稿の読み方はずいぶん違う」
「そうよね。犯罪のニュースやなんかで、アナウンサーが犯人を憎悪する口調で事件を伝えたり、被害者のために涙を流しながら原稿を読むなんて、見たことないものね」玲子さんの譬えはわかりやすい。
「まあ、アナウンサーの仕事にもいろいろあるから、感情を排するって一概には言えないけど。たとえばきょう吹き替えでやったインタビューなんか、まさにアナウンサーの腕の見せ所だね。実に気持ちよく相手にしゃべらせていた。愛由美ちゃんは翻訳もやったからよくわかっただろう。インタビュアーの質問の上手さが」
「はい。ゲストのプロフィールをとても綿密に調べ上げていたと思います。そのうえで通り一遍の質問ではなく一歩も二歩も踏み込んだ質問をして、それでいて相手の魅力と満足度を最大限に引き出しています」
「そのとおり。よくぞ聞いてくれましたって感じで、相手は膝を乗り出してうれしそうに答えている。これはアナウンサーのインタビュー力、つまり聞く力が優れているからだ。一流の証しだね」
ここで僕は、相手を納得させる「決め台詞」を言うために、丹田に気を込めた。
「愛由美ちゃんの能力はこのポジションでこそ活きると、僕は確信している。声の演技にとどまる必要はないと思う」
「先生」と茂森愛由美は涙声で言った「ごめんなさい。わたし、先生のお考えを何も理解できていなくて…。こんなわたしが、アナウンサーになれるでしょうか」
「だいじょうぶ、なれる。君は相手を喜ばせる聞く力を持っている。質問に対する答える力もある。それに」と僕は続けた。「僕の願いをかなえてくるって約束したじゃないか」
「すごいわ! まさに適材適所じゃない。アナウンサーなら、アイドルだなんだって悩むこともないし、その美貌も原稿読みのセンスも、当たり前のこととして活かせるってわけね」
玲子さんは手を叩いて喜ぶと、何か疑問を感じたらしく首を傾げて言った。
「ところで一柳さんは、語り人さんが愛由美ちゃんをアナウンサーにしようとしてるって、なぜわかったの?」
「語り人さんはね、タイミングを読む人なんだよ」一柳はニヤリとして言った。
「半年前、ここで初めて愛由美ちゃんと会ったとき、オレたちは愛由美ちゃんのキラキラした笑顔と、立ち居振る舞いのタイミングの良さに魅了された。それだけじゃなく彼女の言葉使いのセンス、会話の間合いの良さに舌を巻いたんだ。絶妙な間合いで繰り出される的確な質問や合いの手で、オレも語り人さんも気持ちよくなって、気づいたら寸劇までやっちゃってた」
「これは才能だと思った。でもこの才能は、とくべつ声優に必須の能力じゃない。語り人さんがそう考えてることが、オレにはわかったんだ」
「まあ、あなたちって本当に何でも分かり合うのね。まあいいわ。それで、愛由美ちゃんのその才能がアナウンサー向きだって思ったのね」
「オレはそこまで見抜けないよ。さっき、語り人さんと愛由美ちゃんの吹き替えを見てぴんときた。愛由美ちゃんは声優としてアナウンサーを演じていたんじゃない。すでにアナウンサーだった」
「どういうこと?」玲子さんの顏に?マークが浮かんだ。
「さっきも言ったろ。語り人さんはこのアナウンサー役を利用して、愛由美ちゃんをアナウンサーに仕上げたんだよ」
「えっ、なに? じゃあ、愛由美ちゃんは自分でも知らないうちにアナウンサーになってたってこと? なんだか語り人さんって魔法使いみたいね。あっ、ちょっと待って」と言って玲子さんは目を輝かせた。
「そうすると今日は、愛由美ちゃんの声優デビューであると同時に、アナウンサーデビューの日でもあるのね」
「玲子さん、うまいこと言うね。それ、いただき!」一柳はそう言ってから立ち上がり、床の間に吊るされたくす玉に手をかけた。
「じゃあ、せっかくですから、やりますか」そう言って玲子さんに、店長を呼んでくるように、それからビールのおかわりをじゃんじゃん持ってくるように頼んだ。
「じゃんじゃんって、この宴席は店長のおごりなんだぞ。おまえは少しは遠慮しろ」と僕がたしなめると、一柳はぺろっと舌を出した。
茂森愛由美が立ち上がろうとすると、玲子さんは「あなたは主役なんだから、先生にくっついて座ってなさい」と笑顔で言った。
店長と茂森愛由美のバイト仲間が次々にやってきて、乾杯の準備を整えた。乾杯酒にはシャンパンが用意された。山田店長が乾杯の音頭をとった。
「愛由美ちゃんの声優デビューとシャンパンスマイルに、シャンパンで乾杯! おめでとう!」
僕が命名したシャンパンスマイルは、茂森愛由美の代名詞としてすっかり定着していた。
茂森愛由美がくす玉の紐を引くと同時に、盛大なクラッカー音が鳴り響いた。ふたつに割れたくす玉から「茂森愛由美 祝!声優デビュー」と大書された垂れ幕が下がった。つまり、すべてが僕の予想どおりだった。
この店のみんなが、茂森愛由美の声優としての第一歩を心からよろこんでいるのだ。僕は申し訳ないような複雑な気分だった。
茂森愛由美にテレビ局のアナウンサー試験を受験させることを山田店長に告げなければいけなかったが、それはまた別の機会にしようと思った。今夜、店は大忙しだ。店長はスタッフを引き連れて、早々とフロアに引き上げていった。
そこで待ってましたとばかりに一柳が訊いてきた。
「で、語り人さん、どこの局を考えてるんすか。TBSあたりすか?」
「うん。民放ならね。でもおれは、本命はNHKだと考えている」
「たしかに。NHKは愛由美ちゃんの大学の先輩もけっこういますよね」
「ナレーションの達人も多い。何より語学力が大きな武器になるはずだ。NHKは世界で活躍できる環境が整っている。アイドルに祭り上げられる心配もないし、インテリジェンスを嘲笑うバカもいない」
「ねえ、ちょっと待って」と玲子さんが割って入った。「その選択は文句なしにすばらしいと思う。でも本人の気持ちを差し置いて、あなたたちだけで決めちゃっていいわけ? まず愛由美ちゃんの考えを聞くべきじゃないかしら。彼女にとっては寝耳に水の話なんだから」
「わたしは」と茂森愛由美は言った。「先生がそこまで、わたしのことを考えてくださっていたことが何よりうれしくて、幸せに思います。ですから、先生のお考えに従います」
「本音を聞かせて。本当はどうしたいの?」
「大学卒業後は就職しないで、先生の翻訳のお手伝いをさせていただきながら、先生のように、ナレーションを中心に声のお仕事をずっと続けていきたいです。レッスンも今までどおり続けたい」
「でしょうね。語り人さんのそばにいて、ずっと語り人さんと同じことをしていたい。それが本音よね」
玲子さんは茂森愛由美に同情の目を向けると、深い溜息をついてから思い切るように言った。
「でも私は、語り人さんの考えに賛成する。語り人さんは愛由美ちゃんが、愛由美ちゃんに相応しい場所に行くことを心から願っているのよ。それが最優先されるべきだって。本当は語り人さんだって…。わかるでしょ?」
俯いている茂森愛由美の目から大粒の涙がこぼれ、テーブルを濡らした。
「僕は愛由美ちゃんに…」不覚にも声が詰まり、ひとつ咳払いしてから僕は続けた。「一流を知ってもらいたいと思っている。だから、まずは大きな組織に身を置いてほしい。いわゆる大企業に」
「大企業の利点は言うまでもなくそのブランド力だ。社名を聞けば誰もが知っている。知名度、貢献度、影響力、社会的責任、それらを担う選良としての意識。つまり、優越も不安もひっくるめて肌で感じてほしい」
「選ばれてあることの恍惚と不安ふたつ我にあり」一柳が言った。
「太宰治の言葉ですね」茂森愛由美が引き取った。
半年前、太宰治は『走れメロス』と『人間失格』しか読んでいないことを恥じた彼女は、今では殆どの太宰作品を読破している。
「正確に言うと、19世紀フランスの詩人ヴェルレーヌの詩の一節を、太宰が自分になぞらえて引用した言葉」と一柳が繋いだ。
「そう。太宰の処女作品集『晩年』に収められている『葉』という短編に出てくるヴェルレーヌの言葉だね。自分は文学者として神に選ばれた人間だ。そんな太宰の自負と気負いが横溢する作品になっている。でもヴェルレーヌはね…」
「語り人さん、講義はまたにしてくれますか」
長くなりそうな僕の解説に一柳がストップをかけた。
「おまえがヴェルレーヌを持ち出すからだろ」
だったらおれをのせないでくれ、と僕は一柳を睨んだ。
「いや、きっかをつくったのは愛由美ちゃんすよ。こうやって愛由美ちゃんは、オレたちをのせるんだ。アナウンサーでも報道記者でもどっちもイケるんじゃないすか」そう言って一柳は満足そうに頷いた。
「話を戻そう」と言って僕は続けた。
「従業員3百人以上の大企業は、日本の企業全体の0.3% といわれている。その数字の理由を、内部から見極めてもらいたい。大企業が大企業である所以を、一流が一流である証しを、愛由美ちゃんに渦中で体験してほしいんだ」
「一流が一流である証し…」茂森愛由美は繰り返した。
「そうだ。商品であれ、システムであれ、人であれ」
「何年くらい、身を置けばそれがわかりますか」
「5年はいてほしい。翻訳家になるのもナレーターになるのも、それからでも決して遅くない。いや、むしろそのほうが、よほどすごい翻訳ができるし、よほどすごい語り力が身につくはずだ。」
「わかりました」茂森愛由美は鼻をすすり、こくりと頷いて言った。「それが語り人さんの願いだとおっしゃるなら、私はそうします。アナウンサーになります。合格できれば、ということですけど」
「大学の成績、容姿、適正、語学力、家庭環境、どれをとっても落ちる理由は見当たらない。だいじょうぶ」
赤くなった鼻をハンカチで抑えながら、茂森愛由美はぎこちなく笑った。
「うんうん、愛由美ちゃんなら心配ないわよ。万が一落ちたら、うちの会社にいらっしゃい。私の権限をもって、私の部署に配属させるわ。任せなさい」と玲子さんは胸を叩いて言った。
玲子さんは大手都市銀行の本社に総合職として勤務する、バリバリのキャリアウーマンだ。さっきスタジオで、スイーツタイムのとき名刺をもらって、僕はびっくり仰天した。
しかも、あるセクションのマネジャー職にあるというから、一般企業では課長に相当するポジションだ。入社13年で年齢は35歳。大手銀行の総合職は出世に男女差はないことは知っていたが、それにしてもスピード出世だろう。
桜木町駅で最初に見たときの玲子さんの第一印象は、次のとおりだった。
年齢は20代後半に見えるが実年齢は30代半ば。人に命令することに慣れている。男には負けないわよという勝気な性質。これらはすべて当たっていた。でも銀行に勤務する会社員というのは意外だった。
「いちおう大企業の部類に入るから、いいですよね、語り人さん」
「それは本人に返答してもらおう」玲子さんの問いかけに、僕は茂森愛由美を促した。
茂森愛由美は玲子さんに感謝の言葉を丁重に述べてから「保険はかけるな。これと決めたらよそ見はするな。ひとつことに集中しろ。先生はそう仰ると思います」と言った。
「先生がだいじょうぶと仰るなら、わたしは安心してアナウンサー試験の準備に取り組むだけです」
「はいはい、わかったわ。まあ、息の合った師弟だこと」玲子さんは物分かりのいい親戚のおばさんみたいな言い方をした。
「じゃあ愛由美ちゃん、あなたはこれまで抱きつづけてきた夢を捨てて、語り人さんのお願いをきいてあげるんだから、遠慮しないであなたからもお願いしちゃいなさい」
「わたし、声優をやめても、大学を卒業しても、先生から卒業しませんから。今までどおりレッスンをつけてください。わたしを、テレビ局のアナウンサーにしてください。そして将来…」ここで言い淀んでから、茂森愛由美は言葉を継いだ。
「会社員を5年経験したら、わたしを、ナレーターにしてください。翻訳家にしてください。そして、いつも先生の近くにいさせてください。それが、わたしの願いです」
「NHKのアナウンサーになるまでは全面的にサポートする。それは約束する」と僕は言った。「でも会社に入ったら、君には新たな世界が待っている。今からその先の未来を限定することはない」
「わたしは、自分の希望する未来を、今から限定したいんです。5年先、10年先の未来予想図を描いておきたいんです」
「ある詩人は言っている」と僕は言った。
未だ来ないものを人は創っていく
未だ来ないものを待ちながら
限りある日々の彼方を見つめて
人は生きていく
「谷川俊太郎ですね」と茂森愛由美は言った。
誰もきみに未来を贈ることはできない
なぜなら きみ自身が未来だから
「ちょっと語り人さん。詩の言葉の引用で事態を曖昧にしてはぐらかそうとするの、私は好きじゃないな。自分の言葉で、具体的な返事をしたらどうかしら」と玲子さんは異議を唱えた。
「玲子さん、だいじょうぶです」と茂森愛由美は言った。「先生は、はぐらかしてなんかいません。今のわたしにぴったりの言葉をくださいました」
「きみ自身が未来なのに、何を今、未来のあれこれを限定する必要があるだろう。未来に繋がる今日を大切に生きること、それがきみ自身を創り、未来を創ることに他ならないのだから」
茂森愛由美は自分の言葉で、この詩を意訳した。
「先生は、そうおっしゃりたいんだと思います」
「なんかあなたも、語り人さんと一柳さんみたいになっちゃったわね」
玲子さんは僕と一柳を見て大きな溜息をついた。
ここで一柳が「うーん」と唸り声を発した。
出た。一柳お得意の「まとめの言葉」が始まるタイミングだ。
「未来のことはある程度、曖昧にしておいていいんじゃないかな。どうせ、修正を余儀なくされるんだ。上方修正にせよ下方修正にせよ。会社の中長期計画みたいにね。自分の人生は社長も株主も自分だから、だれに気兼ねすることもない」
「わかったわよ。私だけ理系で分が悪いわ」と玲子さんは観念して言った。「まあ、私は愛由美ちゃんがよければいいのよ」
そう、玲子さんは理系女子なのだ。偏差値最高クラスの私立大学の数学科を出ている。これも驚いたことのひとつだった。
そのとき一柳がまた唸り声をあげた。まだまとめ足りないのかと思っていると意外なことを言った。
「分が悪いのはオレですよ。大企業どころか、オレだけ就職未経験者だもん。語り人さん、ズルいっすよ。なんで大学時代、オレに言ってくれなかったんすか!」一柳が恨みがましそうに言った。
「何をだよ?」と僕は訊いた。
「さっき愛由美ちゃんに言ったことっすよ。大企業に潜入して0.3%という数字のトリックを見破ってこいって」
「おれはそんなことは言っていない」呆れて僕は返した。
「大企業で5年辛抱して働いて、それから劇団に行けば、オレの人生はもっとましなものになってたのになぁ」
「言ったよ。言ったけど、あのときのおまえは聞く耳を持たなかっただろ。卒業したらすぐに劇団に入るんだって、それしか頭になかったじゃないか」と僕は反論した。
「もっと説き伏せてほしかったすよ。あーあ、あのときのオレはバカだったなぁ。遊び人の役者バカ」一柳はそう言って嘆息した。
しかし、そのあとすぐに切り替えてニヤリと笑った。「でも語り人さんは、役者のオレに惚れたんすよね」
「おまえ、誤解を招くようなことを…」僕は玲子さんの顔色を窺った。
「やっぱりあなたたち、そういう関係だったのね!」玲子さんの目が吊り上がった。
「オレね、語り人さんにナンパされたんだよ。男にナンパされたのは初めてだった」
「わかったわ。そろそろ、あなたたちの事情聴取に移ろうじゃないの」
そう言って玲子さんは茂森愛由美を見た。「愛由美ちゃん、いいかしら」
「はい、わたしも、先生と一柳さんの大学時代のお話に興味があります」と茂森愛由美は目を輝かせて言った。「玲子さん、わたしは陪審員という立場でよろしいでしょうか」
「愛由美ちゃん、いいわね。その調子で頼むわ」そう言うと玲子さんは、容赦ない冷徹な検事のような皮肉な笑みを口の端に浮かべた。
(次回最終章「一流の証明(後編)」につづく)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 出会いが人を動かし道を開くきっかけとなる。求めれば必ず出会える。笑顔でいなさい。素直でいなさい。懸命でありなさい。誠実でありなさい。
- もう一度言う。笑顔でいなさい。素直でいなさい。懸命でありなさい。誠実でありなさい。それが愛される条件だ。芸能の世界だけではない。どこにいようと、生きるという営み自体が「人気商売」なのだ。愛される人になりなさい。そしてそれ以上に、愛する人になりなさい。
- スクールや養成所に行っていることでやっている気になっている人が多い。生活のためのアルバイトや仕事を言い訳にして、日々の勉強やトレーニングの時間をつくれない人が、どうしてその道のプロになれるだろうか。
- 「聞くために話す」人と「話すために聞く」人がいる。立て板に水のごとく一方的にしゃべって相手を説得してしまう人を「話上手」とは言わない。それは単に「口がうまい」だけだ。
- 物語の性質上、ここでは登場人物のひとりに大きな組織、大企業に入ることを推奨しているが、これはあくまで一例に過ぎない。零細・中小企業には、大企業にはない良さがある。それは主に、部分ではなく全体に携わる仕事ができることだ。そして言うまでもなく、ここにも一流が存在する。一流=大組織ではない。
- 出あって別れて、泣いて笑って、愛して憎んで…。始業と卒業、期待と諦観、希望と絶望、夢と現実、勤勉と怠惰、謙虚と傲慢、尊敬と軽蔑、集中と散漫、注目と無視、理解と誤解、前進と後退、勇気と臆病、善意と悪意、決断と我慢、勝利と敗退…。逆転現象はいつだって起こるんだ。でも、人生はいくらでも修正がきくのだよ。だって、自分が主人公だもん。