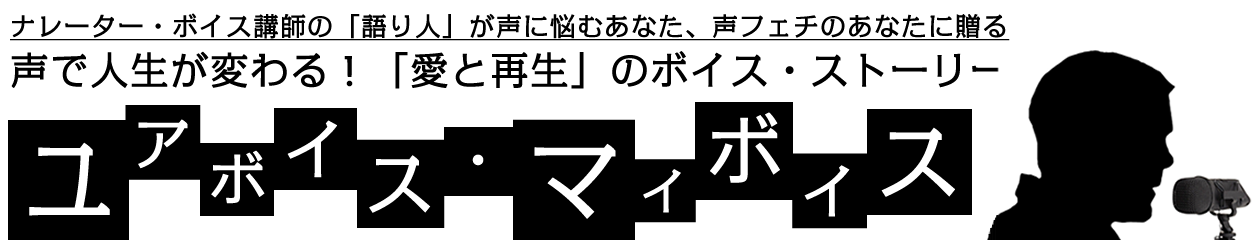そのとき突然、一柳が振り向いたので目が合ってしまった。一柳は少し驚いた表情を見せたが、横にいる茂森愛由美の存在に気づくと、さらに驚いた顔をした。
「おやおや」と一柳は言った。
「おやおや」と負けずに僕も返した。
(6章「一流の選択」のつづき)
「語り人さん直々のお出迎え、まことに痛み入ります。しかも目の覚めるような麗人もご一緒とは、なんとも光栄の至りです」
驚いたときいつもそうするように、一柳は慇懃な態度でおどけて言った。
「何をおっしゃる。赤坂・汐留近辺をワーキングスペースとする貴君を横浜くんだりまで呼びつけたんだ。このくらいの歓迎は当然だ」
そう言って僕も応戦した。「しかも、やんごとない同伴者もおいでとは、貴君も隅におけない。ぜひご紹介賜りたい」
「あーはっはっはー!」一柳は得意のごまかし笑いをした。
「あーはっはっはー!」僕は苦手のごまかし笑いをした。
「いつもそうやって、ふたりで遊んでるんですね」
一柳の連れの女性が口を開いた。人に命令や指示を出すことに慣れている声と物言いだ。
「あ、失礼。私、三条玲子と申します。三つの条件の三条に、王ヘンの玲子です。今日はお仕事の現場にのこのこついてきてすみません。私が一柳さんにお願いしたんです。語り人さんにぜひお会いしたいと」
「は? 僕に、ですか?」僕は素っ頓狂な声を上げたはずだ。
「ええ、そうです。一柳さんの話に一番多く登場するのが語り人さんなんです。彼はあなたのことになると、とてもうれしそうにイキイキ話すので、どうしてもお会いしたくなりました」
「一柳をもっとよく知るために、ですか?」と僕は訊いてみた。
「失礼ながら、おっしゃるとおりです」
「なるほど。どんな人物かを知るにはその人の友を見よ、ですね」
「気分を害されたのなら謝ります」
「とんでもない。率直さは一番の美徳だと僕は考えています。だから遠慮なく、その調子で」僕は笑って言った。「率直さにかけては僕も一柳も相当なものです。だから敵は多く友達は少ない」
「想像どおりの方ですね、語り人さんは。安心しました。それから、たぶん間違いないと思うのですが、そちらのお嬢さんは茂森さんですね」と三条玲子は一柳ではなく、僕と茂森愛由美を見て言った。
一柳が茂森愛由美のことまで彼女に話していたことに、僕は少なからず驚いたが、当の本人はいたって素直にあのシャンパンスマイルで対応した。
「はい。はじめまして。茂森愛由美と申します。一柳さんとは一度お会いしただけですが、語り人先生からいつも聞かされていますので、よく存じ上げております。その意味では三条さんとおなじですね」
茂森愛由美の発言に、三条玲子は初めてにっこり笑って言った。
「本当に素敵な女の子。ふたりの中年男が夢中になるのも無理ないわね」
「いや、おれは違うよ。おれが夢中なのはあなただけだ」
ここでやっと一柳が口を開いたが、三条玲子はその甘いセリフをスルーして意外なことを言った。
「やっぱり、語り人さんは茂森さんの先生になっていたのね。すごい! 一柳さんの予言どおりだわ」
「予言って、一柳、どういうことだ?」僕は一柳に詰め寄った。
「ていうか、あの状況から当然の帰結でしょう」
「あの日のおまえは、三条さんのことで頭がいっぱいだったはずだ。でも結局、何も話してくれなかった。名前だって今はじめて聞いた」
「カチカチ山のメタファから心理分析をして、おれの病状を言い当てたじゃないすか」
「そのくらいわかる。おまえの心は、ただ一人の女性への想いで溢れていた。そしてその女性のために、変わろうとしていた」
「でもあの日あの場所にもう一人、変化を必要としてる人が現れた」
「わたしのこと、ですね?」一柳の言葉に茂森愛由美が敏感に反応した。
「そう。君は語り人さんを求めるはずだし、語り人さんは君をほうっておかないだろうと思った」
「おいおい、だから三条さんのことを打ち明けるのをやめたっていうのか」
「そうっす。しばらくは二人の問題に集中させてあげようと思ったんすよ」
「余計なことを」僕はため息を吐いた。
「お互いが相手を思いやっていたって話ね。まあ、美しい友情だわ」
三条玲子はそう言うと、一柳と僕をそれぞれ睨みつけてからまた言った。
「それはそうと、私たち相当目立ってるわよ。いつまで私と茂森さんをここでさらし者にする気? 夢中になると周りが見えなくなる。本当にお子ちゃまなんだから」
「ごめんなさい」一柳と僕は同時にお子ちゃまらしく謝った。
茂森愛由美がクスクス笑って言った。「先生、あと5分で2時です」
「やばい。一柳、着いたらすぐ本番だぞ」
「うーっす」
スタジオに入ると、寺さんが父親みたいな顔をして待ちかまえていた。
「遅いから心配したよ。デートには時間が足りなかっただろうけどさ」
「寺さん、からかわないでくださいよ。一柳と駅でばったり会って、ちょっと立ち話が長話になってしまって…」彼女の父親に言い訳するみたいに僕はしどろもどろになった。
「寺さん、お久しぶりです!」一柳が声をかけた。
「一柳くん、久しぶり! 何年ぶりかな、4~5年は会ってないよね。ちょっとオジサンになったけど、相変わらず二枚目だね」
「寺さんもお元気そうで。相変わらずフィギュア作ってますか。今日は文句なしのモデルがきたって興奮してるんじゃないっすか?」
「一柳くん、なんでわかるの?」
そう言って寺さんは、茂森愛由美をチラリと見て赤面した。それから一柳のうしろにいる三条玲子に目をとめた。
「今日はいったいどんな日よ! べっぴんさんばっか現れてさ」
「おじゃまします。三条と申します。今日は一柳さんの付添人という位置づけでお願いします」
「ああ、一柳くんの彼女という位置づけね。お似合いだよ」
寺さんは三条玲子と一柳をかわるがわる見て、納得したように言った。
「あ、それからこれ、一柳さんからお好きだと伺ったので」
そう言って三条玲子は、寺さんに持参したみやげを手渡した。
「麻布十番の有名なケーキ屋のチーズケーキです。私も大好きです」
「知ってる! 知ってるけど、まだ食べたことなかったさ。うれしいなあ。ありがとう! あとでみんなでいただこうよ。茂森さんも、なんかおいしそうなもの持ってきてくれたんだよ」そう言ってスイーツ大好き寺さんは、女の子みたいに喜んだ。
知らなかった。こうした気遣いがさりげなくできる茂森愛由美が頼もしくも誇らしく思えた。もちろん三条玲子もさすがだ。
早くスイーツにありつきたい寺さんが号令をかけた。
「準備はできてるよ。いつでもOK」
「さあ一柳、いくぞ。よろしく頼む」
「ほーい。よろしくっす」
ふたりでブースに入り、分厚い台本をページめくりしやすいように整理していると、茂森愛由美がお盆に乗せてコーヒーを運んできた。
「ありがとう、ちょうど飲みたかった」僕は彼女の気遣いに感謝した。
「さすが茂森さん、相変わらずのグッドタイミング」一柳がウインクした。
「おふたりの掛け合いをこうしてまた見ることができるなんて、わたし、うれしいです。ドキドキしています。しっかり勉強させていただきます!」
茂森愛由美の素直さに僕たちは笑顔で応えた。
さあ、いよいよこの瞬間が訪れた。
ビル・ゲイツとウォーレン・バフェットの対談。
僕がゲイツをやり、一柳がバフェットをやり、
そして茂森愛由美が女子大生をやる。
さまざまなシーンが頭の中を去来した。
茂森愛由美にまっさきに知らせたときのこと。
バフェットの声を一柳に依頼したときのこと。
翻訳に頭を悩ませながらも楽しく充実した日々のこと。
茂森愛由美に何度も読み直しを命じた濃密なレッスン。
寺さんのキュー出しが耳に飛び込んできた。
「それじゃあ、絵を流しまーす。本番、さん、に、いち…」
(レコーディング中)
「ストップ! ちょっとごめん、止めてください。寺さん、すみません」
噛んだわけでも間違ったわけでも、リップシンクがずれたわけでもない。
それは完璧だった。さすが一柳だ。しっかり合わせてきている。
それでも僕は止めた。このままではだめだと思ったからだ。
一柳はダミ声を作ってバフェットを巧みに演じていた。
でも違う。それはバフェットじゃない。僕は一柳に言った。
「一柳、なんか違うよね」
「うん。オレもそう感じてるっす」
「バフェットはこのとき何歳だ?」
「あっ…」
「この対談当時、バフェットは70歳だ。もちろん年齢のわりに旺盛な生命力を持った怪物だ。でも声をよく聴いてみろ。単なるダミ声じゃない。独得の"枯れ感"がある」
「枯れ」とは人間的な深みのことだ。酸いも甘いも噛み分けた円熟の極みにある人。それが「オラクル(預言者)」と呼ばれるウォーレン・バフェットなのだ。その枯れが、あたりまえだけど一柳にはない。
「枯れが出ないとバフェットにならないぞ。わかるな」
「わかります。今のオレじゃとても無理だってことっす。
でも無理を承知で、少しでも枯れてみせましょう」
「もうひとつ。これが一番大事なことだ」僕は笑って言った。
「映像との呼吸は合ってる。でもおれたちの呼吸が合っていない。
お互いが一人プレイしている。いつものおれたちでいこうぜ」
「了解っす!」
「寺さん、すみません。もう一度、頭からお願いします」
「はいよ!」
(レコーディング中)
「はい、OK。いただきー!」寺さんの威勢のいい声。
「少し休むかい。それとも続けていくかい。学生さんのセリフ」
「続けてお願いします。さあ愛由美ちゃん、出番だ!」
防音ガラスの向こうのMAルームのソファに、三条玲子と並んで座って祈るように胸の前で手を組み、僕と一柳の吹き替えを見守っていた茂森愛由美は「はい!」と返事をして立ち上がった。
(レコーディング中)
学生のセリフはあまり流暢になってはいけない。現役女子大生の茂森愛由美は、そのへんのさじ加減を心得ていた。さっきのアナウンンサーしゃべりはどこにもなく、等身大のリアルな女子大生を演じた。
僕と一柳の学生役はどうだったか。年齢的にちょっとキツイんじゃないの? そう思われるかもしれないが、そんなことはない。僕たちはプロだ。いろんな声を持っている。
声だけじゃない。読者もすでにおわかりのように、僕たちはいまだ悩める青二才だ。三条玲子から"お子ちゃま"と断じられるほどの未熟者なのだ。その意味で、ゲイツやバフェットといった超大物よりよほど身の丈に合っていたかもしれない。
「はーい。オールOK。ぜーんぶ、いただきましたー!」
「ありがとうございます。寺さんもお疲れさまでした!」
すべての収録が終わり、僕たち5人はテーブルを囲んで談笑した。寺さんお待ちかねのスイーツタイムだ。
三条玲子は「みなさんは休んでいてください。私は何もしていないから」と、コーヒーの用意をしたり皿を並べたりケーキを切り分けたりと、甲斐甲斐しく立ち働いた。茂森愛由美も加勢した。
「寺さん、血糖値はだいじょうぶなんですか」と僕が訊くと、寺さんは「これは別腹さ」と意味不明なことを言って、麻布十番名物のチーズケーキと、茂森愛由美が買ってきた近所で評判のケーキ屋さんのショートケーキに貪りついた。
「そうそう、一柳くんも三条さんも聴いてなかったね。午前中にやった、語り人くんと茂森さんの吹き替え。もう神がかってるっていうかさ、鳥肌もんだよ」そう言いながら寺さんは、ロビーにある大きなスクリーンに再生した。
「すっごい。何だか愛を感じるわね。ふたりの師弟愛? それとも…」
三条玲子が映像を見ながらポツンと言った。茂森愛由美は赤くなって俯いた。
「今日の吹き替え、だれが一番ハマってたかって、やっぱ茂森さんだよね。びっくりした。語り人さん、短期間でよくここまで仕上げたっすね」
「彼女の才能と努力と素直さの勝利だ」一柳の感想に僕はひと言で答えた。
「台本も見ないで一度も噛まずにぴったりアテちゃうんだもん。おれもびっくりしたさ。今の女子大生の役なんか、またガラっと変わってさ。語り人くんと一柳くんと同じで、憑依体質なんだね。天才肌というかさ」寺さんがあらためて茂森愛由美を大絶賛した。
「いや、オレなんかダメっすよ。ぜんぜんバフッェトじゃなかったし、バフェットになれなかった。語り人さん、ほんとすみません」
そう言ってがっくりうなだれる一柳に、同じくがっくりうなだれて僕は言った。
「おまえに偉そうにダメ出ししちゃったけど、おれだって同じだ。ゲイツは今日、最後までおれの中に入ってきてくれなかった。愛由美ちゃんは気づいたはずだ」
「たしかに今日の先生は練習のときと違っていました。でもわたし、ずっと映像の顏だけを見ていたのですけど、本当にゲイツがしゃべってるって錯覚するほどでした。それは一柳さんのバフェットも同じです。やっぱりすごいです」
「私なんかが口を挟むことじゃないけど、茂森さんと同意見ね」三条玲子が言った。「途中から吹き替えということを忘れて、とにかくふたりの話に引き込まれたわ。ゲイツもバフェットも、ふつうに日本語をしゃべるんだって、そんな感じ。それは茂森さんもそうよ」
二人の心優しき女性はそう言ってフォローしてくれたが、一柳も僕も自分が一番よくわかっていた。
一柳は技巧派だ。確かにうまい。だがやっぱりミスキャストだった。彼はいま恋する少年だ。もっと年配の「枯れた演技」が難なくできる声優を、起用するべきだったのだ。
そして僕はといえば、当時のゲイツと同年代だし、彼のパーソナリティを表現することは特別むずかしくはない。僕はゲイツを完全に自分のものにしていたはずだ。でも本番で役に入りきれなかった。
理由はわかっている。本番前にいろいろありすぎて、僕は明らかに集中力を欠いていた。
午前中の茂森愛由美との収録で燃え尽きてしまったのかもしれない。そのあとの横浜散歩で心が揺れてしまったのかもしれない。そして、強烈な個性を放つ三条玲子の出現にうろたえてしまったのかもしれない。
言い訳はよそう。僕も一柳も腑抜けになってしまったのだ。心が乱れて演技に集中できないまま、それを口先のテクニックで補おうとした。それが「役を生きる」ことができなかった現因だ。
「まあ、そんなに落ち込まないで。語り人くんも一柳くんも、一度も合わせ稽古してないんだろう? それであれだけ呼吸が合ってんだもん。さすがだよ。これは二人にしかできなかったさ」今度は寺さんがフォローしてくれた。
「それです。合わせ稽古もしないで、ぶっつけ本番でこんな大物の吹き替えに挑むこと自体、大きな間違いだったんす。オレ、傲慢だったっす」
「いや、演出家としてのおれの責任だ」
そう言って僕たちがおのおの自責の念に打ちひしがれていると、三条玲子が急に立ち上がった。
「いい大人の男が二人して、いつまでぐじぐじ言ってるの! いいかげんになさい!」
三条玲子の声がスタジオ中に響き渡り、場の空気が一瞬にして凍りついた。
「あーはっはっはー!」一柳は再び盛大なごまかし笑いをした。
「あーはっはっはー!」僕もこのときばかりは一柳にならった。
「あーはっはっはー!」なぜか寺さんまで笑い出した。
「すんげえ! 三条さんに一本、だね!」
「あーはっはっはー!」最後は5人全員の本気笑い。
そう、笑いは伝染するのだ。
このとき僕は、一柳が三条玲子に惚れた理由がはっきりわかった。
大好きなケーキをお腹いっぱい食べてご満悦の寺さんが、急にモジモジしはじめた。そろそろあの件を切り出したいのだな、と僕は思った。
「ところで語り人くんさあ…」みんなが寺さんに注目した。
「あのさあ、茂森さんに訊いてもらえないかな…」
「ああ寺さん、茂森さんにフィギュアのモデルになってもらいたいんでしょ」一柳が寺さんの切なる願いを単刀直入に口にしてしまった。
僕は茂森愛由美に、そして何の話かさっぱりわからないだろう三条玲子に、寺さんの「美少女フィギュア」の栄光とその歴史について説明した。(なんでおれがプレゼンしなきゃならないんだ?)と頭の片隅で思いながら。
寺さんの聖域である「フィギュアコーナー」の上座にまします30体の美少女フィギュアを見て、三条玲子が驚嘆の声を上げた。
「すっごいリアル! 生きて呼吸してるみたい。もはや人形の域を超えてるわね」
「ピグマリオンが自ら彫った彫像に恋をして命を吹き込んだように、あるいは仏師が仏像に霊験を封じ込めるように、寺さんは自分が作ったフィギュアに、人格と感情と心を付与する能力を持ってるんだよ」と僕は言った。
「へえ、人格と感情と心ねえ。たしかに感じるわ。どれも上っ面だけの典型化された美少女じゃないもの。ところでピグマリオンってギリシャ神話よね。どんなお話だっけ」三条玲子は俄然、興味を持ったようだ。
「ピグマリオンはギリシャ神話に登場するキプロス王の若き日の名前だよ」
一柳が解説を引き受けてくれるらしい。
「一柳、ナレーション風に頼む」と僕は注文をつけた。
「了解。やってみるっす」と一柳は応え、鼻で息を吸って丹田に溜め込んでから静かに語り始めた。
「あることがあって女性不信に陥り、ずっと独身を通してきたピグマリオンは、彫刻の名手として知られていた。あるとき、美と愛の神ヴィーナスの姿をモチーフにして、自分の理想の女性像を彫った。
それはあまりに素晴らしい出来栄えで、ピグマリオンはその像に恋をしてしまう。そして、この乙女を妻に迎えたいと強く願うようになる。毎日毎日、像に話しかけ、寝食を忘れて磨き上げた。
これを見た女神ヴィーナスは、ピグマリオンの深い想いに心を打たれ願いを聞き入れる。彫像は生きた娘になり、そうして二人は結ばれたのである」
一柳が大きく息を吐き、エンディングを迎えた。
「はい、OK! いただき!」と僕は言った。
「すごい、すごいです!」と茂森愛由美は手をたたいて喜んだ。
「ふつうにピグマリオンのこと教えてくれればいいのに、まったくあなたたちときたら、どうしていつもそう大袈裟なの!」三条玲子は怒った顔をして憎まれ口を叩いたが、その目は潤んでいた。
そのとき寺さんが唸り声をあげた。寺さんにとってはピグマリオンの話などどうでもいいのだ。「で、あの…語り人くん、フィギュアの件だけど、どうかな…」
「寺さん、もう打ち解けたでしょ。本人に直接、訊いてみればいいじゃないすか」一柳がそう言うと、寺さんは恥かしそうに頭を掻いた。
茂森愛由美も黙ったまま、恥かしそうに俯いている。僕が代弁した。
「寺さん、愛由美ちゃんはね、アイドルとかそういうの苦手なんです」
彼女がフィギュアになってここに陳列されネットに上がれば、間違いなく話題になるだろう。もう3年、寺さんは美少女フィギュアを誕生させていない。そう、マニアたちは寺さんの新人美少女アイドルを待ちわびているのだ。
「いや、アイドルとかそういうのを、おれは作ってるわけじゃないよ。人気投票とかセンターとか神セブンとか、そんなことおれには興味ないし、頼んだ覚えもないさ。おれはただ、おれがビビッときた女の子の今の輝きを、そのまま写し取りたいだけなんだ」
わかっている。寺さんに他意はない。もしも寺さんが写真家だったら思わずシャッターを切っただろうし、画家だったら夢中で絵筆を走らせただろう。それだけのことだ。寺さんはそういう人なのだ。
「作ってください!」
茂森愛由美と僕が、ほぼ同時に口を開いた。驚いて僕たちは顔を見合わせて苦笑した。寺さんと一柳と三条玲子もびっくりして、次の言葉を待った。
「ただし」と僕が言った。「公開はしないでほしい」
「いいよ」と寺さんは迷わず即答した。「おれは作れればいいんだからさ。完成したら語り人くんに預ける。それでいいよね?」
「寺さん、すみません」僕は寺さんに頭を下げた。
「ちょっと待ってくださいよ、語り人さん」一柳が口を挟んだ。
「茂森さんはこれから声優としてやっていくんでしょ? だったら寺さんのフィギュアになることは、声優としてまたとないチャンスというか、大きな宣材になるんすよ。寺さんの美少女フィギュアにはそれだけの力がある。語り人さん、わかってますよね!」
「わかってるよ、そんなこと!」僕はムキになって返したが、一柳は負けじと冷静に状況を分析した。
「アイドルとかそういうのが苦手って、茂森さんは好むと好まざるとにかかわらずその路線でしょう? そろそろジュニアランクに上がるはずっす。そうすると事務所は、彼女をバンバン売り出しますよ。ほうっておくわけがない」
「それって、いわゆるアイドル声優ってこと?」三条玲子が訊いた。
「愛由美ちゃん、みんなに話してもいいかい?」
僕の問いかけに彼女はこくりと頷いた。
「半年前、事務所サイドからすでにその話は出てたんだ。でも彼女はそれを拒否した。自分はそういうことをやりたいんじゃないってね。そうしたら鼻で笑われたそうだ。演技もろくにできないくせにインテリぶるんじゃない。きゃあきゃあ言って笑ってりゃいいんだって」
大手声優事務所がアイドル声優として売り出してくれる。どれだけの新人がこのポジションを望んでいるだろう。席はほんのわずか。そのわずかな特等席を、茂森愛由美は自らの足で蹴ったのだ。
しかし業界の名誉のために言っておく。茂森愛由美に対する事務所のマネジメント方針は決して間違ってはいない。客観的にはしごく当然の判断だろう。彼女の主観がそれを許さなかっただけだ。
「ますます気に入ったわ。私も愛由美ちゃんと呼んでいいかしら?」
「おれも、そろそろいいかな?」
三条玲子と一柳がそう言うと、茂森愛由美はにっこり笑って返した。
「はい、よろこんで。わたしも、玲子さんと呼ばせていただいていいですか?」
「おれも、そろそろいいかな?」と一柳がまた言った。
そういえば一柳はずっと"三条さん"と呼んでいた。
「おまえも間のいいやつだ」と言って僕は一柳をからかった。
「先生、ありがとうございます。みなさんも、わたしのことで、いろいろ心配しておっしゃってくれて、ほんとわたし、うれしいやらお恥ずかしいやら…。そんなわけで、だからわたし、有無を言わせない実力をつけたくて、語り人先生にレッスンをお願いしたんです」
「アイドル路線じゃない正統派の声優としてスタートするために、だね?」
一柳はそう言ったあと、何かに気づいたようにハッとして僕の顏を見た。
「まさか、語り人さん…」
どうやら一柳は僕の計画に気づいたようだ。
「その話はあとにしよう」と僕は言った。
「さあ、記念撮影だよ。はい、みんなもっと寄って、寄って!」
寺さんが4人を撮って、それから僕と茂森愛由美、一柳と三条玲子のツーショットを撮った。
「寺さん、本当は愛由美ちゃんをピンで撮りたいんでしょう? 回りくどいことしなくていいっすよ」と一柳が言うと、みんなが笑った。
「寺田さん、どうぞ撮ってください」と茂森愛由美が笑顔で言った。
「ありがとう」と寺さんは言い訳するように言った。「いや、朝からずっと見てるから、茂森さんのあらゆる表情は頭に焼き付けてるんだけどさ、いちおう念のためにね」
「さあ、そろそろ行かないと、山田店長が待ってる。そうだ愛由美ちゃん、ひとり増えるって連絡入れといてくれるかな」写真撮影が終わると僕は言った。
「はい。すでに連絡ずみです」早い。さすが茂森愛由美だ。
「玲子さん、このあとも付き合ってくれますね?」
「もちろんよ。愛由美ちゃんのこともっと聞きたいし、一柳さんと語り人さんの事情聴取も残ってるわ」と三条玲子はサラリと応えた。
「じ、事情聴取って!」一柳と僕は同時に悲鳴を上げた。
「ところで語り人さん、山田店長って、まさかこれから四谷三丁目の焼鳥屋に行くって、そういう話じゃないっすよね?」一柳が疑問を呈した。
「そういう話だよ」だからどうした?という感じで僕は言った。
「えっ、寿司でも焼肉でもオレの好きなもの何でも食っていいって、そう言ったじゃないすか!」
「山田店長が愛由美ちゃんのデビュー祝いをしてくれる。個室をキープして待ってくれているんだ」
「じゃあ寿司は? 焼肉は?」一柳が不満の声を上げた。
「いやなら、おまえはこなくていい」僕は一柳を見捨てた。
茂森愛由美が声を上げて笑いながら言った。
「店長がお寿司を用意してくれるそうです」
「ヤッホー! 寿司だ、寿司だ、寿司だぁ!」一柳ははしゃいだ。
玲子さんが軽蔑の目を向けると、一柳はおとなしくなった。
寺さんに挨拶をしてスタジオを出ると、日はすでに落ちていた。
四谷三丁目に行くため、JR桜木町駅を超えて地下鉄みなとみらい駅に向かった。
昼間は上から見おろした横浜コスモワールドの大観覧車を、地上から見上げるポイントに僕たちは来ていた。そのとき咄嗟に僕は思いついた。
「なあ、みんな。観覧車に乗らないか」
「わあ、語り人さん、グッドアイデアっす! 乗ります、乗ります!」
一柳が歓声を上げた。
三条玲子が呆れ顔で一柳を見た。
茂森愛由美が潤んだ瞳で僕を見た。
平日の夕方6時前で、なんとか待たずに乗れそうだった。
定員8名のゴンドラ。僕は4人一緒に乗るものだと思っていたが、一柳が猛反対した。
「語り人さん、何を無粋なこと言ってるんすか。これは想い合う二人のための乗り物っすよ」
「じゃあ、あななたち二人で乗ればいいわ」と三条玲子は一柳と僕に向かって言った。
「いやだなあ玲子さんたら、心にもないことを言わないで」
そう言って一柳は三条玲子の手を取って、先にさっさと乗り込んだ。
「グッドラック!」と言って僕と茂森愛由美にウインクを決めながら。
二人を乗せたゴンドラを見送って、次のゴンドラに茂森愛由美と乗り込むやいなや、目に閃光が走った。60体あるゴンドラおよび支柱が一斉にライトアップされたのだ。
横浜の町を鮮やかに彩るこの日本最大級の観覧車「コスモロック21」は、季節によりライトの色が変わる。春はグリーン、夏はブルー、冬はピンク、そして秋はゴールドだ。
全身が煌めく金色に包まれた。
茂森愛由美が甘えるように身体を寄せてきた。
「先生、わたし、うれしい。また、願いをかなえてくれて」
「じゃあ、僕の願いもかなえてくれるかな」と僕は言った。
茂森愛由美があの目で僕をまっすぐ見据えて言った。
「先生の願い? わたし、何でもききます。おっしゃるとおりに」
金色のライトのせいか、いつも以上に輝きを放つ彼女の目が眩しくて、
その目が閉じられる前に、僕は言い訳をするように顔をそらし隣のゴンドラに視線を移した。
一柳が三条玲子の肩を抱き、ふたり並んで同じ方向を見ていた。
ベイブリッジの方向だ。
「愛の架け橋か…。よかったな、一柳」と僕は呟いた。
ゴンドラが半周して頂上に達した。地上112.5メートル。
観覧車の全長としては世界で5番目だと聞いたことがある。
宝石を散りばめたような美しさといわれる横浜の夜景が
視界いっぱいに広がった。
言わなければ。今だ。今、言うんだ!
僕は大きく息を吸った。
(次回、最終章につづく)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 「親の顔が見たい」とよく言うが、その人を知りたければ友達の顏を見るほうが早いだろう。親もパートナーも恋人も知らない秘密を友達が知っていたりする。
- 「率直さ」とは誰に対しても言動や態度や意見が変わらないことだ。ぶれない同じ自分でいること。人によって自分を使い分けるのは役者の仕事だ。
- 誰かのために変わろうとすること。自分のために変わろうとすること。
きっかけや理由は何でもいい。チェンジ(CHANGE)のGをCに変えるだけでチャンス(CHANCE)になる。 - 何であれ何かをやり遂げてしまう人は、素直さと頑固さを併せ持った人だ。素直なだけでは流されやすく、頑固なだけでは真実が見えなくなる。素直さと頑固さは矛盾しない。共存できるはず。「素直頑固」な人になれ。
- 人生は多かれ少なかれ人との出会いで決まる。今いる場所で決まる。誰と一緒にいるかで決まる。だったら自分で決めればいい。何処にいたいか。誰といたいか。何をしていたいか。もっとも必要な力は「自ら決める力」だ。