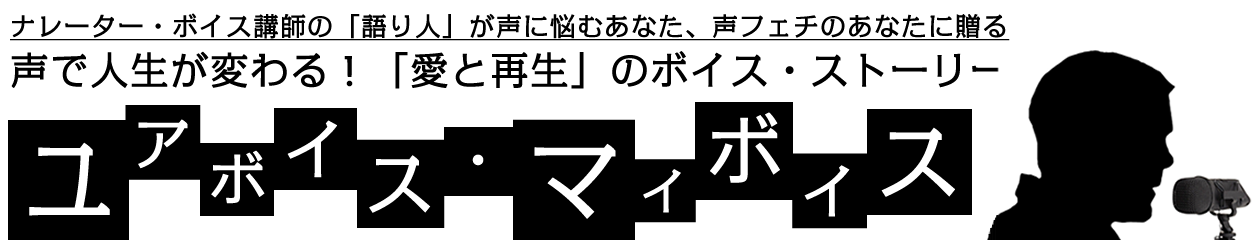翻訳が完成したら、あとはひたすら読み込みだ。レッスンで、映像を流しながら実際に声をあてていく練習を何度も繰り返した。勘がいいうえに努力家の彼女は、みるみる役をものにしていった。そのようにして、僕たちは収録の日を迎えた。茂森愛由美にとっては記念すべき声優デビューの日を。
(5章「一流の条件」のつづき)
「じゃあ寺さん、準備をお願いします。僕たちは声を作ってますから」
声を作るとは発声練習のこと。自宅で軽めの声出しはすませているが、ここで声量を上げた本格的な発声をおこなう。寺さんのスタジオでは気兼ねなくできるからとても助かっている。
「はいよ! Cスタでやるといいさ」寺さんが言った。
僕は茂森愛由美を目で促した。
15分程度の発声を終えてCスタジオを出ると、ロビーのテーブルにコーヒーがふたつ用意されていた。淹れたてみたいだ。今日はとりわけサービス満点の寺さんだ。
「寺さん、ありがとう」「ありがとうございます。ご馳走になります」
僕たちはそれぞれ、MA室で最終チェックをしている寺さんに声をかけた。
「あと5分、くつろいで待っててよ」と声が返ってきた。
本番を前にして茂森愛由美は明らかに緊張していた。無理もない。
「くつろぐどころじゃないよね。じゃあ、あれをやろう」
軽く目を閉じて、丹田を意識してゆっくり口から(15数えながら)吐いて、鼻で(3数えながら)吸う。丹田呼吸法だ。意識を丹田に持っていき呼吸を数えることで、雑念が取り払われ気持ちが落ち着いてくる、れっきとした瞑想法だ。
「お待たせ、スタンバイOK!」
寺さんの声を合図に僕たちは目を開け、互いの顔を見合わせた。
瞑想のあとの茂森愛由美の表情には、緊張とは無縁の静謐で純粋な美しさが宿っていた。なんの憂いもない、企みもない、媚びもない。ひと言でいうなら、それは人を感動させる美しさだった。
もしも今、たとえばルノアールがここにいたら、彼女をモデルに夢中で筆を走らせたに違いない。絵のタイトルは「微睡みから目覚めた少女」。
そして我らが寺さんも、本当はレコーディングなんかうっちゃって、今すぐフィギュア制作に取りかかりたいに違いない。タイトルは「No.31茂森愛由美」。
「さあ、楽しいお芝居の時間だ」
そう言って僕は立ち上がり茂森愛由美にエールを送った。
「君はやるべきことはやった。あとは楽しめばいい」
広めのレコーディングブースの中央に置かれたテーブルの上に、二人分のマイクとモニター画面が向かい合っている。インタビュアー(インタビューする人)とインタビュイー(インタビューされる人)同様、向かい合う設定だ。
「レベルの調整をするんで、まず茂森さんから声をください」
寺さんの声がヘッドフォンから飛び込んできた。
「頭から本番と同じ調子で、ストップがかかるまで読むように」
僕は茂森愛由美にそう指示した。
「はい、OKでーす」と寺さんの声。僕も指でOKサインを作って言った。
「いいよ。その調子だ」茂森愛由美はほっとしたように笑顔を返してきた。
僕のレベルチェックも終わり、さあ、いよいよ本番だ。
モニター画面に映像が流れる。
番組はアナウンンサーのMCから始まる。
5秒のオープニングBGM。
茂森愛由美は目を閉じた。
長いまつ毛が音を立てる。鳥が止まり木で羽を休めるように。
そして再びまつ毛が音を立てる。鳥が羽を広げ飛び立ったのだ。
茂森愛由美は目を開いた。
(レコーディング中)
「はい、オールOK! いただきましたー!」
寺さんの声が終わりを告げた。そして驚きの声をあげた。
「すっごいね。一度も止めなかったよ!」
そうなのだ。僕たちは最初から最後まで一度も噛むことなく、一度も読み違えることなくノンストップで、このしゃべりっぱなしの30分番組の吹き替え収録を終えたのだ。
僕はヘッドフォンをはずし椅子から立ち上がり、右手の親指を立てて茂森愛由美の健闘を称えた。
茫然自失といった様子の彼女は慌ててヘッドフォンをはずし、椅子を倒す勢いで立ち上がると、いきなり僕に飛びついてきた。そして今度は声を上げて泣き出した。子どもみたいに。
茂森愛由美の背中をさすったり、頭をなでたりしながら僕は言った。
「よくがんばった。上手だった。でも仕事はまだ終わってないぞ。声が変わっちゃうから泣くな。次の大学生の役に、色っぽい鼻声はいらないよ」
「はい。すみません」と言いながら彼女は、抱きつかれた体勢のまま僕が箱から鷲掴みして渡した数枚のティッシュで目と鼻を押さえた。
寺さんがその様子をニヤニヤしながら見ていた。寺さんがいるMAルームの前面はガラス張りになっていて、ブース内が丸見えなのだ。
「ほら、寺さんが見てるよ」と言うと、茂森愛由美はハッとして体を離し、ガラス越しに寺さんに向かって「見苦しいところをお見せして申し訳ありません」と言って、顔を真っ赤にしてお辞儀をした。
といっても、マイクを通さないとMAルームにいる寺さんには聞こえないのだが。
レコーディングブースを出ると、寺さんが僕たちを待ち構えていた。
「二人の息がぴったり合っててさ、すっごいリアルだったよ」と寺さんは言った。「茂森さん、初めてって言ってたけど、すっごいね! それに、おれ思ったんだけどさ、茂森さん、台本をほとんど見てなかったよね。まさか、暗記してたって話?」
「そう、丸暗記。翻訳も彼女がしたんです」
寺さんは茂森愛由美を見ずに僕を見てしゃべったので、僕が答えた。
「ひえー、そんな声優さん、おれ、はじめて見たさ!」
寺さんもいろんな声優の収録に立ち会っている。短いセリフならともかく、これだけの長文を一度も噛まずに読み、しかも台本なしでのぞむ声優は見たことがないと驚いたのだ。
翻訳までしてしまう声優もいないと思うのだけど、それはまあ僕がそうだからあえて言及しなかったのだろう。
暗記に関しては、実は僕も驚いた。何度もふたりで合わせ練習をしたわけだけど、何度目かで完全に頭に入っていた。暗記したのかと訊くと、読んでいるうちに自然に覚えたという。なるほど、優等生は記憶力にも優れている。
寺さんは早速、編集と整音の作業に入った。
「ノンストップでいけたので作業は楽ちんさ」と寺さんは喜んだ。
僕たちもMAルームにお邪魔して、映像に同期させた吹き替え音声をひととおり確認した。
「わたし、こんな声なんですね。なんか変です」茂森愛由美が言った。
「最初はびっくりするよね。そのうち慣れるよ」と僕は言った。
「艶っぽくていい声だよね。おれ、好きだなあ」と寺さんは言った。
時間はお昼12時を回ったばかり。予定よりずいぶん早く終わった。
「あっ、そうそう、カツ丼の出前、頼んどいたよ。そろそろ届くころ。今日が愛弟子のデビューだから景気づけにって、語り人くんが」
後半は茂森愛由美をチラッと見て寺さんは言った。
そんなことを言っているうちに出前が到着した。カツ丼が2つしかないのを見て、茂森愛由美は首を傾げた。
「寺さんは愛妻弁当なんだって」僕が代弁した。
「そうなんだ。血糖値とかコレステロール値とか、いろいろ問題があってさ。だから女房に管理されてるんだ。三食、精進料理だよ」と寺さんは苦笑しながら言った。「だからおれのことは気にしないで。二人はしっかり腹にためなきゃ。語り人くんの口癖…」
「声優は腹でしゃべる」茂森愛由美が引き取って笑った。
昼食を終えるとまだ1時前だった。次の録りまで1時間ちょっと。一柳が15分前に入るとしても、まだ1時間ある。食後は軽い散歩を日課とする僕は、茂森愛由美に言った。
「僕はこの辺を少しぶらぶらしてくるけど、君はここでゆっくりしていればいい」
すると茂森愛由美は、自分も歩きたい。わたしが一緒だと邪魔かと訊いた。僕は邪魔じゃないと答えた。
外に出ると、太陽はまだ一番高いところにあった。「今日は暑さが戻るでしょう」と天気予報の女の子が棒読み口調で断言していたが、それほどでもない。季節はもう秋なのだ。
横浜桜木町駅の地下道をみなとみらい方向に歩いていると、いきなり茂森愛由美が叫んだ。
「邪魔なんかじゃない!」
「いったいどうしたんだ?」と訊ねると、彼女はうれしそうに言った。
「今も言ってくださいましたけど、あのとき、半年前、先生がおっしゃったんです。わたしが"おじゃましました"って言ったとき」
「ああ、そうだった。一柳とデカい声でハモっちゃったんだ」
「わたし、びっくりしたけど、あんなにうれしかったことはないの」
「えっ、なにそれ?」
「あんなに本気でかまってもらったことがなかったというか。カチカチ山のお話とかして、本当に楽しかった。うまくいえないけど、とにかく顔がカーって熱くなって、胸がドキドキして…。あのあと裏でわんわん泣いちゃいました。そしたらバイトの吉岡君がね、どうしたの? あの客にいじめられたの?って言うの。違うわよ、ハートを射抜かれたのよ、って言ったらキョトンとしてた」
「泣き虫だね。強いくせに。空手二段」とからかうように僕は言った。
「違います。先生と出会ってから泣き虫になったんです」と茂森愛由美は口を尖らせてから頬を膨らませた。
「えっ、僕のせい?」
「そうです。だって、二番目にうれしかったのは手書きのお名刺をいただいたときだし、三番目はびっくりするくらい心のこもったお手紙をいただいたときだし、四番目は先生のお夕食を作って、おいしいって食べてくださったときだし、五番目はこのお仕事をいただいたときだし、六番目はさっき収録が終わって頭をなでてもらったときだし、七番目はいま…」
「もうわかったよ」めずらしく饒舌な茂森愛由美の口を僕は塞いだ。
「要するに、わたしが泣いたのは、ぜんぶ、先生がらみだってことです。だから、先生が、わたしを、泣き虫にしたんです」
「じゃあ何度も言ってるけど、その"先生"っていうのやめてくれるかな。生徒を泣かせてばかりじゃ、先生とはいえない」
僕は苦手とすることが結構多い人間で、先生と呼ばれることもそのひとつだ。ほかにもカラオケボックスとか、喫茶ルノアールとか、サラリーマンがたむろする新橋あたりの居酒屋とか、終電から始発までの新宿歌舞伎町とか。(あれ、場所ばっかりだ)
「いやです。この際ですからはっきり言わせていただきます」
茂森愛由美は立ち止まり、まっすぐな目で僕を見て言った。この目に僕は弱い。
「わたしの言う先生とは、学校の教師とか、お医者さまとか、弁護士さんとか、議員さんとかの先生じゃないんです。わたしが尊敬し、心からお慕いしている方への敬称です。ですから」ここで一区切り入れて、茂森愛由美は恥らいがちに続けた。
「ですからわたしは、先生の生徒ではありません。生徒ではありませんから、卒業もありません」
「茂森愛由美、君は今日、いささかおしゃべりが過ぎるようだ。楽しい演技の時間をまだ引きずっていて興奮状態にあるのはわかるけど、そのくらいにしておこう」
「興奮状態にあるのは認めます。でも浮かれて言っているんじゃありません。本当の気持ちを申し上げました」
「わかったよ。でも卒業はしてもらう。この先ずっとレッスンを続けるわけにいかないからね。ご両親に約束した期限は2年。だから僕のレッスンは残すところ半年だ」
「わたしが言ったのは、レッスンの卒業じゃありません」
茂森愛由美は俯くと、聞こえるか聞こえないかの小さな声で言った。
聞こえなかったほうを僕は選択した。
コロンビア大学ビジネス・スクール教授のシーナ・アイエンガー博士の調査によると、人は一日、朝起きてから夜眠りにつくまでの間に、平均で70回の選択を行うという。僕自身はもっと多いような気がする。やれやれ。
いつのまにかランドマークタワーにきていた。地上70階の文字どおり横浜のランドマーク(目印)だ。眼下には横浜コスモワールドの大観覧車が、その向こうに横浜港が一望できるビューポイントに僕たちはいた。
「先生、わたし、あの観覧車に乗りたい。先生と」
「ああ、次に何かうれしいことがあったら乗ろう」
「じゃあ、すぐですよ。先生といるとうれしいことばかりですから」
「おっといけない」僕はまた聞こえないふりを選択した。
「もう戻らないと。一柳が先に着いてしまう」
ランドマークタワーの3階、オシャレなショップの並ぶランドマークプラザを出ると、そこから桜木町駅に直結する「動く歩道」がある。けっこうな距離があって、乗ったまま左右に横浜の景観を楽しむことができる。
茂森愛由美が突然、腕をからませてきた。動く歩道が少し苦手なのだという。僕はこういう展開が苦手なのだ、と言おうしてやめた。今日は、今日だけは彼女のしたいようにさせてあげようと思った。
さっきから気づいていたことだが、彼女とふたりでいると擦れ違う人の視線が気になる。10人中8人が目をとめるのだ。茂森愛由美に対する好意的、ないし称賛の視線もあるが、好奇な視線、不躾な視線、嫉妬の視線も散見される。
人々はまずハッとした顔で茂森愛由美を見る。次に僕を見て「?」という顔をする。たぶん「どういう関係?」って訊きたいのだろう。「親子じゃないよね?」という疑問符かもしれない。
ふだん彼女は極力目立たないように、とても地味な格好をしている。Tシャツにジーンズとか、ポロシャツにジャージといった組み合わせだ。外ではほとんどスカートをはかない。靴はもちろんスニーカー。
髪はまっすぐなロングだが、いつも後ろでひっつめている。ときどきキャップをかぶり、黒縁のメガネをかける。メイクはほとんどしない。装身具もつけない。レッスンの日だけ髪をおろし、少しだけ薄化粧をする。
それが今日はしっかりメイクをし、髪は毛先を遊ばせた緩やかな巻き髪にしている。服装は上品なオトナかわいい系のミニのワンピース。さらに、いくつかの小さなダイヤをあしらったネックレスが、さりげなく胸元を飾っている。
いつもは、どちらかといえば美少年という感じで、異性を意識させることはあまりないのだが、こんな格好をするとあらためて「なんてきれいな女の子だろう」とドギマギしてしまう。
ふつうの21歳の女の子なら、いつも可愛い服を着てお出かけしたい年頃だろう。オシャレをして彼氏とデートして、友だちとランチをして、大学のサークルメンバーで飲み会をしたり、旅行の計画を立てたりしているはずだ。
そのとき僕は、そんなこととは無縁の生活を送っている茂森愛由美が無性にけなげに思えて、抱きしめたくなった。抱きしめる代わりに、組んでいる腕に力を込めた。
動く歩道を降りると3階からいっきに下る、これまた長いエスカレーターに乗る。地上に降りても茂森愛由美は組んだ腕を離そうとしなかった。
JR桜木町駅にさしかかると、改札を出たところに見覚えのある男の姿があった。見間違えようがない。一柳だった。
ナイスなタイミング。茂森愛由美がやっと腕を離したので駆け寄ろうとして、すぐに思い直した。一柳が改札のむこう側に手を振ったからだ。どうやら、だれかと待ち合わせをしているらしい。
様子を覗っていると、一柳が手を振った相手は、あたりまえだけど女性だった。遠目からでも目立つ、ある種のオーラを放つ女性だ。
一柳のよく通る声が聞こえた。「遠いところまでありがとう」。
女性が笑みを返した。満面の笑みではない。少し困惑している笑み。
20代後半に見える。でも実年齢は30代中盤といったところか。
次元の違う美人というか、化粧品のCMに出てくるモデルのような女性だ。メイクのせいもあるだろうけど、目ヂカラがあるというか挑戦的な眼差しをしている。「男には負けないわよ」といったような。
あの女性だ! と僕の直感が告げた。一柳を改心させた女性。数々の浮名を流してきた百戦錬磨のモテ男が、はじめて自分から惚れた女性。
僕たちは5メートルほど後方から見ていたのだけど、そのとき突然、一柳が振り向いたので目が合ってしまった。
一柳は少し驚いた表情を見せたが、横にいる茂森愛由美の存在に気づくと、さらに驚いた顔をした。
「おやおや」と一柳は言った。
「おやおや」と負けずに僕も返した。
(次章につづく)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 疲れたとき、緊張しそうなとき、心がざわつくとき、むしゃくしゃするとき、丹田瞑想をお勧めする。スーッと気持ちが静まり、心が落ち着くのを実感するだろう。
- 「やるべきことはやった」と本当に言えるのか。いつも自問することが大切だ。
- 「苦手」という言葉はあまり使わないほうがいいが、使うなら自信を持って言おう。反対に「得意」という言葉は控えめに言おう。
- 世の中には「先生」が多すぎる。先に生まれたから先生というわけじゃない。できないことを教えてくれて、導いてくれて、眼を開かせてくれる人。年齢に関係なく、そういう人を先生と呼びたい。
- 「人は一日に2万回もの選択をおこなっている」という説もある。70回説と2万回説の違いは、基準をどこに置くかという定義の問題だ。数字は数字でしかない。傾注すべきはその選択をおこなった結果だ。
- 仕事が先かデートが先か。一柳と語り人は、いったいどこに向かおうとしているのか。それは僕にもわからない。やれやれだ。