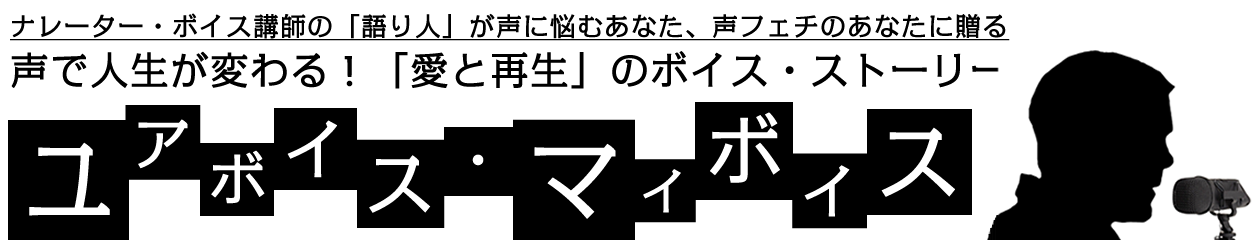「ところで、一柳さんと玲子さんの馴れ初めをまだ伺っていませんよね」
茂森愛由美が興味津々といった様子で口火を切った。
「あっ、一柳がなんで金持ちになるって喚き出したのかも聞いてないぞ」
半年前に持ち上がった、一柳の「金持ち宣言」を僕は思い出した。
「待って」玲子さんが遮った。「一柳さんが役者の夢破れて実家に帰ってから、10年の歳月を経て再び上京し、ナレーターになった経緯をまだ聞いていないわよ」
(最終章「一流の証明(後編)」のつづき)
グラスに半分ほどあったビールを勢いよく喉に流し込んでから、一柳は話し始めた。
「放心状態で演劇学校を後にしたオレの足は、自然ともうひとつの懐かしい場所に向かっていた」
そこはすぐ近くの公園。在学当時、一柳が発声練習やセリフ読み、ダンスの振り付けのおさらいをしていた西池袋公園。台本読みの練習相手に、僕はよく付き合わされものだった。
「園内に入るとトランペットの音が聴こえた。エルガーの『威風堂々』の主旋律。まさか、と思った。だって、二年前と同じだったから。音の鳴るほうへ行ってみると、間違いない、あのラッパ吹きだ」
「そいつは今も、二年前と同じ場所で同じ曲を、同じ直立不動の姿勢で演奏していた。オレはデジャヴかと思った。でもそうじゃない。ひとつだけ、二年前とは明らかに違っていた。音だ。その音はなんていうか、芸術が芸術であるための表現領域に苦もなく入っていた。つまり彼の演奏は格段にうまくなっていたんだ」
「彼のトランペットを聴きながら、オレは涙が止まらなかった。自分の二年間が、ひどく薄汚れたものに思えた。オレはいったい何をしてきたのか」
「『威風堂々』の第一楽章が終わると、演奏を称える拍手の音がした。見ると、10メートルほど離れた滑り台の上に誰かがいた。そう、語り人さんだった。ラッパ吹きは拍手に応えて恭しくお辞儀をした」
「スーツ姿なのに構わずお尻で滑り降りると、語り人さんはラッパ吹きのもとに駆け寄り賛辞を贈った」
『久しぶりに聴かせてもらったけど、素晴らしい演奏だった。この曲の持つ荘厳な勇ましさを見事に表現していたね。胸が熱くなったよ。本当にありがとう!』
「そう言うと語り人さんは、からだをオレのほうに向けて両手を差し出した。『この曲はあなたに捧げました』というように」
「オレは慌ててベンチから立ち上がり拍手をした。ラッパ吹きは、今度はオレに向けて恭しくお辞儀をした。そしてステージで演奏を終えたソリストがそうするように、その場から立ち去った」
「先生が、そのラッパ吹きさんを連れてこられたのですね。そしてそれは、一柳さんを励ますために先生が仕組まれた演出だったのですね!」
茂森愛由美が正解を出した。
「そのとおり。語り人さんは会社を早退して、オレのためにそんな手の込んだパフォーマンスを演出してくれたんだ。ラッパ吹きまで動員してね」
「あ、ラッパ吹きなんて言っちゃいけないな。当時みんなからラッパさんって呼ばれてたんだけど、彼は今や、日本の大手フィルハーモニー管弦楽団の第一トランペット奏者だ。むかし公園で毎日のように顔を合わせていたけど、ほとんどしゃべったことはなかった。お互い自分の練習に必死だったからね。語り人さんはラッパさんと親しかったんだ」
「そのあとあなたは、語り人さんの胸でさめざめと泣き崩れたんでしょ」
「なんでわかるの? 玲子さん、まさか見てたの?」
「そのとき私は小学6年生だから、まあ公園にいても不思議はないけど、残念ながら池袋にはいなかったわ。ていうか、もうあなたの行動パターンは把握ずみよ」
一柳は小さく笑ってから続けた。
「30分は泣いてたと思う。なんでこんなに泣けるんだろう。なんでこんなにあとからあとから涙が出てくるんだろうって、自分でもびっくりした。そのあいだ語り人さんは、何も言わず黙ったままオレの肩を抱いてくれてた」
「そうして30分、泣き疲れて顔を上げると、語り人さんは口を真一文字に結んで虚空を睨みつけていた。目が真っ赤だった。そうなんだ。語り人さんは声をあげずに泣いていたんだと、そのときわかった」
「マジで言っちゃうけど、その日、演劇学校の校長から最後通告を言い渡されて、ああオレはもう役者には戻れないんだってわかったとき、じゃあ生きててもしょうがない、死んじゃおうって思ったんだよね」
「そこへ『威風堂々』を勇ましく吹き鳴らすラッパさんがいて、語り人さんが颯爽と登場してきて、語り人さんの胸で思う存分泣いて、そしたら死神はどこかへ行っちゃってた」
「オレが泣き止んだのがわかると、語り人さんはすっくと立ち上がり、はじめてオレに声をかけた。『一柳、今日は死ぬほど飲むぞ!』」
「それからママの店に行って、オレたちは暴れに暴れた。いや、喧嘩じゃないよ。客たちから代わるがわるお題を頂戴して即興の寸劇をやりまくったんだ。10本くらいやったんじゃないかな。大ウケでしたね、語り人さん」
「ああ、おまえは神がかってたよ。おれは必死にくらいついていった」
「オレの最後の舞台だと思ってやりましたから。喧嘩と言えば、ねえ語り人さん、覚えてます? "もしもこの二人が喧嘩したら"ってやつ。いろんなお題が出てきましたね」
「ああ。ゲーテとベートーヴェン、モーツアルトとサリエリ、それから太宰治と三島由紀夫、中原中也と小林秀夫、ゴッホとゴーギャン、クリムトとエゴンシーレ」
「キリストと釈迦もありましたよ。これは名作だと絶賛された。ローマ法王とダライラマも。でもいちばんウケたのは、浅利慶太と蜷川幸雄でしたね」
「あれは気合が入ったな。最後は取っ組み合いの喧嘩になった」
「本物が乗り移ったみたいだと言われましたっけ」
「わたし、聞きたいです」
「えっ、浅利慶太と蜷川幸雄?」
「いえ、それは大変なことになりそうなのでやめておきます。名作と絶賛されたキリストと釈迦なんかいかがでしょうか」
「いい加減にしなさい、あなたたち。今は寸劇の時間ではありません!」
玲子さんはなぜか寸劇はお気に召さないようだ。
「アーメン」と僕は十字を切った。
「南無阿弥陀仏」と一柳はマントラを唱えた。
「なんて不謹慎なの!ばちが当たるわよ」玲子さんは意外に生真面目だ。
「汝、我らの罪を許し給え」僕はふたたび十字を切って言った。
「天上天下唯我独尊」一柳は右手を天に、左手を地に指して言った。
玲子さんは深い溜息を吐き、茂森愛由美は口を押えて笑いを堪えた。
店を出るとき、ママはやはり勘定を受け取らなかった。
『もうおれたちは社会人だよ』と僕が言うと、『飲み代は今日の出演料でいいわよ。それより一柳くんのこと、しっかりケアしてあげなさい』とママは言った。
それから池袋駅に行って山手線に乗った。僕たちはもう学生ではなかったし、池袋の住人でもなかった。当時、一柳は劇団の所在地である横浜のあざみ野に、僕は都内の三鷹に住んでいた。
「新宿で電車を降りる間際に語り人さんが言ったことは今でも忘れない」
「先生はなんておっしゃったのですか?」
「『一柳、三鷹に引っ越してこい。それから、おまえは声優になれ。明日からその準備にかかるんだ。いいな』そう言い残して、渋谷まで乗るオレを置いて電車を降りてった。うれしかった。一瞬にして目の前が晴れた気がした」
「ここで"声優"が出てくるわけだ。それでまた語り人さんを追っかけて、今度は三鷹に引っ越すのね」
「いや、結局オレは三鷹に引っ越すことはなかったし、声優にもならなかった」
「つまり、このタイミングで実家に帰ったの? 何か事情があったのね」
「そう。このタイミングで実家の母から連絡が入った。親父の体に癌が見つかったと。胃癌だった」
一柳の父親は、静岡の駅前に中規模のビジネスホテルを所有する経営者だった。長男の一柳は当然"跡継ぎ"と考えられていたが、それに逆らって一柳は役者の道に進んだのだ。
一柳には歳の離れた弟がいて、当時まだ中学三年生だった。父親はまだ50歳そこそこだったし、一柳は弟に将来、ホテル経営を継いでもらうつもりでいた。
「なんてタイミングだろうって…。でも潮時だと思った。オレの命運もここまでだって」
「そういうことだったのね…」玲子さん感慨深げに言った。
「声優として再起をかけようとした矢先に…。さぞ無念だったことでしょう」茂森愛由美は一柳の心情を慮った。
「静岡に帰る前日、語り人さんはオレのために新宿の高層ホテルに部屋を取ってくれたんだ。39階の見事な夜景が拝めるゴージャスな部屋。静岡のうちのホテルの、きっと10倍の値段はする部屋だろう。そして展望レストランの窓際の席でディナーをご馳走してくれた」
「せっかくの夜景が、目が霞んで見えなかったさ。オレはずっとボロボロ泣きながら食べてたし、何を食べたのかも覚えてない。泣くか食うかどっちかにしろって、語り人さんに叱られたよ」
「部屋に戻って、語り人さんが用意してくれたシャンパンをあけた。舞台俳優にもダンサーにもなれなくて、そして声優にさえなれない自分が悔しくて情けなくて、やっぱり泣きながら飲んだ。いやそれ以上に、語り人さんと別れるのがつらかった」
「語り人さんはきっと、そんなオレを見てるのがたまらなかったんだろう。ずっと窓際に立って夜景を眺めていた」
「先生も、泣いていらっしゃったんだと思います」と茂森愛由美も泣きながら言った。
「ああ、そうだね。だから語り人さんはオレに背を向けたままこう言った」
『静岡なんて目と鼻の先だ。いつでも会える。おれが会いに行く。おいホテル屋、部屋はいくらでもあるんだろう?』
『最上階の一番いい部屋をご用意しますよ。といっても7階ですけどね』
「そう答えると、語り人さんは底抜けに明るい声で笑った。そして『いいか一柳、忘れるな』そう言って、オレに言葉を贈ってくれたんだ」
そのときの僕がそうしたように一柳は窓際へ移動し、みんなに背を向けて朗誦した。
もしもおまえが
よくきいてくれ
ひとりのやさしい娘をおもうようになるそのとき
おまえに無数の影と光の像があらわれる
おまえはそれを音にするのだ
みんなが町で暮らしたり
一日遊んでいるときに
おまえはひとりであの石原の草を刈る
そのさびしさでおまえは音をつくるのだ
多くの侮辱や困窮の
それらを噛んで歌うのだ
「宮沢賢治の『告別』ですね 。わたしの大好きな詩です!」
茂森愛由美が感極まってそう言うと、一柳は振り返りにっこり笑って彼女に続きを促した。しかし、この感受性の豊かすぎる女の子はとても朗誦できる状態ではなかった。首を振って「先生のが聞きたいです」と涙声で僕に懇願した。
20年前の情景がありありと蘇った。あの日と同じように、だけど今日は茂森愛由美に向けて、僕は言葉を紡いだ。
もしも楽器がなかったら
いいかおまえはおれの弟子なのだ
ちからのかぎり
そらいっぱいの
光でできたパイプオルガンを弾くがいい
茂森愛由美は、この詩が自分に向けられたことを感じ取りわんわん泣いた。
一柳は、当時の心情そのままに酒をあおりぼろぼろ泣いた。
玲子さんは、そんな一柳に寄り添いさめざめ泣いた。
一柳が実家に帰って三か月後、父親は息を引き取った。52歳の若さゆえ癌の転移も早かったのだろう、自分の死期を知っていたかのように、父親は一柳に経営者としてすべきことを残らず叩き込んだ。
「告別式に語り人さんは来てくれた。そのとき語り人さんは、中学三年生の弟にあるお願いをしたらしい。オレがそれを知ったのはずっとあとのこと。弟が大学を卒業するちょっと前、弟の口から聞かされた。なんだと思う?」
「大学を出たら君が会社を継ぎなさい。そしてお兄さんを僕に返してくれ。先生はそうおっしゃったのではないでしょうか」
「さすが愛由美ちゃん、語り人さんのことよくわかってるね」
「お兄さんを返してくれとまでは言わなかったみたいだけど、はっきりとこう言ったそうだ。お兄さんにもう一度、役者をやらせてあげてくれって」
「愛由美ちゃん、大正解よ。それって、お兄さんを僕に返してくれっていうのと同義だもの。それで10年後に、弟さんにバトンタッチしたのね」
「まあ、結果的にはそうなったけど、すんなりと事が運んだわけじゃないんだ」
「弟さんがやっぱり継ぐのはイヤだと言い出したの?」と玲子さん。
「いや、弟は『語り人さんと約束したんだ。早く行け』って言ってくれていたんだけど、問題はオレ自身だった」
「何? 今度は何の問題?」
社長に就任して7年後に一柳は、近隣の採算の上がらない10階建てのシティホテルを買い取り、そこをわずか1年で軌道に乗せる経営手腕を見せた。つまり一柳は、ふたつのホテルを所有する実業家になったのだ。
「ホテル経営の仕事が面白くなったのね」玲子さんの目が光った。
「まあ、簡単に言うとそういうことだね。役者に戻る自信もなかったし」
「その頃はどんな目標があったの?」玲子さんはさりげなく訊いた。
「39階建てのホテルを建てて、最上階に語り人さんを招待する」
「東京での最後の夜、新宿の高層ホテルの39階に、語り人さんはオレを招待してくれた。夜景を見ながら語り人さんはこうも言った。『一柳、この高さを忘れるな』」
「おれはそういう意味で言ったんじゃないよ」と僕は言った。
「もちろん、わかってます。オレが途中から目標をすり替えたんです」
「それでも結局あなたは、静岡に39階建てのホテルを建てるという目標を捨てて、東京に舞い戻ってきた。なぜなの? 何か理由がありそうね」玲子さんは核心を突いてきた。
「わたし、わかっちゃいました」茂森愛由美は謎を解く名探偵コナンみたいに言った。「きっと先生ですね。先生が何か行動を起こされた。つまり、先生が会社を辞めて声優になられたんです。身を持って一柳さんに道を示されたんです」
「語り人さん」一柳は僕を見て強い口調で言った。「愛由美ちゃんを絶対に手離しちゃダメっすよ。愛由美ちゃんは語り人さんの思考と完全に同化してます。つまりそれほど…」
「愛してるってこと」玲子さんはこの重い言葉を、軽々と僕に投げつけた。
茂森愛由美はうれしそうに頬を赤らめた。
「語り人さんは、会社を辞めたのは自分自身の問題だって言ってるけど、わかってる。オレをもう一度、役者に戻すために範を垂れてくれたんだ。それでもオレは、決心がつかなかった」
「あるとき、東京に戻る一年くらい前だったかな、語り人さんから朗読劇の招待状が届いた。一筆箋に"絶対に来い"と添えられていた」
「語り人さんは当時、テレビCMや番組ナレーションを中心に、主にナレーターとして実績を積んでいた。そんな語り人さんが朗読劇を…」
「しかも演題は『中原中也─汚れっちまった悲しみに─』作・演出は語り人さん。出演者は語り人さんはじめ、語り人さんが所属する声優プロダクションの声優たち五名で構成されていた」
「行かないわけにいかなかった。なぜってこの演目は、かつて語り人さんとオレが二人芝居でやっていた得意ネタだったから。それを五人構成で? しかも会場は池袋。演劇学校と西池袋公園の中間にあるカフェ・バー」
「先生の、一柳さん思いのパフォーマンスの続編ですね。もう何章目でしょうか」
「あはは。愛由美ちゃん、うまいこと言うね」
「その朗読劇を観て再び役者魂に火がついたのね」と玲子さん。
「それだけ魂を揺さぶられる舞台だったのですね」と茂森愛由美。
「そうだね。朗読の不思議な世界に引き込まれた。台本を手にしたまま微動だにせず、まさに声だけで多彩な表現をする"朗読劇"というパフォーマンス・スタイルにまず驚いた」
「セリフ読みもドラマティックに喜怒哀楽を表出するんじゃなくて、極限まで抑えている。かといってもちろん棒読みとは違う繊細な読みで、それでいて細部にまで感情表現が行き届いている」
「声優たちの声がまた素晴らしかった。これがナレーターなんだと感心した。語り人さんの中原中也は、とくに詩の朗読が圧巻でね。発音の精度が昔とは比較にならないほど洗練されていた。それはプロだから当然だよね」
「語り人さんは声の演技のプロになったんだと思い知らされて、オレは悔しかった。何より悔しかったのは、オレがやっていた小林秀夫の役をオレじゃない誰かがやっていたこと」
「公演が終わってオレは語り人さんに詰め寄ったよ。なんでオレじゃないんすか!って。そしたら語り人さんは笑ってこう返してきた。『だから一年前に呼んだじゃないか。次回はおまえがやれ』」
「語り人さんの作戦にまんまと引っかかったのね」
「そう。まんまと餌に食いついた」
「それからは大忙しだったよ。弟はやっと語り人さんとの約束を果たせるとよろこんでくれた。彼はもう25歳になっていた。奇しくもオレが引き継いだときと同じ年齢。二年前から、いつ引き継いでもいいように準備をしてくれていたんだ」
「発声と滑舌を一からやり直すべく、声に特化したトレーニングメニューを語り人さんに組んでもらった。あらゆるナレーションテクニックを研究し、アフレコとボイスオーバーの声出しとタイミングの練習もした」
「語りさん指導のもとボイスサンプルを作り、そして語り人さんの推薦で、語り人さんが所属している事務所に入った。ぜんぶ語り人さんのお膳立てのおかげだ。オレは最短距離で、声優としてスタートラインに立つことができた」
「聞くまでもないけど、東京での住まいは、語り人さんと同じマンションに?」
「そう。吉祥寺、井の頭公園近くのマンション。語り人さんのいるところ必ず良い公園がある。なにしろ散歩が好きな人だから」
「井の頭公園で毎日、語り人さんと一緒に発声と本読みをやった」
「正直に言います。わたし、いま一柳さんに、激しく嫉妬しています」
茂森愛由美は彼女にはめずらしく感情的な物言いをした。
「一柳さんには声優になれ、わたしには声優になるな、って。わかっています。わたしはいま、感情的になってあらぬことを口走っています。それでも言わせていただきます」
「そうよ! 愛由美ちゃん、もっと言ったんさい、言ったんさい」
玲子さんが茂森愛由美をたきつけた。
「先生と同じマンションで、いつも一緒にいて、井の頭公園を散歩して、レッスンをして。何かあるといつも先生が颯爽と現れて助けてくれて。それでは、わたしが入るスキがないではありませんか」
「いや、愛由美ちゃん、それは10年前の話で…」一柳はタジタジになった。
「私も言わせてもらうわ」玲子さんも参戦してきた。「そこまで一柳さんから愛されている語り人さんに、私は半年前からずっと嫉妬してるわよ」
「池袋で出会って恋に落ちて、同棲同然の生活をして、その後10年間は東京と静岡で遠距離恋愛をして、そして今度はふたりで同じ仕事をして、吉祥寺でまた同棲? どう考えたって異常だわよ。それに」
「静岡にホテルをふたつも持つ社長が、その地位も年収も捨てて、いい年をしてなんで今さら貧乏役者をやる必要があるのよ! いつまで青臭い青春を引き摺ってるのよ! これはきっと、語り人さんの陰謀に違いないわ」
「い、陰謀って、そんな、玲子さん…」一柳は悲しそうに俯いた。
「半年前にあなたから告白されたとき、私はたしかそんなことを言ったわよね」
玲子さんの問わず語りが始まった。
「一年前、あなたがフラメンコ教室にきてから、私はそわそわして落ち着かなくなった。あなたは教室のドアを開けた瞬間からスターだった。女子たちはみんなあなたの虜になり、だから男の先生の何人かはやめていった。そりゃあそうよね。先生よりダンスがうまくて、そのうえイイ男が生徒で入ってきたんだもの」
「お二人はフラメンコ教室で出会われたのですか」
茂森愛由美が意外そうに言った。「先生は、ご存知だったのですか?」
「いや、フラメンコダンスを始めたのは聞いていたけど、そこに玲子さんがいたというのは、今はじめて知った」僕は唇に人差し指を当て、茂森愛由美に言った。
「まあ、とにかく黙って聞こう」
「あなたは純子先生から、あっ、純子先生は教室の主催者ね。男のインストラクターがやめていった責任を取れと、生徒から先生に格上げされた。たった三か月で。私は二年も教室に通ってるのに、三か月しかフラメンコをやっていないあなたから指導を受けることになった」
「じょうだんじゃないって思ったわ。純子先生にも抗議した。フラメンコはそんな上っ面のダンスじゃないってね。私あなたに尋ねたわよね。なぜフラメンコを?って。そしたらあなたはこう答えた。リハビリにちょうどいいと思った」
「リハビリ? ソーシャルダンスの大学チャンピオンだかなんか知らないけど、フラメンコはそんな甘いダンスじゃない。私はそう言って…」
「そう言ってオレを睨み付けると、さっさと帰って行った。次の週、君はレッスンに現れなかった。また次の週も」
「あなたが会社のエントランスにいるのを見たときはびっくりした。あのいけ好かない男、私の職場まで何しにきた!って。純子先生が教えたんだろうって察しはついたけど」
「オレのせいでインストラクターが三人もやめて、そのうえ玲子さんまでやめてしまったら、オレはどう責任を取っていいかわからなかった」
「なに言ってんの。その代りあなたがインストラクターになって、生徒が10人も増えたじゃないの。あなたは教室に利益をもたらした。純子先生も大喜びよ」
「そう言うとあなたは、この二週間でまた5人増えたって自慢した。ふん、どうでもいいわよ、そんな情報。そんなことより何しにきたの? 私を教室に呼び戻しにきたの?って訊くと、謝りにきたってあなたは言った」
「そして、ディナーをご馳走させてほしいんだけど、あいにく自分はこの丸の内界隈は不案内だ。どこか案内してもらえないだろうかと言った」
「そしたら君は、ここにあなたと行きたいお店はないと言った。オレががっかりしていると、新宿まで付き合える?って言って、返事も待たずさっさと大手町の駅に向かってひとりで歩き出した。オレは慌てて後をついていった」
「そこは新宿にあるフラメンコ・パブだった。スペイン料理を食べさせる店で、ショータイムもあるという。店の人はみんな君に一目置いていた。君は女王様みたいだったよ」
「その話はいいわ。そこであなたの話を聞いて、とにかくフラメンコダンスを軽く見てるわけじゃないことは理解した。それでもあなたが、どこか軽薄で表面的で節操のない男だという印象は拭えなかったわ。そして私は、そんなあなたに惹かれはじめている自分が許せなかった。だから教室にはもういかないつもりだった」
「でもその週、君は教室にきてくれた。うれしかったよ。でもずっと不機嫌なままだった。どうして?」
「今まで胸に収めてたけど、じゃあ言うわ。私、気づいちゃったのよ。あなたが純子先生と関係があったってこと。純子先生だけじゃない。真奈美さんともそうでしょう。違う?」
「あっ…」一柳は否定することも肯定することもできなかった。
「そういうの、わかるのよ。女には。いつからか、純子先生のあなたを見る目が変わったもの。真奈美さんも同じ目だった。あなたというオスを見る発情したメスの目」
「それなのにあなたは厚かましくも、私に交際を申し込んできた。なんて無神経な男だろう。私をバカにするにもほどがある! …でも同時に、申し出をよろこんでいる自分がいることも、私は気づいてた。私はあなたが憎たらしかった」
「翌週の教室であなたは、私に交際を申し込んだことをみんなの前で公表した。『みなさん、うまくいくように応援してくださいね』とあなたは笑って言った。どういうつもり? この人はバカなのか。でもそのとき、純子先生と真奈美さんの表情が嫉妬に歪むのを、私は見逃さなかった」
「そして私はハッっとした。この交際宣言を、この男は純子先生と真奈美さんに向けて発したのではないか。自分は三条玲子と交際する。だから君たちとはもう寝ない。どうぞよろしくと」
「ほかにもあなたを狙っているレッスン生がいることも私は知っていたわ。つまりこの宣言は、同時に彼女たちへの牽制にもなる…。そう思うと、私は快感に胸が震えた。この男はバカだけどバカじゃない」
「それからの私は少しずつ、あなたに対して心を開くようになっていった。ジェントルマンで、頭が良くて、高潔な感性と純真な心を持つ男性だということもわかった。ただ、私が初恋の女性だというあなたの主張には、いささか首をひねらざるをえなかったけど」
そう言って玲子さんはフフフと笑った。
「一度、私はあなたに尋ねた。あなたには信頼するに足る、心を許せる友達はいるかって。そしたらあなたは、ひとりだけいると自信たっぷりに答えた。そして語り人さんのことを話してくれた。心の底からうれしそうに、泣いたり笑ったりしながら、いろんな話をしてくれたわ」
「私はうれしかった。そんな素晴らしい友がいるこの男なら、本気で信頼していいのかもしれないって。でも私は、自分の目で確かめないことには納得がいかないタイプなの。それで語り人さんに会わせてちょうだいって頼んだわけ」
「それで、どうだった?」と一柳は尋ねた。
「あなたとよく似ているわ。概ね同じといっていいんじゃないかしら。まさに類は友を呼ぶ。器用なのに不器用で、賢いのにおバカで、大人なのにお子ちゃまで。とにかく、とてもチャーミングな男性です」
「違いはひとつ。あらゆる面において、語り人さんが持っている器のほうが大きくて深い。だからたぶん、さっき語り人さんは一柳さんの孤独と言いましたけど、語り人さんが抱えている孤独のほうが大きくて深い気がする」
「それだけ強い人なのよ、語り人さんは。でもその強さは諸刃の剣でね、誰かを守ろうとして自分を切ってしまうことも多い。だから語り人さんは、実は傷だらけだったりする」
「そのことを一番よくわかっているのが一柳さんなの。女にはなかなか理解できないところだと思う。だから二人は離れられないわけ。あ、ごめんなさい。また生意気なことを言ってしまいました」
「玲子さん、すごい! やっぱりオレが見込んだ女性だよ。ね、語り人さん」
一柳は興奮して、心底うれしそうに言った。
「そんなこと、とっくにわかってるよ」と一柳に返してから僕は玲子さんに言った。「なるほど。お話はよくわかりました。そんな僕たちだけど、今後ともどうぞよろしく」
良かれ悪しかれ、僕は自分を分析されることが苦手だ。この話題に終止符を打とうと、愛想のない常套句の挨拶でごまかした。それを察した玲子さんは、右手を上げるとおどけて言った。
「はい。よろしく頼まれました。そこで、注意事項がひとつありまーす」
「はい、なんなりと」一柳は右手を左胸に当てて恭しく応じた。
「今後あなたたち二人だけで行動するのは控えてください」
「は? なんすか、それ?」一柳の声がひっくり返った。
「言葉どおりです。語り人さんと会うときは、私も一緒です」
「賛成です。先生、一柳さんと会うときは、わたしもお供させていただきます」
茂森愛由美も即座に反応した。
「いや、それは。そうもいかないときだってあるよ。たとえば収録とか。ほかにもいろいろと、ね、語り人さん」
「ああ、そうだね。たとえば収録とか、収録とか、収録とか…」僕の声は尻すぼみ小さくなっていった。
「収録だけでしょ。収録が終わって飲むときは、私たちも合流します。ね、愛由美ちゃん」
「はい。どうしてもわたしと玲子さんが合流できないときは、飲みは禁止です」
「なんで、そうなるの?!」一柳が絶叫した。
「それは、あなたたちが前科持ちだからよ。その声で寸劇やって、また罪を作りたいの? だから、いいわね。女子のいるところでの寸劇禁止。一柳さんは笑顔禁止、ダンス禁止」
「先生は、詩の朗読も禁止です。あと、『邪魔なんかじゃない』ってセリフ禁止です。それから、名刺を渡すことも禁止します。あ、もうひとつ。女の子の個人レッスン禁止です」
「ちょっと待ってよ。オレたちに仕事するなって言うの?」
「なんか、"ふたりだけで行動するな"からズレてきてないか?」
「いい? 私たちの身にもなってちょうだい。ふつうは彼氏の女遊びの心配だけしてればいいところを、男遊びの心配までしなくちゃいけないのよ」
「なんだい、それ?」一柳の目が点になった。
「あなたたちが愛し合っているということよ」
「……」ここは黙ってやりすごすという作戦で僕と一柳は一致団結した。
「それと一柳さん、金勘定は私に任せること」
「えっ、どういうこと?」
「あなたは役者バカでしょ。私の年収以上を稼ごうとか、余計なことを考えなくていいの。そんなことをやってると、ただのバカになってしまう。語り人さんからも愛想をつかされちゃうわよ」
「玲子さん…」そう言って一柳は頭を掻きながら僕を見た。
なるほど、そういうことだったのか。一柳の「金持ち宣言」は、玲子さんと交際もしくは結婚するためには、高給取りの玲子さんの収入を上回る稼ぎが必要だという、男のプライドの問題だったのだ。
「あなたが今、ナレーターとしてもっと上を目指して奮闘していることはわかってる。でもお金のためにがんばらないで。語り人さんのように自由でいて」
「お金ってね、追い求めてはいけないものなの。お金が目的であってはいけないの。それはお金に隷属する道であり、自由への道じゃない。本当の意味での一流への道じゃないの」
「銀行屋がこんなこと言うのは変だけどね」
そう言って玲子さんは自嘲気味に笑った。
僕が一柳に言いたかったことを、玲子さんはいささかの文学的修辞を援用することなく、まっすぐな言葉でぶつけた。あらためて、すごい人だと思った。
玲子さんの説得は続いた。
「あなたにはもうひとつ、上を目指すための大きな目標があったじゃない」
「それってもしかして、39階建てのビルのこと?」
「そうよ。語り人さんに借りを返さなきゃ。私は貸し借りには厳しいの。その目標に全面的に加担させていただくわ。だから、金勘定のことは私に任せなさいって言ってるの」
「でも、オレはもう社長じゃないし、静岡に戻るつもりはないし、ナレーターもやめないよ」
「わかってるわよ。静岡に戻る必要はないし、ナレーターも続けてちょうだい。でないと、あなたのために血を流してくれた語り人さんに申し訳が立たないでしょ」
「でも、どうやって…」一柳には見当もつかなかった。
「あなたには代表権のある会長職に就いてもらう。それから、過去20年間の会社の決算書が必要だわ」
「なんだい、それ?」一柳は怪訝な顏をした。
「それは今度ゆっくり説明する。だいじょうぶよ。私は並みの銀行屋じゃないのよ」
「それから、フラメンコ教室のインストラクターはもうやめてね。もちろん私もやめるわ。リハビリはもうすんだでしょ。これからはふたりでソーシャルダンスをはじめるの。目指すはシニア部門のチャンピオンよ」
「えーっ?」一柳は飛び上がらんばかりに驚いた。
「だって、今度こそ本当のパートナーを見つけたんでしょ? ひとりで踊るフラメンコはもう卒業。よろしく頼むわよ。一柳先生」
「玲子さん、いきなりそんなにいろいろ言われても、オレ、頭がついていかないよ」次々と繰り出される玲子さんの新計画に、一柳は困惑しているようだった。
「一柳、とにかく玲子さんの言うとおりにしろ」と僕は言った。「玲子さんは、おまえに取り戻してもらいたいんだよ。心ならずも失った、おまえが一流である証明を」
「ええ、そうよ。まだ失効していないわ。私が取り返してあげる。それがこれからの私の目標」
「素敵です、玲子さん! わたしが思うに、お二人はもうすぐにでも…」
「そうだ、一柳。このタイミングだ。愛由美ちゃんのタイミング出しを信じろ」
「わかってます」と頷いて、一柳は深呼吸をしてから玲子さんを直視した。
「ちょっと待って」玲子さんが制した。「詩とか小説の引用はやめてね。ちゃんと私に向けて、ふつうの言葉でストレートに言って」
「わかってる」もう一度、大きく深呼吸をしてから一柳は口を開いた。
「この年まで独りでいたのは、君を探し歩いていたからだ。待たせたね。道に迷って遠回りしちゃったけど、やっと探し当てた。だから、もう離さない。結婚してください」
「ほんとに、何してたのよ。寄り道ばっかして…」玲子さんの目から大粒の涙がこぼれた。
「でも、信じて待ってた。だから、私も独りでいた。あんまり遅かったから、つい意地悪しちゃったの。でもうれしかった、迎えにきてくれて。ありがとう。結婚の申し出、よろこんでお受けします」
「すてき! おめでとうございます!」
茂森愛由美は激しく手を叩いて二人を祝福した。
それから玲子さんはあらためて僕を見て言った。「語り人さんには心からお礼を言います。ずっとこの人の面倒を見てくださって、本当にありがとうございました」
「いや、そんな。玲子さんにお礼を言われることじゃ…」
「あとは私が引き取りますので、どうかもうご心配なく」
「はっ? それはどういう…」
「玲子さん、もうやめなさい!」
一柳は玲子さんをたしなめたが、玲子さんはおかまいなしに、今度は茂森愛由美を促した。「さ、愛由美ちゃんも言いなさい」
「はい」と返事をして、茂森愛由美は一柳に向かって言った。
「もう一柳さんには玲子さんがいるのですから、これからは先生を煩わせないでくださいね。先生は満身創痍なんです。今後はわたしが、先生の傷のお手当を担当しますから、ご心配には及びません」
「あ、愛由美ちゃんまで、何を…」一柳は信じられないという顔をした。
僕はなんとなくわかっていたので、黙って様子を見守っていた。
少しの間があって、二人の女子は声を揃えてけらけら笑った。
「冗談よ」玲子さんはしてやったり、という顔をして言った。
「わたしは、前半が冗談で、後半が本気です」と茂森愛由美。
「二人は分身だものね。誰もあなたたちを引き離せない」
「オレと玲子さんだって、誰にも引き離すことはできないさ」
「天国でもともとひとつだった魂は」と僕は言った。
「この世に生まれてくるときに男性と女性に分けられて別々に生まれてくる。だから、現世で天国時代のもう片方の自分に出会うと、身も心もぴたりと相性が合うと言われる。その相方をベター・ハーフと呼ぶんだよ」
「そうよね。ベター・ハーフは男と女だものね。語り人さんと一柳さんがベター・ハーフじゃないことがわかって安心したわ」
「それがそうとも限らないんだ」一柳が言わずもがなの知識を披露した。
「ベター・ハーフの語源は古代ギリシャに遡るんだけど、プラトンの『饗宴』によると、"男と女"のほかにも"男と男"、そして"女と女"という三種類が存在したそうだよ」
「それなら、やっぱりあなたたちがベター・ハーフなわけ?」
玲子さんはまたしても眉を吊り上げた。
僕は一柳を睨みつけると、玲子さんをなだめるため説明を捕捉した。
「いや、それは違う。アンドロギュノスと呼ばれる"男と女"以外は同性愛者として生を受けるそうだ。言うまでもないけど、おれと一柳は同性愛者じゃない。安心してくれ」
「あなたたちは無類の女好きだものね。うん、うん。そうよね!」そう言って玲子さんは機嫌を直したが、この時点で僕は、玲子さんのキャラがつかめなくなっていた。
「そう。オレと玲子さんは正真正銘のベター・ハーフだぁ!」
そう叫ぶと一柳は、玲子さんに手を差し出し「Shall we dance?」と言った。
「すごーい!これが噂に聞いた一柳さんの必殺技"Shall we dance?"ですね。しびれちゃいます!」茂森愛由美が無邪気によろこんだ。
「うん。僕も久しぶりに聞いたけど、あいつのこんな優しさと慈しみに溢れた本心からの"Shall we dance?"は、はじめてだよ」
二人は手を取り体を寄せ合い、ワルツのステップを踏み出した。
「そう、玲子さん、じょうず。そう、アン・ドゥ・トロワ、アン・ドゥ・トロワ、アン・ドゥ・トロワ…」
優雅で美しい二人のダンスを眺めていると、茂森愛由美が僕の手を握ってきた。反射的に僕はその手を握り返した。握り返してからしまったと思い、僕はわけのわからない言い訳をした。
「ごめん。僕は踊れないんだ」
<完>
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 気分転換に公園へ行こう。公園は人間観察にもってこいの場所だ。そこには一柳みたいな人、ラッパさんみたいな人がいる。もしかすると語り人がいるかもしれない。ひとりで行くのがつまらなければ、友達や恋人、夫婦や家族など、隣に気の合う誰かがいてくれればなお素敵だ。
- 大小問わず何か目標をひとつクリアしたら、誰かのためになる「善き行い」をしよう。ひとつひとつ目標を達成していくためには、そういう善の循環が必要だ。
- 誰でも「ああ、もう死んじゃいたい」と思うときがある。そんなときはこれが最後だと思って、好きなことに死ぬほど力を注いでみよう。「もうダメだ」の先に視界が開くポイントがある。
- 家族の事情、経済的な事情、人間関係の事情、いろんな事情で夢を断念せざるを得ないときがある。あきらめきれず歯を食いしばって這い上がろうとする人。見せてくれ、君の粘りを。聴かせてくれ、君の声を。
- 今日の名台詞は玲子さんが言ったこれ!「お金ってね、追い求めてはいけないものなの。お金が目的であってはいけないの。それはお金に隷属する道であり、自由への道じゃない。本当の意味での一流への道じゃないの」
- 男性諸君に告ぐ。女性を待たせてはいけないよ。待たせる男を女性は決して許さないから。もしもいま待たせているなら、腹を決めなさい!
- 「Shall we dance?」って素敵な言葉だよね。今は小学校の授業にダンスレッスンがある時代。「ごめん。僕は踊れないんだ」なんて言ってる場合じゃない。
- 孤独を愛そう。孤独はあらゆる創造の源だ。賢治の詩にあるように、「その寂しさで音を創るのだ。多くの侮辱や困窮のそれらを噛んで歌うのだ」。みんなでわいわい騒いでいるとき、神さまはきてくれない。ひとりで孤独を噛んでいるとき、神さまはそっときてくれるのだ。
- まだベター・ハーフが現れていないという人。この人がベター・ハーフかどうかわからないという人。見分け方のヒントは、一柳と玲子さんのラブストーリーをもう一度、読んでみて。実は僕も、まだよくわからないんだ。ごめんね。