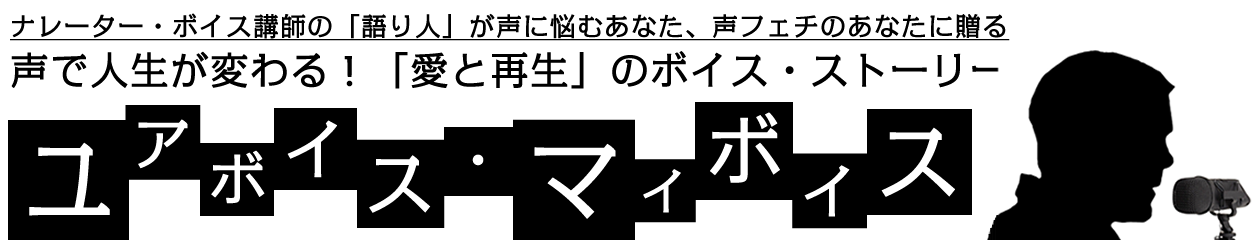「は~い、ぜーんぶいただいちゃいました。ブラボーよ、語り人ちゃん!」
終わって我に返ると、ブースの窓の向こうにスタッフみんなのスタンディングオベーションが見えた。ありがとう! だからやめられない。声優ほど、素敵な商売はない。
(1章「声優ほど素敵な商売はない」のつづき)
「あ~ら、語り人ちゃん。お久しぶりねぇ。会いたかったわぁ!」
スタジオに入るやいなや、太いガラガラ声のオネエ言葉に迎えられた。
1週間というタームが「久しぶり」に相当するかどうかの僕の考察を遮り、
彼は上機嫌で畳みかけた。
「まあ、かたいこと言わないの。もっともこの1週間、先週録音した分の編集作業をずうっとやってたじゃない。だからワタシ、語り人ちゃんの声とともに寝起きしてた、といっても過言じゃないのよ。ちょっとハグさせてちょうだい」
いえ、遠慮願いたいです。という間もなく、毛むくじゃらの太い腕を強引に背中に巻き付けられた。
「アナタ、相変わらずスマートだわね。羨ましいわぁ! 見てよ、ワタシなんかこのていたらくよ」
そう言って黒地に虎の絵がプリントされたTシャツを首元までまくし上げ、でっぷりしたお腹をポンポンとふたつ叩いて盛大に笑うこの人。 オーディオブック『脳内沖縄紀行』の担当ディレクター、 ひげ面のオネエキャラ、虎田シーサーさんその人だ。
顔面ばかりか、腕から手の甲、お腹にまでびっしりと毛が密集している。
「おいおい、腹毛で腹芸か!」という言葉をぐっと飲み込んだ僕は、彼の腹芸と僕のダジャレがこれ以上エスカレートしないようにと、さっそく仕事の話を切り出した。
「シーサーさん、台本は昨日いただいたもので全部ですか。各章の、おそらくエンディングにあたる部分が欠落しているように思えますが」
きのうマネージャーから台本を受け取った僕は、一読して違和感を覚えたのだけど、マネージャーはこれで全部だという。
「そのとおりよ、語り人ちゃん。つづきはここにあるわ」
そう言ってシーサーさんは、かなりの分量の紙束を手に取り、まるでハープでも弾くようにそれを5本の指ではじくと、不敵な笑みを見せた。
「えっ、それを今日、初見で読めということですか」
「そうよ。それがどうしたの。プロフィールによると、あなたの特技欄に初見読みとあるわ。あら、大風呂敷を広げちゃったのかしら」
さっきとは打って変わって、冷ややかな攻撃的な口調でシーサーさんは言った。
Tシャツにプリントされた虎が、今にも襲いかかってきそうな剣呑な空気だ。彼の腹芸にリアクションをしなかったことを怒っているのか。まさか!
でも、言うべきことは言わなければ。鼻から息を吸い、たっぷり丹田(下腹)に溜め込んでから、僕は言葉を発した。
ちなみに「丹田」とは、臍(ヘソ)と恥骨(恥ずかしい骨って!)のあいだの部位。インドではここを「チャクラ(生命エネルギーの集積所)」といい、英語で「センター・オブ・ボディ(身体の中心)」という。悟りを司る聖なるポイントといわれている。
丹田呼吸と呼ばれる呼吸法で瞑想状態に入ることで知られているが、発声ではここを使うことによって、深く力強い声を出すことができる。かつて日本の軍隊などで、上官が弱々しい声の兵士に「臍下丹田に力を込めろ!」と檄を飛ばしたと伝えられている。
もちろん、丹田発声を日々トレーニングしている僕は、仕事以外でもここぞというときにこの発声法を使う。
たとえば重要な交渉事などで相手を説得したいとき。たとえば相手に大事な用件を伝えるとき。たとえば騒がしい居酒屋なんかで、遠くにいる店員を呼びつけるとき(実際これはいつも僕の役割だ)。
それから男性諸君、女性を口説くときも有効だ。子宮に響くといわれる腹式低音ボイスをマスターし、存分に女性の下心をくすぐってくれたまえ(失礼!)。
そして女性のみなさん、高音の鼻にかかったカワいい声だけが男を舞い上がらせるわけじゃないよ。少し低めの艶のあるカッコいい声を「勝負声」にすることをおすすめする。男の前立腺を刺激することうけあいだ(失礼!)。
センター・オブ・ボディ。身体の中心を開いて、愛を叫ぶのだ!
話を戻そう。
言うべきことを言うために、僕は丹田発声を用いてシーサーさんに言った。
「いえ、特技というにはおこがましいですが、初見読みに対応する訓練は積んでいるつもりです。ですが、それはモノによるのではないでしょうか」
ある種のナレーション台本、たとえばテレビ・ラジオCMや生放送なんかの場合、 初見で読むことはままある。
だけどこれはオーディオブック。やはり、 じっくり読み込んで、満を持して臨むべきだろう。下調べだって、役作りだって必要なのだ。
以上のことを僕は、自分の正当性を声高にではなく、誠実さがしっかり伝わる深く安定した声で主張した。
人は相手に攻撃されたり何か理不尽な扱いを受けたりしたとき、自衛本能から感情がたかぶり、心拍数が上昇する。だから呼吸が浅くなり、声が高くなりうわずったりする。これは胸式呼吸になっていることが原因だ。
まさにその見本となる例を、僕たちはテレビのニュース等で最近何度も目にしている。STAP細胞の存在の有無を詰問された小保方晴子さんが発した「STAP細胞はあります」という言葉。いや、言葉ではなく声だ。とくに「あります」の部分は不自然に高く震え、完全にうわずっていた。
こんなときこそ腹式(丹田)呼吸で、お腹にしっかり支えられた声で「あります」と、小保方さんは力強く主張しなければいけなかった。ヘアメイクもフェイスメイクも完璧だったのに、もうひとつ大事なメイクを彼女は怠った。それはボイスメイクだ。
おっと、うまいオチがついたと悦に入っている場合じゃない。小保方さんは今、研究者として絶体絶命のピンチを迎えている。いや、今は自分の心配をしよう。かくいう僕だって(狭い世界だけど)、ナレーターとして絶体絶命のピンチを迎えている。ナレーター生命を脅かされているといっていい。
たとえば、こんな噂が流れたら、僕のナレーター生命は風前の灯火となる。
(語り人、「特技は初見読み」はウソだった!)
(語り人は初見読みにビビって現場から逃げ出したらしい)
(語り人はシーサーさんのギャグをスルーして彼の逆鱗に触れたらしい)
ああ見えてシーサーさんはCMやPV、ドキュメンタリー番組など幅広いジャンルでヒット作を量産する、気鋭の演出家として知られている。彼を怒らせて仕事をほされたナレーターを、僕は三人知っている。ここでしくじったら僕だってただではすまない。
(考えろ、語り人! おまえは1本の葦のように弱い存在だ。でも考えることはできる。ピンチをチャンスに変える逆転の発想を考えるんだ!)とフランスの哲学者パスカルに仮託して、僕は自分を鼓舞した。
しかし、どう考えてもわからない。各章の肝心のエンディング部分だけが、きのうの時点で未入稿だったとはどうしても考えにくい。それは不自然だ。とすると答えはひとつ。シーサーさんはきのう、原稿の一部をわざと抜いて提出したと考えられる。
ではなぜ、そんな手の込んだ嫌がらせを? 僕が何をしたというのか。
僕の声は、シーサーさんの身体の中心を貫くことができなかったのか。子宮を響かせることはできなかったのか(できなかったのだろう。その理由は言うまでもない)。
不自然といえば、今日のシーサーさんはどこか違う。いつものシーサーさんじゃない。オネエしゃべりは健在なのだけど、何かが足りないのだ。決定的な何かが。記憶を司る脳の海馬に鞭を当ててみたが、ダメだ。思い出せない。
1本の葦と化した僕に、シーサーさんはさらに冷ややかな口調で追い打ちをかけた。
「まあ、なんでもいいわ。できるの? それともできないの?」
言われてしまった。男が決して言われてはいけない言葉。
言わせてしまった。女に決して言わせてはいけない言葉。
「まあ、なんでもいいわ。できるの? それともできないの?」
僕は考えることをやめた。1本の葦であることをやめた。
自分の仕事ができること以上に大事なことなんてこの世にありはしない。
だから、返事は決まっている。「もちろん、やります」。
そう応えて僕は、孤独なナレーションブースに潜り込んだ。
深い海底にたった一人で潜る潜水夫みたいに。
長い潜水になりそうだ。
息はつづくだろうか。
そこに景色はあるだろうか。
いや、景色を創るのは僕の仕事だ。
(次章につづく)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 履歴書やプロフィールの「特技」は試されることを想定して記入しよう。あなたが痛い目に遭わないことを祈る。
- 言うべきことを堂々と言いたいなら、腹式(丹田)呼吸をマスターすべきだ。
- 正しいことを言うときこそ高圧的になってはいけない。誠実さが伝わる優しい安定した深い声で。
- ヘアメイク、フェイスメイク、ボディメイクときて、さあ次はボイスメイクの番だ。
- 勝負下着も大事だが、勝負声にもこだわりたい。
- 身体の中心で愛を叫ぶときは、できるだけ紳士・淑女でありたい。
- 言われてはいけない言葉・言わせてはいけない言葉、今日の1位は「できるの? できないの?」
- 自分の仕事ができること以上に大事なことなんてこの世に存在しない。