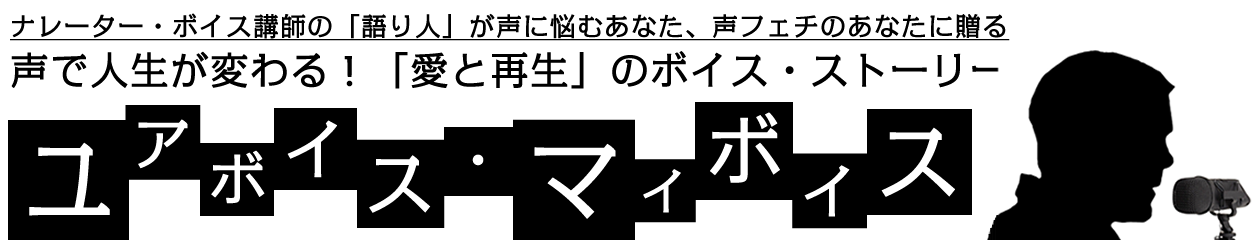「岡本、おまえも一緒に来い」
「おれも大阪にか? なんでだ」
「おれたちの青春を書き直すんだ」
「大阪で青春を書き直す? どういう意味だ」
「この流れだ。少しは想像してみろ」
「まさか、飯倉奈都子が大阪にいるって話か?」
「ああ、あのときのままの飯倉奈都子がな」
(過去からの贈り物(下)のつづき)
岡本との話し合いは概ね、こちらの思惑どおりに運んだと思う。
それにしても、古巣の職場復帰の話が出たときは驚いた。今さら会社人間に戻るつもりもないし、戻れるはずもない。またその器でもない。
岡本、おまえはおれを買いかぶっている。そもそもの始めから、おれは会社に骨を埋めるつもりなどなかった。自分が組織に向かないタイプの人間であることくらい知っている。だから岡本、おまえのせいじゃない。遅かれ早かれ、おれは辞めていたよ。
おまえのおかげで、おまえの嫉妬のおかげで、おれは出世コースから外れ、絶妙なタイミングで、自然な流れで身を引くことができた。そうでなければ仕事が面白くなっていたおれは、あのままずるずると会社に居続けたんじゃないかな。
そうだよ、岡本。あのとき飯倉奈都子が姿を消したのは、これもおまえのせいにするつもりはない。結局はおれと奈都子の問題だからだ。
あのとき奈都子は、おれを追って赴任地にやってきた。おれが呼び寄せたんじゃない。相談すれば反対されるに決まっている。だから彼女は奇襲作戦に出た。
予告なしの来訪に絶句するおれを見て、奈都子はべそをかく子どもみたいなよるべない顔をした。そのくせ「来ちゃった」と言っておどけてみせた。
おまえもよく知っている、おれのおよそ栄転とはいえない、時期外れの、必然性のない海外赴任。その原因の発端はそもそも自分にあると、奈都子は責任を感じていたんだ。
だからうちの内定を手放し就職もあきらめ、16時間かけて海を渡っておれのところにやってきた。ベッドルームがひとつしかない単身用の、お世辞にも快適とはいえない部屋。かつて一世紀以上も前に、有名な画家がアトリエに使っていたという触れ込みだけが自慢の、古色蒼然たるアパルトマンに。
もちろんおれは、すぐに奈都子を日本へ帰すつもりだった。
だが翌日、日本から彼女の大量の荷物が届いた。ほとんどが食品で、保存がきく発酵食品や海藻類、乾麺や菓子類などがぎっしり詰まっていた。それから相当数の本と卒論のための資料。「服は?」と訊くと「衣類はこっちで季節ごとに揃えるつもり」と笑った。
ああ、長期滞在するつもりで奈都子はやってきたんだ。
彼女の言い分はこうだった。卒業のための単位はすでに取っている。あとは八割がた出来ている卒論を仕上げるだけ。食事などの家事はちゃんとやる。だから、どうか私を追い返さないでくれ。
「就職は?」と訊くと「就職はしない」と奈都子は小声で、しかしきっぱりと答えた。彼女はおれの赴任期間の一年を、ここで共に暮らすと決心してきたのだ。どうして追い返すことなどできただろう。
飯倉奈都子と過ごした異国での日々のあれこれを、ここでおまえにつらつら語るつもりはない。ただ、これだけは言っておく。岡本、おまえは誤算をしたよ。奈都子とおれを引き離そうとしたことが、逆に奈都子とおれを離れがたくしたのだ。そんなおまえの誤算に、おれは感謝するべきかな。
だが、おれもまた誤算をした。人生最大の誤算を。
ふたりの異国での暮らしも三月が過ぎた頃だった。こんな言い方をすると、おまえはまた嫉妬に狂うかもしれないが、それはおれと奈都子にとって蜜月ともいうべき、不器用ながらも幸福な生活だった。
ある日、奈都子が買い物に出かけていたとき、おれは何とはなしに奈都子の本を手に取った。それはメディア論の原書だったが、開いたページから一通の封書がこぼれ落ちた。奈都子の大学の担当教授からの書簡だった。
いけないと思いつつも、これは自分が知るべき重要な手紙だと直感したおれは、急いで便箋の文字に目を走らせた。
教授はまず卒論を読んだこと、そしてその内容が素晴らしい出来であることを評価したうえでこう書いていた。「就職の内定を蹴ったのなら大学院に進みなさい。このままではいけない。とにかく一度、帰ってきなさい。じっくり話し合おう。きみの将来のために、悪いようにはしない」
おれが驚いたのは、上から目線のおとながよく言う「悪いようにはしない」という決まり文句じゃない。それは"追伸"として記された文言だった。
「岡本という男が大学に私を訪ねてきた。きみが就職するはずだった会社の人だね。きみの居所をしつこく尋ねられたが、彼に何か普通でないものを感じたので知らないと答えておいた。それでよかったかな?」
いま思えば、おれはもっとおまえを警戒すべきだったのだ。だがそのときは、奈都子の進路のことで頭がいっぱいだった。おれのために彼女の将来を潰すわけにはいかない。とにかく奈都子を日本に帰すこと、それが最優先事項だった。
買い物から帰ってきた奈都子はいつも以上に上機嫌で、ドアをあけるやいなや弾んだ声を出した。「あのね、今日いつものパン屋さんでね、マダムって呼ばれたの。ずっとマドモアゼルだったのに、マダムよ!」
おれは黙ったまま、奈都子に教授の手紙を差し出した。
奈都子の顏に一瞬暗い影が落ちたが、すぐに笑顔を取り戻すと「読んだ?」と悪戯っぽい表情で言った。「心配しないで。卒業式のときにちょこっと帰るけど、すぐに戻ってくるから…」
言い終わるまえにおれは奈都子を遮った。
「教授の意見にはおれも賛成だ。院に進学しろ」
「院にはいつでもいけるわ。今はあなたとここにいることが、わたしには大事なことなの。迷惑…かな」
「ああ、はっきり言って、迷惑だ。これ以上お嬢様のお遊びに付き合うほど、おれは暇じゃない」
「本気で言ってる?」
「知ってるだろ、おれはいつも本気だ」
岡本、おれは本気で嘘をついたよ。
そうしておれは、奈都子を強制的に帰国させた。おまえが待ち構えている東京に。あんなことになるなんて知る由もなく。
あのとき奈都子を手離さなければ。マダムと呼ばれ無邪気に喜ぶ彼女を、思いきり抱きしめていれば。おれは今でも、歯ぎしりするほど後悔しているよ。
おれは奈都子の担当教授に手紙を書いた。奈都子とここで暮らしていたこと、そして近い将来、奈都子と結婚するつもりでいることを率直に伝えた。自分が帰国するまで、どうか彼女を守り導いてあげてほしいと。教授からすぐに返信が届いた。
「きみのことは飯倉くんから聞いている。まずは彼女を帰してくれてありがとう。責任を持って飯倉くんを預かる。だが、彼女を守るのは私ではなく、きみの仕事だよ」
結局おれは、奈都子を守ってやることができなかった。
何よりおれの最大の過ちは、岡本、おまえに奈都子とのことを徹底して秘密にしたことだ。奈都子は奈都子で、大学を卒業するまで誰とも恋愛しないと、おまえに言った自分の言葉に縛られていた。
おまえの奈都子への熱愛ぶりは、周囲の誰もが知っていた。この飛びぬけて優秀な美しい女をものにするのは岡本しかいないと、誰もが思っていたはずだ。一方、おれと奈都子の関係は、おそらく誰ひとり感知していなかっただろう。岡本、おまえを除いては。
おまえだけが、恋する者特有の嗅覚で、おれたちの関係に感づいていた。そして感づいていながら、感づいていないふりをした。検証されていない以上、それは今のところ事実ではない。おまえはそう考えたのだろう。
案の定、奈都子の卒業式の日におまえは現れた。それは想定内だった。大学の正門前に佇むおまえの姿を教授が確認している。教授は機転を利かせ、奈都子を裏門から帰した。奈都子が出てくるのを待って、おまえは何時間もそこに立ちつくしていたそうだな。
奈都子はおまえに申し訳ないと思っていたようだが、おれはおまえに同情はしない。卒業式という晴れの日に、大学を裏門から出て行かねばならなかった奈都子をこそ哀れに思う。
だが、これであきらめるおまえじゃない。
その後の話はおれが語るまでもないが、とにかくおまえは、とうとう奈都子を探し当てた。自然な再会を装い、持ち前の人懐っこさで奈都子の警戒心を解いた。そうして少しずつ、奈都子の生活圏に踏み込んでいった。
もともと奈都子は、決しておまえを嫌ってはいなかった。上からは信頼され、下からは慕われる人望の厚いおまえを、むしろ尊敬していた。
ただ一方で、目的のために手段を選ばないおまえという人間を怖れてもいた。人ひとりを簡単に海外に飛ばしてしまえるおまえの、直情的で容赦ない冷徹さと、会社での影響力を怖れていた。
そんなおまえに見つかってしまったのだ。かくれんぼが終わってもなお、奈都子は「まあだだよ!」と心の中で叫び続けていた。おまえを受け入れることも拒むことも、どちらもできなかったのだ。
自分の出方次第で、またおれに累が及んでしまう。だから、ふたりの関係は断じて知られてはならない。奈都子はそう思った。
それは岡本、おまえにとってむしろ好都合だった。知らないふりをすることで、おまえは自由に奈都子に接近できたわけだからな。人の弱みにつけこむ卑劣なやり方だ。
おれが知っているのはここまで。なぜって、奈都子がいなくなったからだよ。
そうだ。おまえの前から姿を消しただけじゃない。奈都子はおれにも連絡を寄こさなくなった。電話も通じない。アパートも引き払ったらしく、手紙は宛先不明で戻ってきた。
教授か? もちろん電話したよ。だが彼の受け答えは要領を得ないもので、何かあると思ったおれはすぐに休暇を取って帰国し、教授に会いに行った。おまえも行ったんだろう? 教授の研究室に。
ああ、はじめはおれにも「知らない」の一点張りだった。だが、教授が知らないはずがない。彼の表情には明らかに、事情を知っている人の困惑が見て取れた。そしてもうひとつ、おれに対する憐憫の情がそこにはっきりと表れていた。
「頼むから、彼女を探さないでくれ」
やがて教授は絞り出すように言った。
「それで僕が納得して帰るとお思いですか」
おれは教授につめ寄ったよ。
「きみが納得しないのはわかっている。わかっているが、今はそうお願いするしかない」
「なぜ先生が、僕にお願いするんですか? 僕がお願いしているんです。いったい奈都子に何があったんですか? 彼女に会わせてください」
「きみには悪いが、わたしは飯倉くんの意思を尊重する」
「黙って姿を消して、もう会わないというのが奈都子の意思ですか」
「飯倉くんを無理やり帰国させた、わたしの責任だ。本当にすまない」
教授は何度も首を振って、深いため息を吐いた。
「それなら僕も同罪です。彼女を帰したことを、いま激しく後悔しています」
「とにかく心配しないでくれ。飯倉くんは元気だ」
「先生は、奈都子の居場所をご存知なのですね」
「いつか必ず、彼女はきみの前に現れる。それまで待ってやってくれないか」
「それはいつですか。半年後ですか? 一年後、五年後、それとも二十年後ですか!」
おれの剣幕に教授は一瞬ひるんだが、覚悟を決めるように言った。
「飯倉くんとの結婚は、もうあきらめたほうがいいだろう」
「それも奈都子の意思ですか。それとも先生のご意見ですか?」
「これだけは伝えておこう。きみは私への手紙に、飯倉くんと結婚するつもりだ、と書いたね。それを話したら、彼女は目を潤ませて喜んでいたよ」
そう言うと教授は、心から申し訳なさそうな顔をして言葉を繋いだ。
「それなら何故?と、きみは問いたいだろう。だが、その質問はしないでもらいたい。飯倉くんもそれを望んでいる。人生には知らないほうがいいこともたくさんある」
まだ若かったんだな。おれはこうした、上から目線のおとなの常套句が大嫌いだった。「人生には知らないほうがいいこともある」「あきらめたほうがいいだろう」「悪いようにしないから」などなど。
頭にきたおれは、こともあろうに腕づくで教授から真相を聞き出そうと考えた。
「知るべきことを知らないですませる頓馬な生き方を、僕はしたくない。その気になれば、先生の口を割らせることは、それほどむずかしいことではありませんよ」
「きみはやさ男のくせに腕っぷしは強いと、飯倉くんから聞いている。それでも、わたしはしゃべらない。わたしはケンカはからっきしダメだが、暴力に屈しない強さは持っているつもりだ。試してみるかね?」
「奈都子を守るのは僕の仕事だって、先生はおっしゃった。なのにどうして、先生が守ろうとしているんです? いったい先生は、奈都子の何を守ろうとしているんですか!」
「何度も言ったよ。いま私が必死に守ろうとしているのは、飯倉くんの意思だ。いいかね、語り人くん。私たちはもはや、彼女の意思を守ってやることしかできないのだよ。なぜなら…」
教授はここで言い淀んだ。おれの身体に緊張が走った。
次の言葉だ。教授は必ずヒントをくれるはずだ、とおれは直感した。
「なぜなら?」おれは柔らかい声で復唱した。
「飯倉くん自身が守る側を選択したからだ。守られる側ではなくてね」
「さあ、ここまでだ。もう十分だろう。帰りたまえ」
そう言うと教授は、もう何ひとつしゃべらないとばかりに目を閉じ、口を真一文字に結んだ。教授も奈都子の熱烈なファンのひとりなのだと、そのとき思った。
「奈都子に伝言をお願いできますか」おれは最後の手に打って出た。
「言ってみなさい」教授は目を閉じたまま言った。
おれは自分の言葉じゃなくて、奈都子の好きな『かもめ』の、ある台詞の一部分を朗誦した。
「君は自分の道を見つけて、ちゃんと行く先を知っている。だが僕は相変らず、妄想と混沌のなかをふらついて、一体それが誰に、なんのために必要なのかわからずにいる。僕は信念が持てず、何が自分の使命かということも、知らずにいるのだ」
「チェーホフ、かね」教授は薄目を開けて言った。「わかった。伝えよう」
「先生、僕は悲劇を演じればいいんでしょうか? それとも、これは喜劇ですか?」
「チェーホフなら"喜劇だ"と言うだろうね」
おれは笑って「そうですね」と返して、もうひとつ教授に伝言を頼んだ。
「会社は辞める。だから、もう心配するな」
案の定、教授はこの言葉に反応した。目を見開いて、はじめて大声を出した。
「馬鹿なことを言うんじゃない! それじゃあ、飯倉くんは何のために…」
教授はここで言葉を止めたが、もう遅い。これですべてがわかった。
いや、すべてじゃないな。ひとつだけ、わからないことがあった。それが判明したのは、つい最近のことだよ。
「もっと早く辞めるべきでした」
そう言っておれは教授に頭を下げ、研究室をあとにした。教授の上から目線のおとなの常套句を背中に聞きながら。「人生を棒に振るんじゃないぞ!」
岡本、あのまま会社にいたら、おれはおまえを、殺していたよ。
あははは。心配するな。今はそんなこと考えていないよ。そうだな。おまえの命は、奈都子に救われたわけだ。償いをしたい? 償いなんて言ってるうちはダメだな。それは自己満足に過ぎない。おまえに自己満足なんかさせてたまるか。
さあ、物語も佳境に入った。ここからが大事な話だ。岡本、覚悟して聞け。
ひと月ほど前、奈都子から連絡がきた。ああ、Facebookからのメッセージだ。
そして一週間前、彼女は東京にやってきた。そうだ、おれに会いにきたんだ。
二十年ぶりだぞ。正確には二十二年ぶりになるな。
だから、あのときのまんまの奈都子が目の前にいて、おれは腰が抜けそうになった。彼女は四十五歳のはずだ。ありえないことだった。
謎はすぐに解けたよ。
彼女はおれの背後からきた人に視線を移すと、その人に声をかけた。
「あっ、ママ! 語り人さん、やっぱり私をママだと思ったみたいよ」
そうだ。ママと呼ばれたのが奈都子で、ママと呼んだのが娘の"千絵"だ。
チェーホフからとった名前だそうだ。美しい名前だろ?
どうした? 岡本、顔色が悪いぞ。自分の子どもかどうか、心配なのか?
奈都子は最後まで、それを明かさなかったが、おれにはわかった。そして、おれがわかったことに奈都子は気づいた。おまえも、会えばわかる。それまで、悶々と苦しむがいいよ。
二十二年前、お腹に子を宿したことを知った奈都子は、京都の実家に身を寄せた。母方の性を名乗り、名前も漢字を変えた。つまり、それほどおれたちから身を隠したかったわけだ。
おれは奈都子を探さないと教授に約束したから、京都には行かなかった。おまえは行ったそうだな。だが、ここでもおまえは門前払いをくらい、奈都子に会うことはかなわなかった。おまえも、つくづく悲しい男だよ。
ああ、もうこんな時間か。おれは終電で帰るぞ。明日も早いからな。
朝まで飲もうって? バカか、おまえは。昔の話をしてるからって、昔に戻った気になるな。おれたちはもう若くないんだ。ここから先は駆け足で話すぞ。
千絵が三歳のとき、奈都子は千絵を連れアメリカに渡った。
奈都子はもともと帰国子女で、中学まで向こうにいたのは知ってるよな。その家には当時、奈都子の母の弟夫婦が住んでいて、母子はそこに居を定めた。さらに教授の推薦で、近くの大学院に籍を置いたそうだ。ドクターを取得したあとは、美術館や図書館の運営などに携わっていたらしい。
十年後に帰国して京都に戻り、京都と大阪の美術館や歴史資料館、それから劇場やシンフォニーホールの立ち上げに尽力した。さらにUSJのイベント企画を手掛けたりもした。そして現在は、大阪の名門私立大学の教授でもある。
千絵が話してくれたよ。二十二年間の奈都子の来歴を。千絵は話がじょうずなんだ。奈都子は、ただ黙って微笑んでいて、おれの表情の変化を見て楽しんでいるようすだった。
驚いたか? おれはうれしかったよ。奈都子は娘を守って、おれとおまえを守って、そしてちゃんと自分も守った。ああ、奈都子は今でもとびきりの美人だよ。そうだ。ずっとシングルマザーだ。
千絵は、おれのことをずっと「お父さんだと思っている」と言った。それから、こうも言った。「ママったらスゴイわよね。だって、私にはお父さんがふたりいるんだもの」
そうだよ。奈都子はおれたちから身を隠したが、娘に対して隠し事はしなかった。千絵が幼いころから「ママが愛した男性」と言って"千絵のふたりのお父さん"の話を聞かせていたらしい。
おい、泣くな岡本。みんな見てるぞ。おれが泣かしてるみたいじゃないか。
では、なぜこのタイミングで、奈都子はおれの前に姿をあらわしたのか。
たぶん、千絵だと思う。千絵はおれたちの、いや、おまえの会社に入りたがっている。母親が果たせなかったことを、自分が果たそうと考えているんだろう。あるいは、これは奈都子が二十二年間、目論んできたことかもしれない。
いずれにしても、過去からの素晴らしい贈り物だと思わないか?
岡本、これからおまえがやるべきことが何か、わかったな。
まだ飲むのか!おまえがそんなに泣き上戸だとは知らなかったよ。
じゃあ、おれは帰るぞ。大阪行きの日程が決まったら連絡してくれ。
(エピローグ)
「なあ、語り人。ひとつ教えてくれ」
岡本はおしぼりで涙を拭きながら言った。
「もう質問は受け付けない。終電に間に合わなくなるだろ」
「なんで、大阪の仕事が必要なんだ?」岡本はかまわず訊いた。
「ああ、そのことか。奈都子と千絵が、どうしてもおれの収録現場を見たいって言うんだ」
「なるほど、そういうことか。妻と娘の"パパのお仕事参観"ってやつだな」
「岡本、おまえやっぱり、おれに絞め殺されたいらしいな」
「おれも、ぜひ見たいよ。おまえの収録現場」
「おまえは見なくていい。パチンコでもやってろ」
「語り人、へたくそだったら会社に連れ戻すからな」
「おお、そりゃ大変だ。死ぬ気で頑張らなきゃな!」
そう言うと岡本は、笑いながら握手を求めてきた。
「時間を取らせて悪かったな。おもてに車を待たせてある。寝ながら帰ってくれ」
「まさかおまえ、社用車じゃないだろうな」
「違うよ」と言いながら、岡本は握手をした僕の手に一枚の紙を握らせた。
「なんだ、タクシーチケットか」
「お車代でございます」
「お車代はふつう現金だろ」
「現金はどうかご勘弁を。これから何かと物入りになるんでね。おい、語り人、娘へのプレゼントは何がいいかな? 二十二年分だからな、そうとう弾まなきゃならんだろう。おまえもだぞ。大阪に行く前に一度、打ち合わせをしよう」
岡本、つくづく憎めないやつだよ、おまえは。
千絵はきっと、おまえのことを大好きになるだろう。
『過去からの贈り物』─ 完 ─