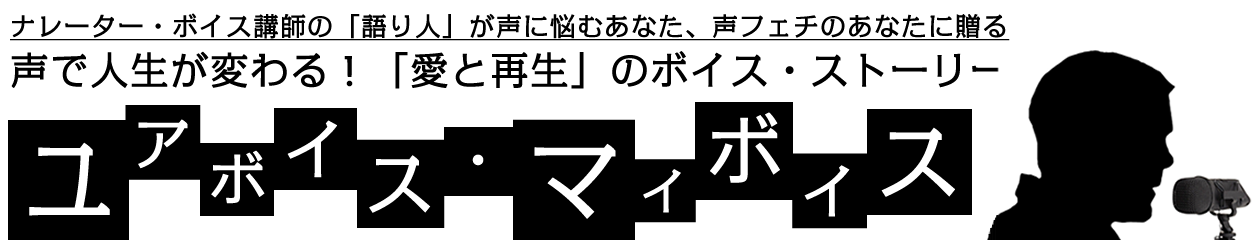あらためて僕はこう言わなければならないだろう。
「頼むから、僕を自由にしないでくれ」
ひとりでいることが自由でないことくらい、
僕だって知っている。
(過去からの贈り物(上)のつづき)
そんな気取ったオチをつけてみが、それにしても、やはり疑問は残った。
秋から年末にかけての、あの雪崩のような目まぐるしい出来事はいったい何だったのか。
何故かくも、この期に及んで、縁の途切れて久しい人たちばかりが何人も、まるで申し合わせたように過去の茶ばんだアドレス帳を引っ張り出して僕に声をかけてきたのか、ということである。なかには「今さら」の感が否めない人もいた。
でも、うれしい再会もあったよ。懐かしさに胸が熱くなる再会も。二度と再び交差しないだろうことを互いに感じながら、笑顔で別れた再会もあった。また会いたい人には「今度はオレに奢らせろよ」と肩をたたき合い、もう会うことのないだろう人には「活躍を見守っている」とエールを送り合った。
温故知新──もっとも人口に膾炙したこの四字熟語の、僕は勇ましい実践者だった。そう、新しい出会いもあったんだ。
今後さらに関係を発展させたいと思える人との鮮烈な出会いがあった。年甲斐もなく恋心を呼び覚まされるような、泣き虫で笑顔の美しい可憐な女の子との清新な交流もあったよ。
それなのに、そんな人たちとの心躍る交流に待ったをかけるように登場した、今となっては「招かれざる客」というべきモノクロームの闖入者たち。
これはいったいなんの「伏線」なのか。あるいは何かの「暗示」なのか。このにわかには信じがたい出来事から僕は何を気づき、何を学ぶべきなのか。
答えはわかっている。
それは「後悔」だ。過去に置き去りにした僕の強い後悔の念が、彼らを今一度、現在に呼び戻したのだ。
誤解や無理解、高慢や偏見、怠慢や諦念、不安や臆病、弱さや自信のなさなど、ネガティブな感情から袂を分かった人たち一人ひとりと、もう一度きちんと向き合い決着をつける。僕にはそうする必要があった。
これは僕にとっての禊(みそぎ)なのだ。そう考えるしか、この不思議な出来事の合理的な説明はつかなかった。
そうして、過去にやり残した「後悔」と言う名の宿題をひとつひとつ、ただひたすら精魂込めて片付けていくうちに、僕の2015年は終わった。
2016年が始まった今、この数カ月間に起こった椿事を振り返って思うこと。それは、このことによって「僕の中の何かが変わっただろうか」ということである。
それはわからない。わからないし、わかろうとも思わない。変化とは、自分ではなく周りが認知することだからだ。
ただ、これだけは言える。僕はもう、過去を苦し紛れに封印したりはしない。後悔を引きずるような生き方はもうしないよ。「人はいくつになっても自分を書き直せる」ことを知ったから。
むろん過去を書き直すことはできない。過去のある出来事を後悔している今の自分を書き直すのだ。
それを教えてくれたのが、過去から突然現れた彼らだった。
突然現れたといっても、もちろん昔のままの姿じゃない。歳月はその分だけ、彼らに年を取らせていた。容色の衰えや精神の摩耗といった容赦ないかたちで。それは僕だってそう。僕たちに等しく与えられているのは、命あるあいだの物理的な時間だけなのだ。
そんな中ひとりだけ、その物理的時間の制約をまったく受けずに生きてきた、そうとしかいいようのない、つまり昔と寸分違わぬ姿で僕の前に現れた人がいた。その人の話をしよう。
二十年ぶりに再会するその人は、間違いなく45歳になっているはずだった。なのに、僕は幻覚を見ているのか。その容姿も体型も、髪形も服装も、眩いばかりの精神の溌剌さも、もう何から何まで、僕の記憶に鮮明に焼き付いている、二十年前の彼女そのままなのだ。
「語り人さん!」昔のままの澄んだ声で彼女は僕を呼んだ。
タイムスリップした人のように僕はうろたえた。周りをきょろきょろと見廻し、それから自分の顏に手を触れ、その手を素早くチェックした。自分に変化がないことがわかると、僕はあらためて視線を彼女に戻した。
「な、奈都子…なのか?」僕は咄嗟に少し若い声をつくったはずだが、その声が二十年前と遜色ないか、そんなことがひどく気になった。
(過去からの贈り物(下)につづく)