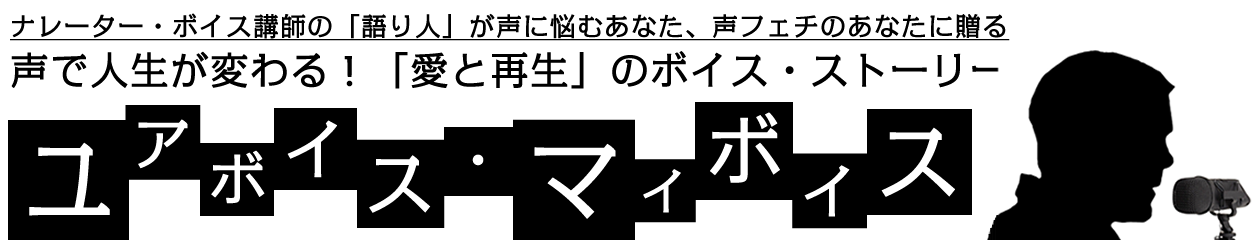大きくなった僕は、アメリカ人と喧嘩するどころかアメリカンガールに恋をして失恋して、そして今は変な米兵に弱みを見せまくり、やつといることに奇妙な安らぎさえ覚えるていたらくだ。そんな軟弱な息子を、父は天国から苦々しい思いで見ているのだろうか。
(3章「日本のアメリカ」)のつづき)
年が明けても僕たちは二日とあけず顏を合わせた。
基地のゲートを挟んで向かい合って言葉を交わす。1時間以上話し込むこともあれば、2.3分で切り上げざるを得なかったり、ただ笑顔を交わすだけの日もあった。ジョージだって仕事をしているのだ。もちろん僕だって少しは忙しい。
おもしろいのは、目の前にいるのにジョージがいるところはアメリカで、僕がいるところは日本ということだった。ジョージはそれをネタにした。
「僕たちは38度線に阻まれた恋人同士みたいだね」
「問題発言を含む笑えないジョークだ」
「毎日のように会いにきてくれるじゃないか」
「きみこそ、いつも僕を待ってるじゃないか」
そうだよ。僕は毎日ジョージに会いたかった。初めて会った日、彼が予言したとおり、たしかに僕はジョージを求めていた。
それと同時に男女の恋愛問題や、そこから派生する将来設計といった煩わしい問題から自由になっていた僕は、ひたすら仕事に専心した。声と言葉の力だけを信じて。
どんな案件も気を抜くことなく全身全霊で打ち込んだ。以前は「いい声ですね」としか言われなかった収録現場で「鳥肌が立ちました」と言われるようになった。これって褒め言葉だよね?
自分で選択して飛び込んだ業界。プロでも食べていけるのは3%といわれる、努力が報われることの極めて少ない業界。免許も資格もなく、仕事の保証などどこにもないリスキーな業界。すでにベテランに仕分けされるほどの年月を、僕はここで闘ってきた。
ジョージと出会う前、プライベート面ばかりか仕事面でもスランプに陥っていた僕は、自分の居場所も自分の言葉さえも見失っていた。台本を読んでも言葉が上滑りして、何を読んでいるのかさっぱりわからない始末だった。
それがジョージと会話することで、僕の言語脳はどんどん研ぎ澄まされていった。英語脳を活性化させたことが大きかったと思う。また英語を喋ることで、日本語の発声はこれまでにない響きを獲得していた。
そして何より、ジョージは国境の向こう側でいつも僕を待ってくれていた。
利害関係も力関係もない。その純粋性が、僕を幸せな気持ちにしてくれた。
僕は独りだったけど一人じゃなかった。孤独だったけど寂しくはなかった。
そうして、引き籠るにはうってつけの冬が終わり、僕にとってはいささか面映ゆい春が過ぎ、恵みの雨季がやってきた。僕はこの季節が好きだ。ジョージにあげようと庭に咲くガクアジサイを何本か摘み、雨の中カッパを着て国境のゲートに向かった。
その日、ジョージの表情は暗かった。
「語り人、きみは僕のことが恐くないのか?」
「いきなりどうしたんだ?」
「……」ジョージは黙ったまま俯いた。
「きみの不思議な能力のこと?」
僕は突出した本物の能力に対してはそれが非常に特殊なもの、たとえば超常的なものであれ脳障害がもたらすものであれ、畏敬の念をもって素直に受け止める公正さは持ち合わせているつもりだった。
「あのさ、世の中にはいろんな人がいるよ。何桁の数字もたちどころに暗記してしまう人。一度聴いた楽曲を正確に再現できる人。絶対音感を持っている人はどんな音もドレミで聴こえるそうだ。これは恐いことだと思うよ。どこにいても雑多な音が溢れていてさ、気軽に街も歩けやしない。もっと言おうか?」
「もういいよ。ありがとう」 ジョージの顔に輝きが戻った。「語り人がわかってくれればそれでいいんだ」
「あのさジョージ、何が視えても、もう余計なことを言っちゃダメだよ。また誰かに苛められた?」
「まあ、慣れてるけどね…」
図星だったようだ。
落ち込んでいるジョージを見ていると、僕の中で唐突に悪戯心が湧き起った。ジョージと親しく話をするようになって10か月、僕の英語脳は大学生レベルまでには戻っていたと思う。だから僕は、きっと調子に乗っていたんだ。
「ああ、そうだよジョージ。僕はわかってる。きみの能力の正体をね」
名探偵にでもなったつもりだったのか、僕は芝居っ気たっぷりに言ってみた。
「きみの能力は簡単な心理学だよ。つまりきみは、人の顔色を読み取る能力にとても優れている。それともうひとつ、きみは話の誘導が実にうまい。人の感じやすい部分をピタリと言い当ててるみたいだけど、でも本当は多くの情報を相手の話の中から巧みに引き出している」
僕はたぶん、自分の言葉の力を試そうとしていた。
「たとえばきみは、僕の仕事を言い当てようとニコラス・ケイジの言葉を引用したね。それは役者の言葉だと僕はいなした。するときみは、すぐに表現者と言い換えた。人は誰もが表現者だよ。またきみは、相手の何かを指摘したあと『違う?』と確認を促す。人はこの念押し確認に弱いんだ。『そのとおりだ。違わない』となる。これらは心理学の誘導法で説明できる」
芝居なのか芝居じゃないのか、もうわからない。僕は自分を止めることができなかった。
「もっと言おうか。僕がボストンの女の子と付き合った事実は、僕の英語を聴けばわかる人にはわかることだよ。アメリカに行ったことがないのは、僕の英語がその子の影響しか受けていないことから容易に判断できるだろう。僕の話す英語が30年前と変わっていないからだ。つまり僕の英語脳は青臭い19歳のまま成長が止まっているということ。そこで身長がぴたりと止まったみたいにね。きみはそれに気づいた」
ひと呼吸置いて、僕は自嘲するように続けた。
「ていうか、僕はうっかりヒントをあげちゃったよね。もう四半世紀以上、まともに英語を話していないって」
そうして僕は、泣きそうになりながら言葉の銃口をジョージに向けると、とどめを刺した。
「それがきみの能力の正体だ。インチキ教祖とかエセ霊能者がよく使う手口だよ。違う?」
ジョージは呆気にとられたような顔で目を見開いて僕を見ていたが、一瞬だけ悲しげな、困ったような微笑を浮かべた。そして文字どおり瞬きをする間に普段の笑顔を取り戻すと、今度は声をあげて笑った。
「そのとおりだ。違わないよ。それにしても見事な演説だ!」と拍手をしながら言った。「語り人にはかなわないね。きみこそ、何でもお見通しってわけだ」
ジョージの顏を見たのは、それが最後だった。
(5章につづく)