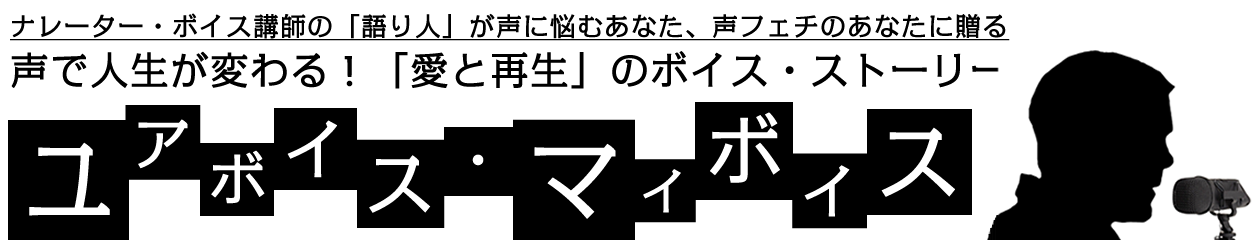それにしても、この黒人にしては華奢でハンサムな男は、いったい何者なのだ。僕の過去や現在が視えるとでもいうのか。「たしかに視えている」としかいいようのない事態に、僕はひどくうろたえた。
(2章 遠いアメリカのつづき)
ジョージは僕のことをよく知っていた。
これまで僕の身に起こったいくつかの重大な出来事や選択した物事、あるいはまた、三日後に起こるであろうハプニングなどを次々に言い当て、僕を驚かせた。
あるときなんかは、翌日起こるはずだったいささかやっかいなトラブルを、ジョージの忠告のおかげで未然に回避することさえできた。けれども、僕はジョージに苦言を呈した。
「教えてくれたことには感謝してるよ。でも、もう言わないでくれるかな。自分で解決したいんだ。何が起こるかわからないのが人生だろ? 僕はこの人生を修行の場だと思ってるんだ」
「修行の場か。どんな経験も甘んじて受ける。語り人らしいね。みんな僕を利用するか、気味悪がって逃げていくかどっちかなのに」
それからというもの、僕たちは会えば肩を叩き合い、いろいろな話をするようになった。ジョージの屈託のない笑顔を見ていると心が軽くなり、気づけばいつのまにか、誰にも言えないようなことまで打ち明けていた。
12月、街がクリスマスの狂騒に包まれる浮かれた季節がやってきた。それは年に一度決まって襲ってくる強迫観念の発作のように僕には思えた。
そんなとき、ジョージの特別な計らいで米軍基地に招待された。
そこは横浜市民とはいえ、おいそれと日本人(外国人)が立ち入ることは許されない領域。僕たち住民が「フェンスの向こう側」と呼ぶ未知のエリアだ。その意味でここもまた、近くて遠いアメリカだった。
「入国」するためには、まずは日本を「出国」しなければならなかった。パスポートを持ってくるようジョージに言われたときはびっくりしたが、考えてみれば当然といえば当然のことだった。
たしかにそこはアメリカだった!
住宅棟とは別に野球やサッカーができるグラウンド、室内のトレーニングジムにプール、テニスコートも三面ある。アメリカの食品や日用品などを揃えたスーパーマーケットもあった。
戸外でバーベキューパーティーが頻繁に行われているらしく、道具類が散乱するスペースがあちこちにあった。そんなところもいかにアメリカだった。
驚いたのは……いや、やめておく。フェンス内は治外法権とはいえ、機密事項に抵触する恐れがある。これ以上の描写は控えるとしよう。
ジョージに連れられ広大な基地内を見学しながら、僕は父のことを思い出していた。むかし父が言った言葉を。
「日本は戦争に負けるわけだ」
1960年代初頭、僕の父は仕事で山口県の岩国基地を訪れた。「そこはまさに別世界だった」。そんな話を、のちに小学校高学年のころ聞かされたことを覚えている。
「当時の日本人が、新しい生活の象徴といわれた三種の神器(白黒テレビ・冷蔵庫・洗濯機)を持つことが夢だった時代、そこには、日本のアメリカにはぜんぶがあった」と父は言った。
広いリビングには巨大な冷蔵庫にカラーテレビまである。靴を履いたまま室内に通された父は、ある種の罪悪感とともに圧倒的な敗北感を味わったという。
何がきっかけで父がそんな話をしたのかは覚えていないが、ふだん子どもとろくに言葉も交わさなかった昭和ひと桁生まれの厳格な父が、珍しく上機嫌で饒舌だったことが僕には嬉しくもあり、記憶に焼き付いているのだ。
「いいか、よく覚えておけ」と父は少し怖い顔をして言った。「父さんはアメリカが嫌いだ。でも喧嘩するにはやつらの言葉が必要だった。もっとも父さんは、追従笑いをしてペコペコ頭を下げてばかりで、喧嘩もできやしなかった。おまえは大きくなったら、やつらと対等に喧嘩しろ」
大きくなった僕は、アメリカ人と喧嘩するどころかアメリカンガールに恋をして失恋して、そして今は変な米兵に弱みを見せまくり、やつといることに奇妙な安らぎさえ覚えるていたらくだ。そんな軟弱な息子を、父は天国から苦々しい思いで見ているのだろうか。
「因縁浅からぬ話だね。半世紀以上の時を経て、父に継いで息子が日本のアメリカに降り立ったわけだ」僕の話に頷きながら耳を傾けていたジョージが感慨深げに言った。
「まるで月に降り立ったみたいな言い方だな」僕がそう返すと、
「まあ、そのようなもんだろ」とジョージは笑いながら言った。
「語り人、きみはもう一生アメリカに行くことはないと思ってた。違う?」
「違わないよ」僕は素直に認めた。
「アメリカと日本が辿ってきた歴史はともかく、きみは今まさにアメリカにいる。アメリカにきたんだよ。こんな効率的な体験ってあるかい?」
「効率的ではあるけど感動的とはいえないな。パスポートを出したのに飛行機にも乗ってないんだよ。まるでどこでもドアから入ってきたみたいだ」
「どこでもドア?」
「うん。ドラえもん。アニメ・映画にもなっている日本が誇る国民的マンガ」
「おお、ドラえもん! ここの子どもたちも大好きだよ。未来からやってきたネコ型ロボットだろ」
僕はドラえもんの道具をいくつか説明してあげた。ジョージは興味しんしんといった様子で聴いていたが、どうやらひとつの道具にしか興味がないようだった。僕の下手くそな英語のせいかもしれない。
「どこでもドアか、それがあればなあ」。溜め息まじりにそう言うと、やがて下を向いてぽつんと呟いた。「結局、僕は誰ひとり救えないんだ」
このときどうしてジョージの心情に寄り添ってあげることができなかったのか。こんな意味深長な言葉をどうして僕はやり過ごしたのか。もっと自分に余裕があったら、もっと英語で深くものを考えられたら……。今となっては悔やまれてならない。
(3章につづく)