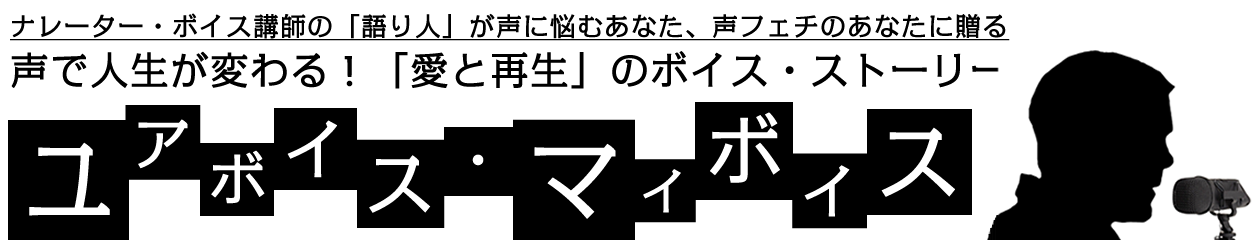結論を言ってしまえば、最後のレッスンで録音した彼の声は、最初のものとは別人といってよかった。
(3章「シャル・ウイ・キャッチボール?」のつづき)
次のレッスン日を決めるメールのやり取りで、彼はいつも、僕が与えた課題(およびルーティーンのトレーニングメニュー)をきちんとこなしていること、そして顕著に現れ始めた「成果」を報告してきた。
とくに忘れられないのが4回目、最後のレッスン日のスケジュールを決めるメールでの報告だった。Mさんの言葉はいつも以上に弾んでいた。
「ここ最近の私の変貌ぶりに驚嘆する職場の同僚からは、恋人でもできたのだろうと揶揄され、インストラクターの担当コーチからは、そこまでいけば11月のインストラクター認定試験は問題ないだろうと、太鼓判を押されました。(中略)私は、本当に、生まれ変わったみたいです!」
そして彼は、最後のレッスン場所に、再びあの場所を指定した。
新宿中央公園だ。えっ、なぜ新宿中央公園かって?
これについては、また別のエピソードでお話する機会があるだろう。
ともかく、あることがきっかけで、僕は新宿中央公園をしばしばレッスン場にしていたのだが、Mさんとの2回目のレッスンもここだった。
メールでMさんは「もう一度だけ、キャッチボールがしたい」と申し出た。
用具は自分で持参しますと、書き添えられていた。
そう、キャッチボール。彼としたキャッチボールについて、少し記しておこう。
2回目のレッスン。はじめてのキャッチボール。
僕たちは大きな声を掛け合いながら、もう汗まみれになってボールを投げ合った。僕は、彼が投げるノーコンの球を全力でキャッチしようと前後左右に走り、 彼は、僕の投げる球を取り損ねてばかりで、そこら中を右往左往した。
その姿はあまりにも無様で、道行く人々の失笑を買ったが、彼は真剣だった。大真面目だった。そして真剣で大真面目だからこそ、そこには祈りがあった。
だから僕たちは、キャッチボールを楽しんでいる人にはとても見えなかったに違いない。まるで何かの苦行、もしくは儀式のように見えた、という人がいたら、それが正しい見方だと思う。
Mさんにとってキャッチボールは、新しい自分を獲得するための通過儀礼だったのかもしれない。
レッスン最終日、これまでのレッスンの総まとめ。
ひとつひとつの項目を丁寧にチェックしていき、今後も続けていく彼のセルフトレーニングに指針を与えた。
そして前回おこなった、彼のインストラクター用の講義台本を、読み口調から語り口調へとスイッチさせるポイントの復習をした。
間の取り方や発声の強弱のつけ方に、もちろん当意即妙とはいかないまでも、安定したリズムと息遣いが感じられた。長足の進歩といっていい。
二度目の、そして最後のキャッチボール。
道具を自分で用意すると聞いたときからある程度の予想はしていたが、彼は僕が投げたボールを、優しい球ならほぼ確実に受け取れるようになっていた。投げるほうも、僕の可動範囲をそれほど大きく外れることはなくなっていた。
何より投球フォームとグラブさばきに、基本動作をいやというほど繰り返した人の「洗練さ」がうかがえた。たったの2週間で、彼はいったいどれだけの練習をしたのだろう。
「キャッチボールは自宅レッスンのメニューに入ってなかったはずだけど。いつ、どこで、誰とキャッチボールを?」
驚く僕に、よくぞ聞いてくれましたとばかりに、Mさんはうれしそうに応じた。
「毎日、会社のお昼休みと終業後にやっているんです」
「すばらしい! でも、よく付き合ってくれる人がいましたね」
言ってから「しまった。これは失言だ!」と思ったが、Mさんは気にすることなく、さらにうれしそうにつづけた。
「語り人さんがおっしゃいました。真っ直ぐ投げれば真っ直ぐ返ってくるって。キャッチボール、いま会社で流行っているんです」
「へえー、すごいな! Mさんが仕掛け人になったんですね」
「仕掛け人は語り人さんです」彼は首を振った。
「いや、私はトレーナーの立場を利用してMさんをそそのかしただけですよ。でもMさんは入社2年目にして、会社でキャッチボールを広めた。立派な先駆者です」
「1ヵ月前の私からは想像もできないです。会社が楽しくなりました」
「キャッチボールのおかげで?」 僕はボールを返した。
「いいえ、声のおかげです。キャッチボールはメタファに過ぎない、でしょ?」 Mさんは速球を投げ込んできた。
「とはいえ、すこぶる実用性に富んだメタファ」
なんとかキャッチして僕は返球した。
「もはやメタファを超えた、有用なコミュニケーションツール」
おお、Mさん、いい球だ。
「その根拠は」と僕は言った。「第一に相手の球を跳ね返すのではなく、いったん受け止めてから投げ返す懐の深さ。第二に、相手との立ち位置の間合いを適宜変更できる自在度の高さ。第三は…」
僕はボールを投げると、Mさんに先を促した。「第三は、Mさんどうぞ」
「私のお株を奪われてしまいました」Mさんは笑ってボールを投げた。
「第三は、会話も可能な適度な運動量と絶妙な距離感、そこに生まれるあうんの呼吸」
Mさんの見事な返球に、僕は心の底から感動していた。
思えば彼が、「どこまでもつづく一方通行トーク」で僕を怒らせたのは、つい1ヵ月前のことなのだ。
秋晴れの新宿中央公園。土曜日の昼下り。僕たちは声を上げて笑った。
笑いながら、僕たちの「言葉とボールのキャッチボール」はつづいた。
どんな関係に見えるかは別にして、もうだれが見ても、単純にキャッチボールに興じる二人の男だった。もしも、仲睦まじいゲイのカップルに見えたとしたら、それは誤りである。断じて!
別れ際、Mさんは何度も何度も頭を下げて、感謝の言葉を繰り返した。
「試験、もう大丈夫ですね。良いインストラクターになってください」
「ええ、まずは。でも、会社は三年勤めたら辞めようと思います」
「それは、どうして?」
「高校の先生になりたいんです。母校の」
僕は彼の顔をまじまじと見据えた。冗談を言っている目ではなかった。
「へえー、教科は何ですか」
「いま高校でもITに関する科目が増えています。私の母校はとくに力を入れています」
「そうですか、それはいい!」
「私のようなロボット人間を増やさないためにも、そうしたいのです」
このMさんの言葉に、またしても僕は打たれた。
「社会経験も積んで、不得手なことも自分の力で克服したMさんなら、かならず良い先生になれますよ」
「それを教えてくださったのは、語り人さんです」
今にも泣き出してしまいそうな自分を抑えて、僕はわざとぶっきらぼうに言った。
「Mさん、ロボット人間に必要なレッスンは? 3つ、言ってみなさい」
「声とキャッチボールと…」
Mさんは少し考えてから、僕の目をまっすぐ見て決然と言い放った。
「それと、愛です」
(おわり)
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 日々のルーティンメニューをしっかり、確実に、愚直にこなそう。
- 有効だと思えば、苦手なこと、自分らしくないことにも挑戦してみよう(Mさんがキャッチボールをルーティンワークに取り入れたように)。
- 実際キャッチボールは、ボイストレーニングにもってこいだ。声量のコントロール、声の収束性と方向性を養うことができる。
- 多くの人が「自分を変えたい」と願う。そして多くの人が「やっぱり変わらない」と嘆く。最後までやりもしないで。では、最後までとはどこまでか。もちろん目的を達成するまでだが、まずは身近な人から「最近、変わったね。なんかあったの」と言われるまで。そこが目安だ。
- 「今の仕事(職場)を辞めたい」と思うなら、ひとつでいい、そこで何かを成し遂げてからにしよう。成功体験が人を前進させるのだ。
- 人間関係において「愛」は、「ホスピタリティ(おもいやり・おもてなし)」と同義である。