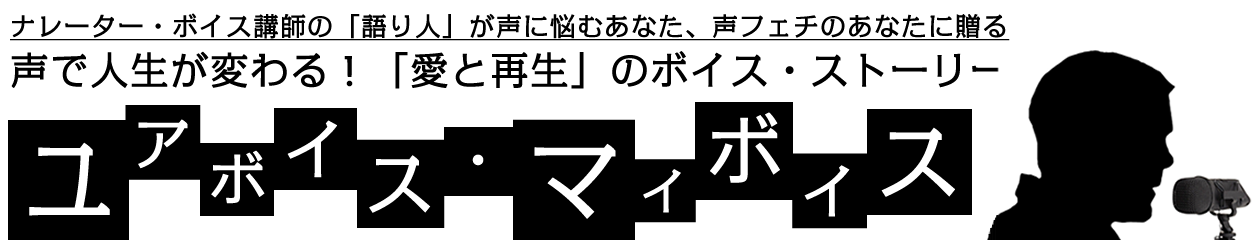「来週はキャッチボールをやりましょう。グラブとボールは私が用意します」
「えっ、キャッチボールは喩えではないのですか?」
Mさんは驚いたようだったが、言った僕自身がもっと驚いていた。
(2章「問わず語りの彼」のつづき)
「もちろん、喩えですよ。でも、最初のメールでも言ったはずです。精神論だけでは何も変わらないと。覚えていますか?」
「はい、覚えています。ですから私は、語り人さんにボイスを習おうと決心したのです。そもそも語り人さんの評判を聞いたとき、私は3つの点で共感を覚えました」
僕がジロリと睨むとMさんは首をすくめた。そうだMさん、その反応だ。それがコミュニケーションだよ。なかなか良い兆候だと僕は思った。
「砂糖の甘さを今さら説明する必要がないのは」と僕は言った。
「だれでも一度は砂糖を舐めたことがあるからです。どうですか?」
「はい、砂糖を舐めた経験ならあります。幼稚園のときでした」
Mさんは遠い目をしてつづけた。
「母の目を盗んで砂糖入れに指を入れてこっそり舐めたのでした。甘美な経験でした。それが病みつきになった私は、3日で砂糖入れを空っぽにしてしまったのです。もちろん母にはずいぶんと叱られました」
3つの理由から彼はお母さんに叱られたはずだ。虫歯に肥満、もうひとつは泥棒というキーワードを挙げればじゅうぶんだろう。
「ご名答です。さすがです! このように、あらゆる事象には3つの…」
「もう結構。そんなこと誰にだってわかります」僕は先をつづけた。
「Mさんは砂糖を舐めた経験はあってもキャッチボールの経験はない」
「ですから、私はキャッチボールを経験する必要があるのですね。素晴らしい!」と言ってMさんは拍手をした。
「素晴らしいのはMさんのほうですよ」僕は拍手のお返しをした。
「その間合いに、その返しです。いまのはナイスプレイですよ」
Mさんはうれしそうにはにかんだ。
「私は実体験のともなわない机上の空論は好まない。 キャッチボールの比喩を使った以上、身体で証明しましょう」
「あの、語り人さん、レッスンでいつもキャッチボールをしていらっしゃるのですか?」Mさんはもっともな質問をした。
「まさか!」と僕は答えた。「するわけないでしょう」
では、これは自分専用のメニューなのか、と彼は心配そうな顔をした。
「キャッチボールは時間に入れませんからご心配なく」と僕は言った。
「私が好きでやることだから気にしないで。1ヶ月でその声をなんとかする、Mさんはそれだけに集中してください」
「おちぇしゅをうかけしまっしゅ」
あえて文字にすると、こんな音が彼の口から洩れた。どうやら「お手数をおかけします」と言ったようだった。
こうして文章にするとよどみなく話していると思うかもしれない。でも彼の発音は、万事こんな調子だった。
さてここで、Mさんの呼吸や発声、音読などのレッスンを通して気づいた特筆すべき点について言及してみたいと思う。そしてこれをもって、いい加減そろそろ、Mさんとのレッスンブログのまとめへと突入したい。
まず彼は、驚くべき心肺能力の持ち主だった。
心肺能力、つまり息が長いのだ。腹式による呼気を測定した結果、彼のワンブレスまでの息は50秒、最終的に1分をクリアした。
毎日トレーニングをしているプロの僕でさえ、1分の壁は厚い。オペラ歌手で80秒という怪物がいるそうだが、それはこのさい度外視しよう。普通はだいたい20秒前後。10秒に満たない人もいる。20秒程度で問題はないが、最低30秒はクリアしたい。40秒を超えれば、声によるさまざまな表現が可能になる。
もちろん呼気が長いのは有利には違いないが、問題はその使い方。呼気に声が過不足なくのっかっていなくては意味がない。というより有害でさえある。
実際Mさんの発声はあきらかに息漏れを起こしていて、声が出ない割に息だけは、まるで蝋燭の火を吹き消すような盛大な風を起こした。そのため彼と対面したとき、僕はしばしば顔をそむけなければならなかった。
必要なのは呼気のコントロール。これは3回目のレッスンで改善された。
また喋るとき、彼の唇はネチャネチャ、ピチャピチャと、実に耳ざわりで不快な音を立てた。リップノイズだ。これはその後、正しい50音の発声と、口周りを中心にした表情筋のトレーニングで克服した。
また音読レッスンに、僕は新聞のコラムを使用しているのだが、Mさんは初見でスラスラ読めた。ほとんどつっかえる場面がないのだ(スラスラといってもあの発声、あの発音だが)。訊いてみると、彼は活字の音読に関しては習熟しているのだという。
「小さい頃、吃音(どもり)がひどかったのです」
「その治療に音読療法を?」僕は重ねて尋ねた。
「それはご両親とか学校の先生のススメで始めたのですか?」
Mさんは首を横に振った。
「では、自分から?」
驚いた。実は僕も幼少の頃、軽度の吃音症を抱えていたのだが、それを治したくて、自ら進んで音読を始めた経緯があった。Mさんとの思わぬ符号を見つけた僕は、もう何がなんでも彼の声と話し方を改善させてやろうと、あらたな闘志を燃やしたのだった。
とはいえMさんの音読は前述したとおり、句読点をまったく無視した、ただ先へ先へと機械的に流していく棒読みで、加えて例の発声・発音である。
本の音読において、僕の場合は幼い頃より、ドラマティックに読み上げたり、声を演じ分けるという遊びに無上の楽しみを見出していたが、Mさんの場合はロボットの声真似に終始した。その違いが今、教える側と教わる側に分岐したのかと思うと、感慨深いものを覚えずにはいられなかった。
そこで僕は、Mさんの音読をこっそり録音した。意識せずに読んでほしかったからだが、それをあとで聞かされたMさんの反応は、想像以上だった。彼はがっくりと肩を落とし、「ひどい…」と、ひと言つぶやいた。
余談だが、ほとんどの人が自分の声や話し方を2割り増しプラスに捉えている。でも録音した自分の声を聞いてみると、はっきりわかる。発音や話し方のイヤな癖が耳につく。声も、なんか変。「えー、これが私の声? 」そう、それがふだん他人が聞いている、あなたの本当の声なのだ。
「ビフォー&アフターのビフォーです。アフターが楽しみでしょ!」
そう言って、僕はMさんを激励した。でも正直、どの程度改善されるのか見当もつかなかった。
いや、もっと正直に言おう。Mさんの声と話し方を劇的に変えるなんて、どだい無理な相談だ。しかも1か月という短期間で…。そう思わなかったといえば、嘘になる。
僕は覚悟した。「ボイス講師の看板をおろすことになるかもしれない」と。
でも、Mさんは頑張った。半端なく頑張った。
結論を言ってしまえば、最後のレッスンで録音した彼の声は、最初のものとは別人といってよかった。
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 精神論では何も変わらない。自ら体験し学習しよう。
- 呼気は長いほうが有利だが、問題は呼気のコントロールと声の乗せ方。
- 新聞のコラムを音読する(例/読売「編集手帳」、朝日「天声人語」、日経「春秋」)
- 自分の声を録音して聴いてみる(90%の人がガッカリするそうだ。10%の人は、すぐにこのブログを閉じてかまわない)。