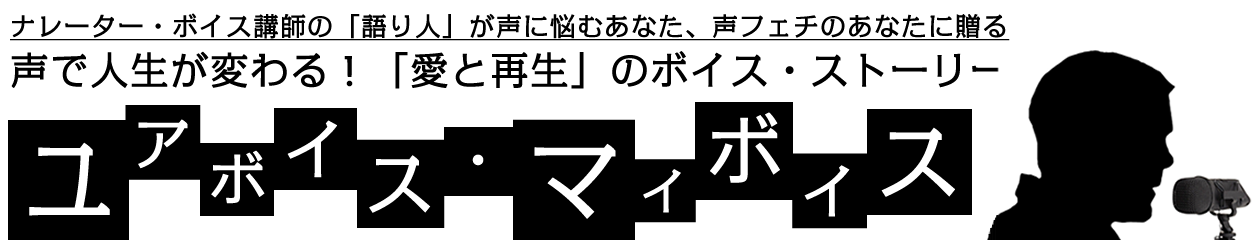彼が何を言っているのか、僕には半分も理解できなかった。
使用言語はたしかに日本語なのに…。
原因はすぐにわかった。それは…
(1章「君の声が届かない」のつづき)
彼の話し方はまるで独り言のようだった。相手に伝えよう、届けようという意思が感じられない。自己完結した喋りといえば、おわかりいただけるだろうか。
あらゆる言葉が、彼の口から出た途端に本来の目的を失い、あるいは虚空に拡散し、あるいは地面に落下した。それは、作り方を間違えた凧を、僕に連想させた。
にもかかわらず、彼はよく喋る。そのくせ、並んで歩いている僕のほうを見るでもなく、その目線はつねに前方のビルの看板か、さもなければ自分の足元に限られていた。
彼の独り語りはとどまることを知らず、ひとつ質問をするたびにこちらが制するまで延々とつづくかに思われた。「へえー」「なるほど」「それでそれで」といった、会話に不可欠な“合いの手”さえ挟む余地がないのだ。
それだけじゃない。彼の話し方には、いわゆる「間」がなかった。句読点のない文章を想像してほしい。読むのに難渋するだろう。それを喋りでやられたら、聞くほうはたまらない。
また口をほとんど開けない発声は、日本語の50音をこのうえなく歪めていた。いくら日本語が口を大きく開けずとも発音に支障のない言語だからといって、自ずと限度がある。
母音、とくに連母音(例:あおいいえ)は口腔内に引きこもったまま外に出ることはなく、子音にいたっては、壊れたロボットさながらの耳ざわりで不気味な音を発していた。つまり、「母音・子音ともにきわめて重篤な症状」といって差支えない。
その症状はもはや「滑舌が悪い」というレベルを超えて、喩えは悪いが「母子ともに瀕死の状態」といってよかった。
原因は、おそらくロボット話法にある。テレビなんかに出てくる「しゃべるロボット」を思い出してほしい。口をあまり開けないで口腔奥でしゃべると、あの声になる。ロボット発声の出来上がりだ。Mさんはきっと、その発声法が癖になっているのだろう。
だから、言っていることの半分も理解できないというのは、決して誇張ではないのだ。
「ちょ、ちょっと待って。いつもそんな話し方をしているの?」
堪らなくなって、彼のどこまでも一方通行トークを遮った。
これはもう、声以前の問題だった。
「ロボットみたいですよね。小さいころロボットの声真似をして遊んでいました。『勇者ライディーン』とか好きで、あれはいまのロボットアニメの先駆けとなるような作品で、いわゆるアニメーションという呼称がまだ生まれるまえの時代、ロボット漫画のテレビ版といった位置付けになろうかと思われますが、それは後の『ガンダム』なんかに発展していくわけでありまして、特筆すべきは…」
「ちょっと、待ったー!」
僕は思わず、いや、意識的に大声を出した。普段は封印しているが、こんなときの僕のひと声は迫力がある。周りの人ばかりか、100メートル先の通行人まで振り返った。(ああ、やってしまった…)
彼がいちばん驚いただろう。表情の乏しかった切れ長の目は大きく見開かれ、長身の猫背がピンと伸びた。ほらね、表情筋も背筋も、ちゃんと動くじゃないか。
「会話はキャッチボールでしょ」
声をもとに戻し、照れ隠しも手伝って僕はニッコリ笑って言った。
「すみません…私はひとりっ子でして」
彼の言葉に、そうだろうね、と僕が相槌を打とうとした瞬間だった。
「ひとりっ子というのは、ご承知のようにこの核家族の時代においてきわめて難しい問題を孕んでおりまして、私の考えではそのティピカルな問題点は3つあると…」
またしても問わず語りが始まった彼の肩に腕を巻き、耳元で僕は優しく囁いた。「もう、大きな声を出させないで」
僕のこの突然のリアクションに彼はハッとしたようで、その顔は激しく赤面していた。こんなこと、されたことがなかったのだろう。免疫のない純情なMさん。いや待てよ。まさか、Mさん…
そのとき僕は、僕たちふたりに注がれている通行人の好奇な視線に気づいたのだった。(ああ、やってしまった…)
いや、みなさん、これはそういうことじゃなくて、この青年をリラックスさせようと思ってですね(怪しいぞ)、いや違う、つまりレッスンの一環としてですね(よけい怪しいぞ)、これも違う、とにかくみなさんが想像しているようなですね…だから、少なくともオレはゲイじゃないって!
世間の心の声に内心でそう叫びながら、そしてMさんがゲイかどうかの判断に苦しみながら、僕は、表面上は威厳と冷静さを崩さぬよう落ち着いた調子で言った。
「Mさん、ひとりっ子が陥りやすい罠の話は、またにしましょう」
「いえ、私が申し上げたのは、核家族におけるひとりっ子の…」
「どっちでもいい!」僕は少しだけ声を荒らげた。
「問題はコミュニケーションでしょ。言葉と気遣いのキャッチボールです。たとえばMさんが、私はひとりっ子ですというボールを相手に投げる。投げるんですよ、相手をよく見て。相手のグラブにしっかりと」
なんて陳腐な喩えを使っているのだろう。われながらうんざりしたが、これで最後までいくしかなかった。僕は半ばやけくその気分でつづけた。
「だけどMさん、あなたはキャッチャーがグラブを構える前にボールを投げている。それもコントロールの定まらないヘナヘナ球をね。それでも相手は全力でそのボールを捕ろうとする。だってそうでしょ? それが気遣いというものですよ。 なんとか捕ったと思ったら、返しを待たず、あなたは立てつづけに次のボールを投げる。それも、だれもいないところに」
「だれもいないところに」と言うとき、僕は肩をすくめ両手を広げる例のポーズをしてみせた。「That’s all」というように。「欧米か!」と自分ツッコミを入れながら。
受け手のいないボールがコロコロと転がって、草薮の中に入って見えなくなる、そんな状況をMさんが想像していることがはっきりと感じられた。じゅうぶんな間をとってから、僕は言った。
「そんな人と、だれがキャッチボールをしたいと思いますか」
ああ、今度は僕がとまらなくなった。
「いいですかMさん、私はひとりっ子です、に対する相手の返球は何だと思いますか。それは相槌だけかもしれないし、私もひとりっ子ですという同意かもしれない。では、もしも相手の返しがなければどうします?」
あまり質問攻めのようになってはいけない。だからここは、相手が考えるための間を置く必要はない。すかさず言った。
「あなたのご兄弟は? と、もう一球投げるんでしょ。わかりますよね」
「はい、わかります」どうやら、イメージできたようだ。
「そうしたボールをときに優しく、ときに鋭く、またときに本気で、ときに遊び心をもって投げ合うんです。Mさん、キャッチボールをしたことはありますか」
「ご推察どおりです。キャッチボールの経験はないに等しいと言ってよいでしょう。そもそも私は運動に関しては、まあ幼少の頃より身体が弱かったせいもあるわけですが、次の3つの理由から馴染めなかったのです。 ひとつは…」
「3つの理由についてはまた後日伺うとして」咳払いをして僕はつづけた。「来週はキャッチボールをやりましょう。グラブとボールは私が用意します」
「えっ、キャッチボールは喩えではないのですか?」
Mさんは驚いたようだったが、言った僕自身がもっと驚いていた。
今日のボイスメモ、あるいは、声にまつわるささやかな教訓
- 会話は言葉と気遣いのキャッチボールだ。
- 会話は相手6、自分4が好ましい。
- 人間関係で必要なもの。寛容、本気、ユーモア、優しさ。
- 同性同士の街中でのスキンシップはNG。